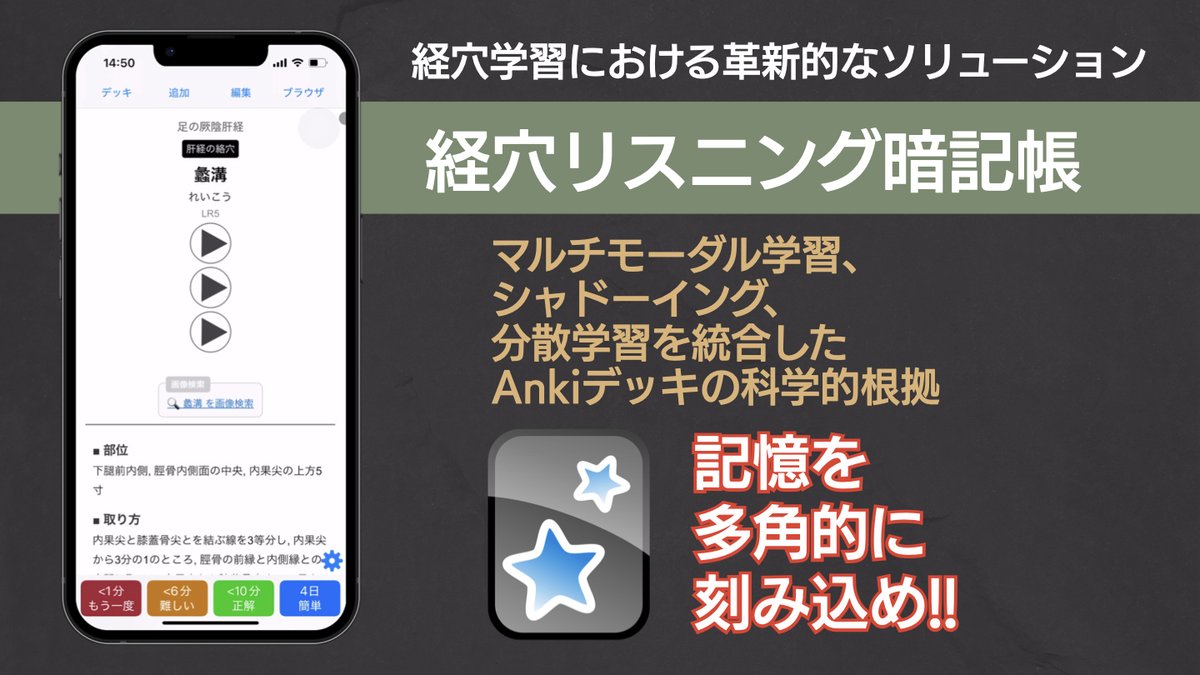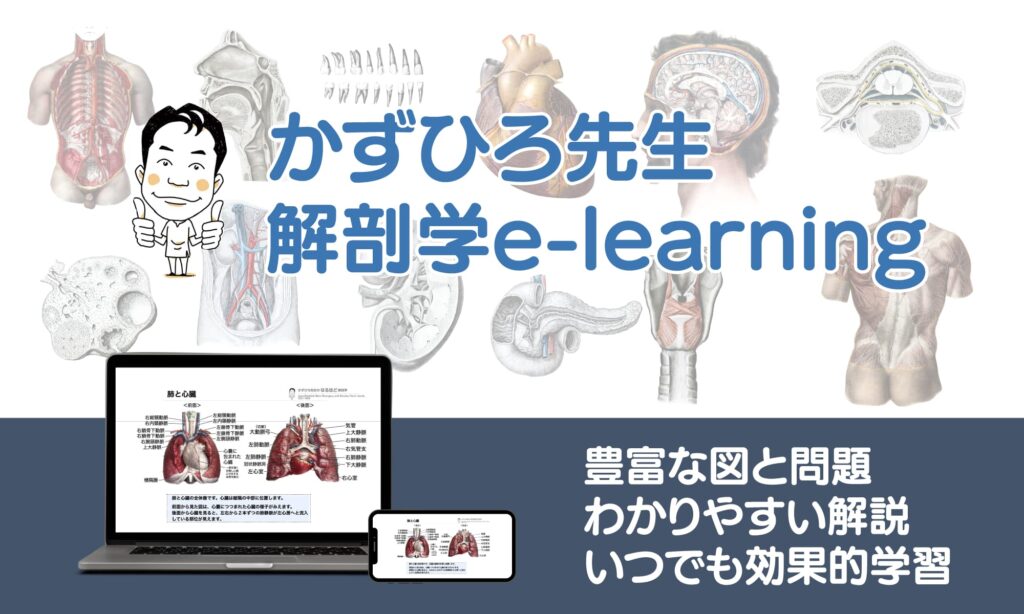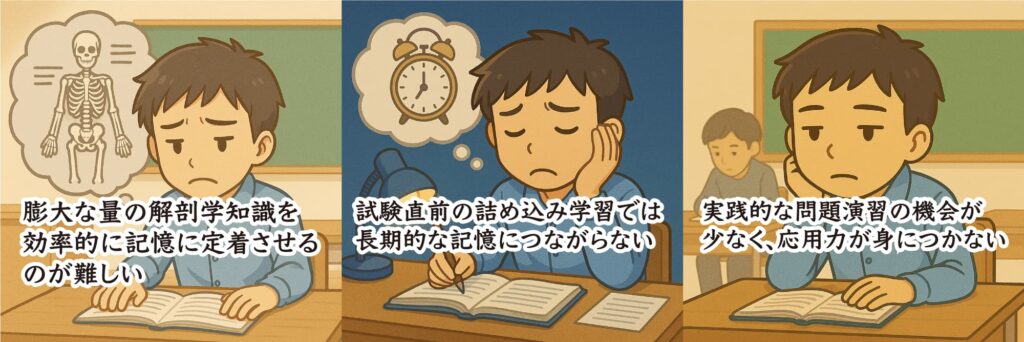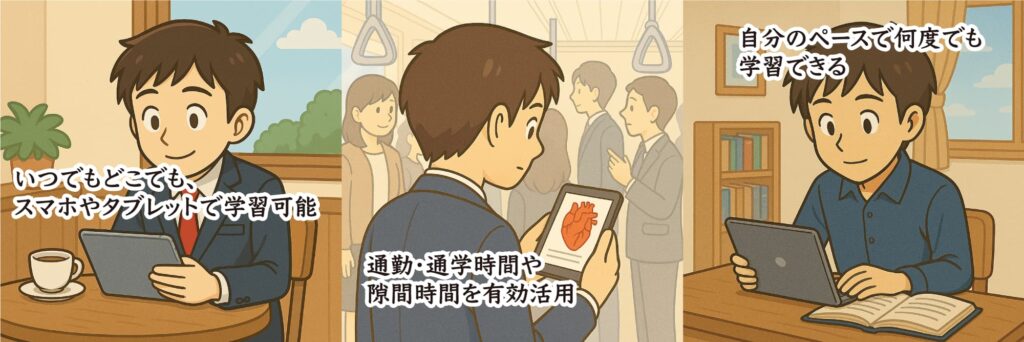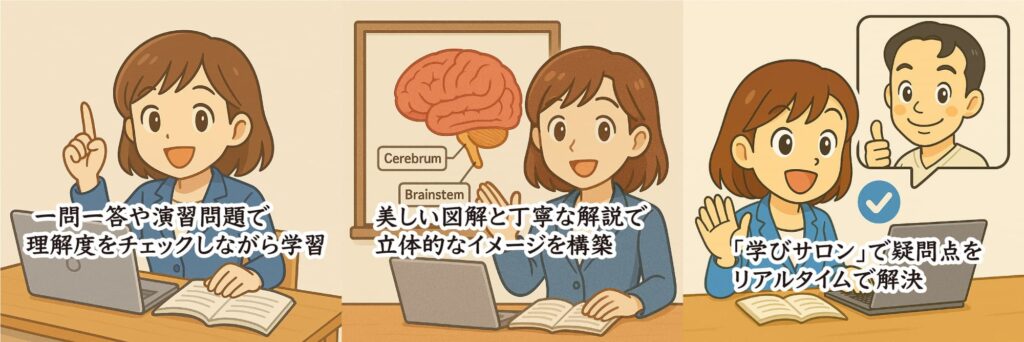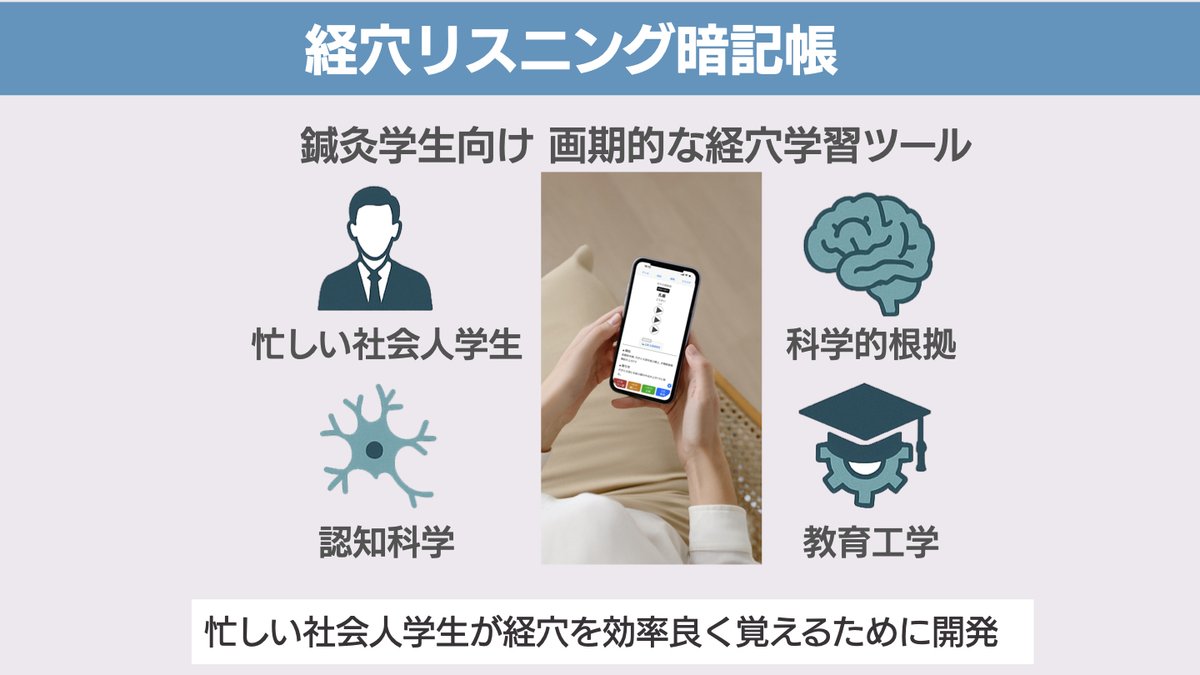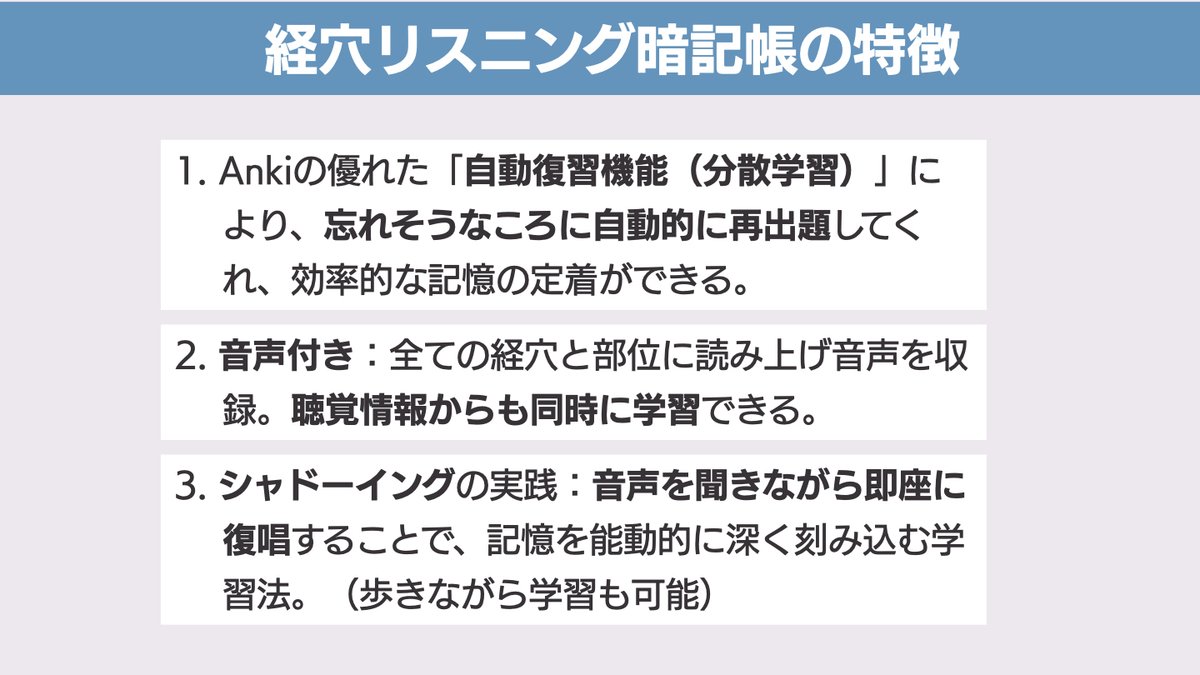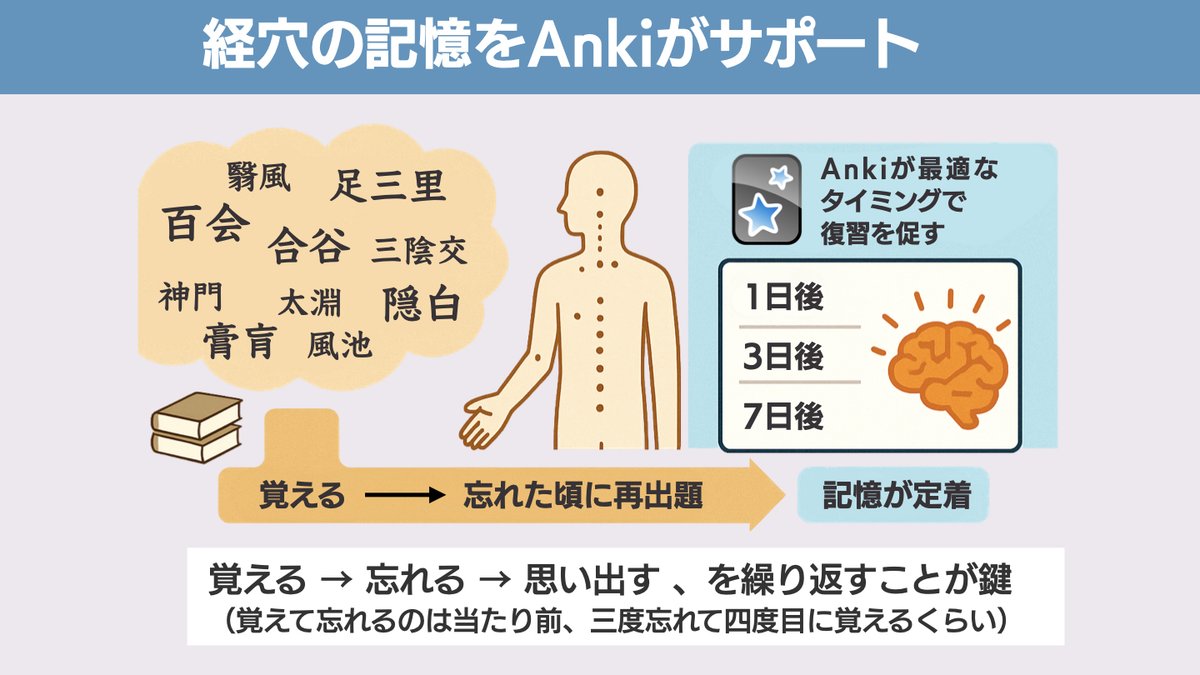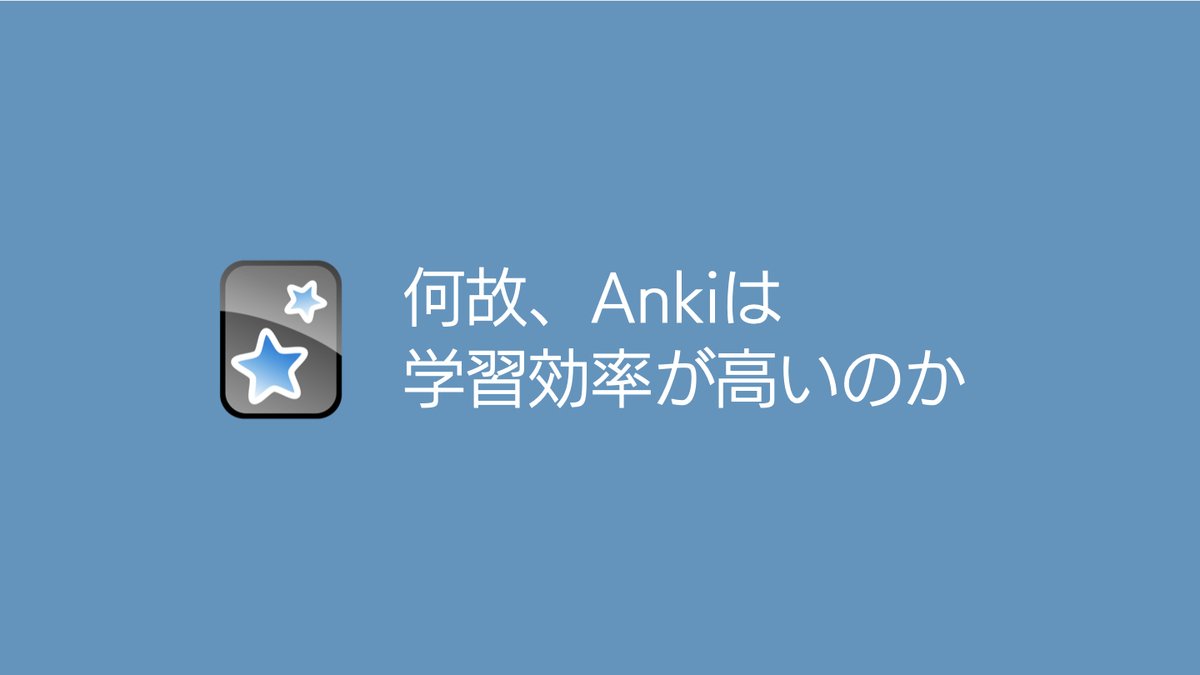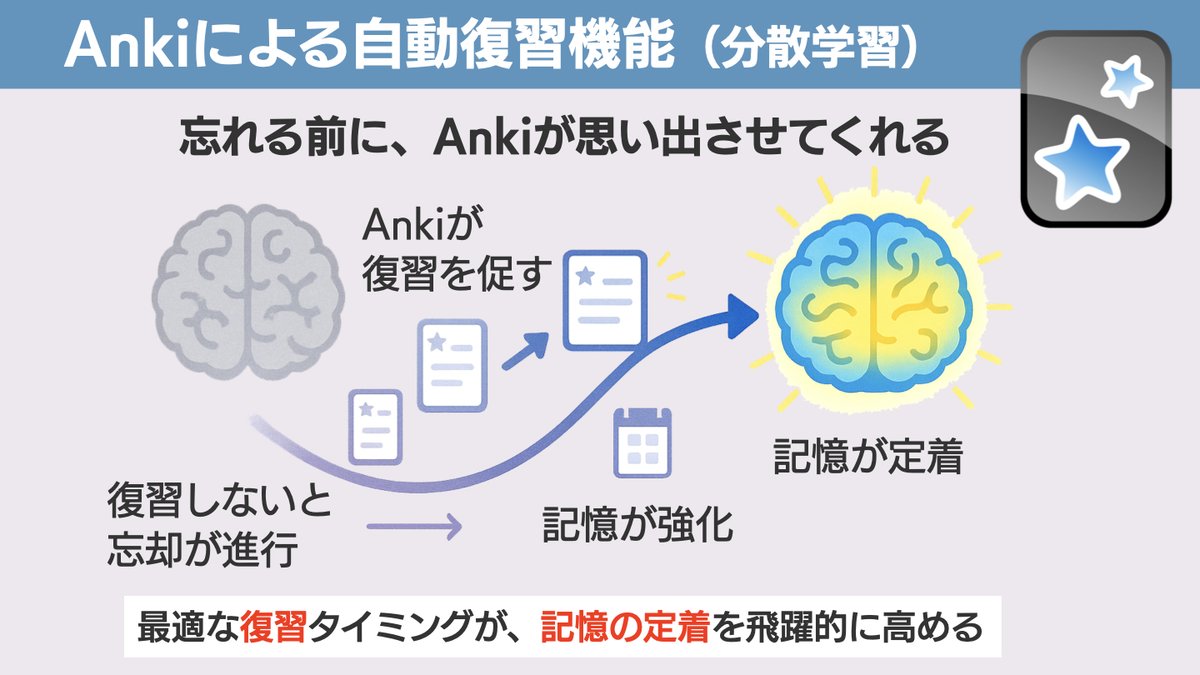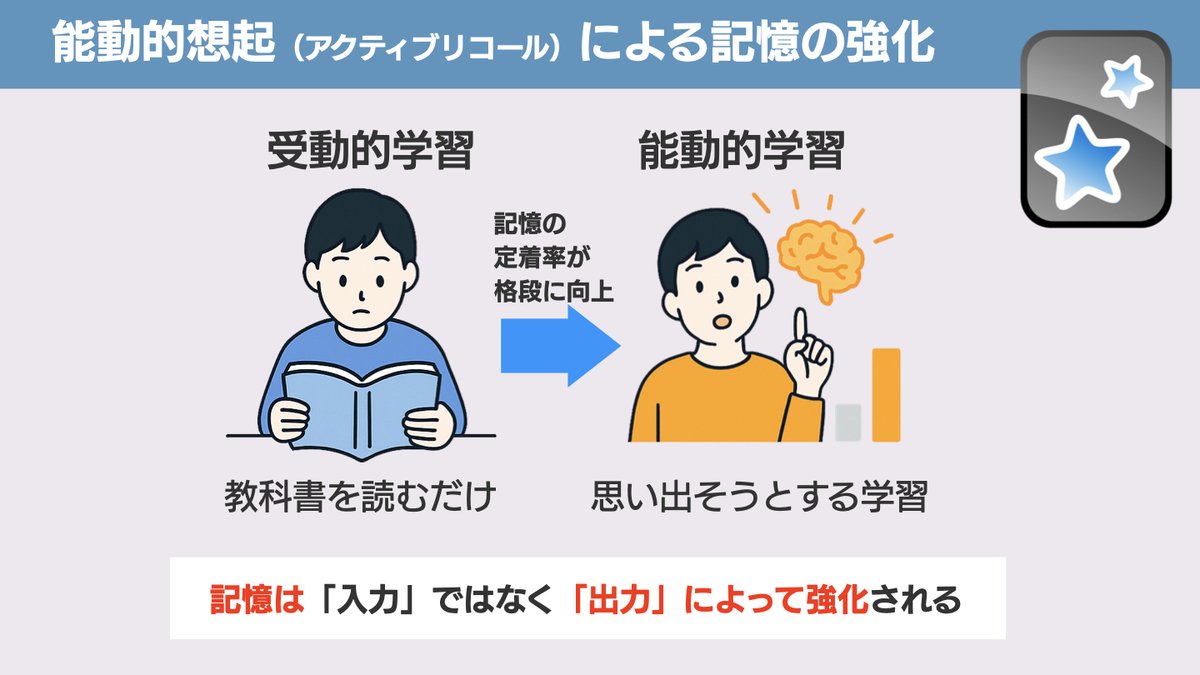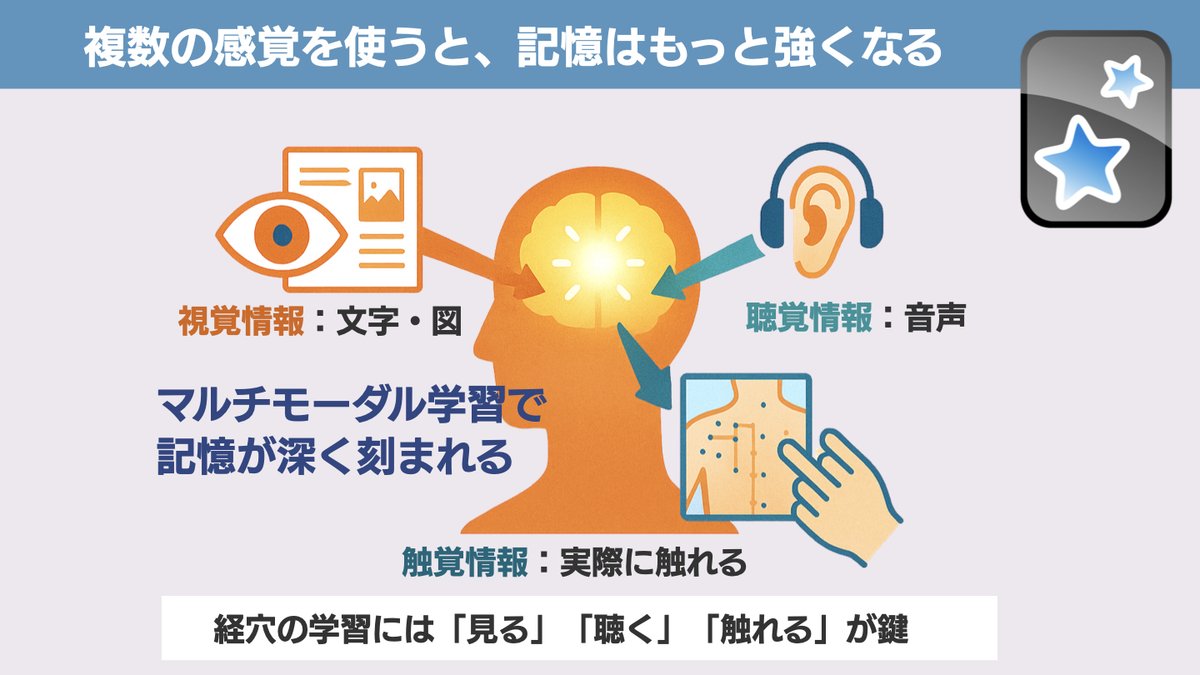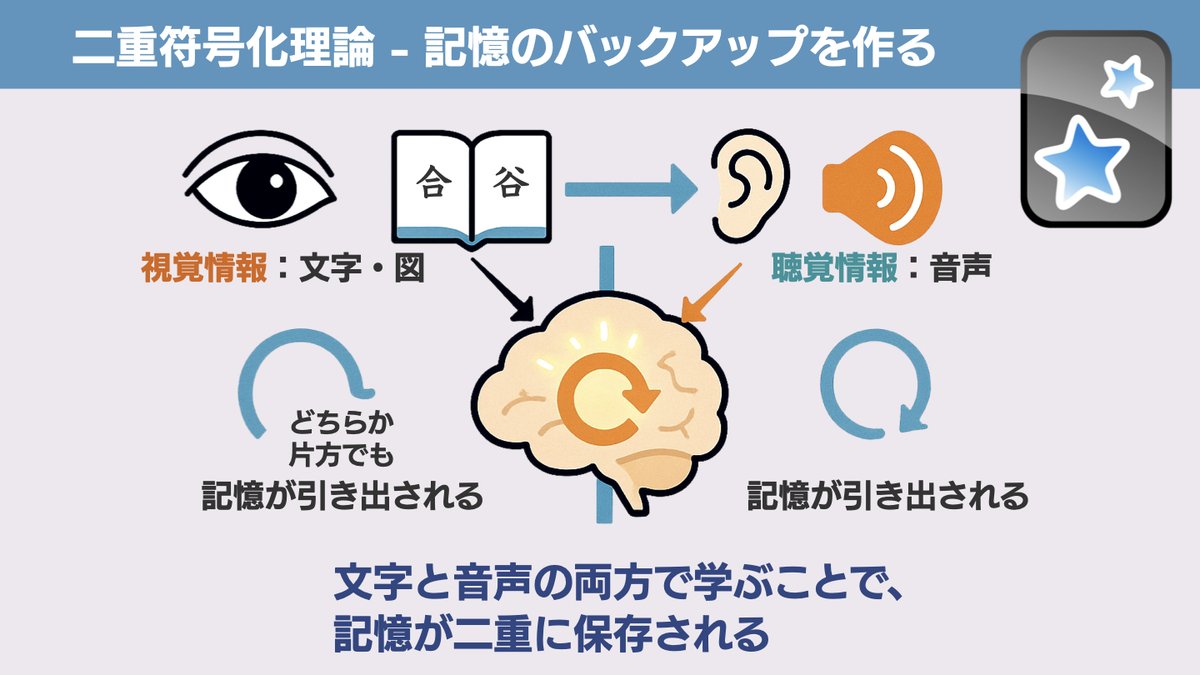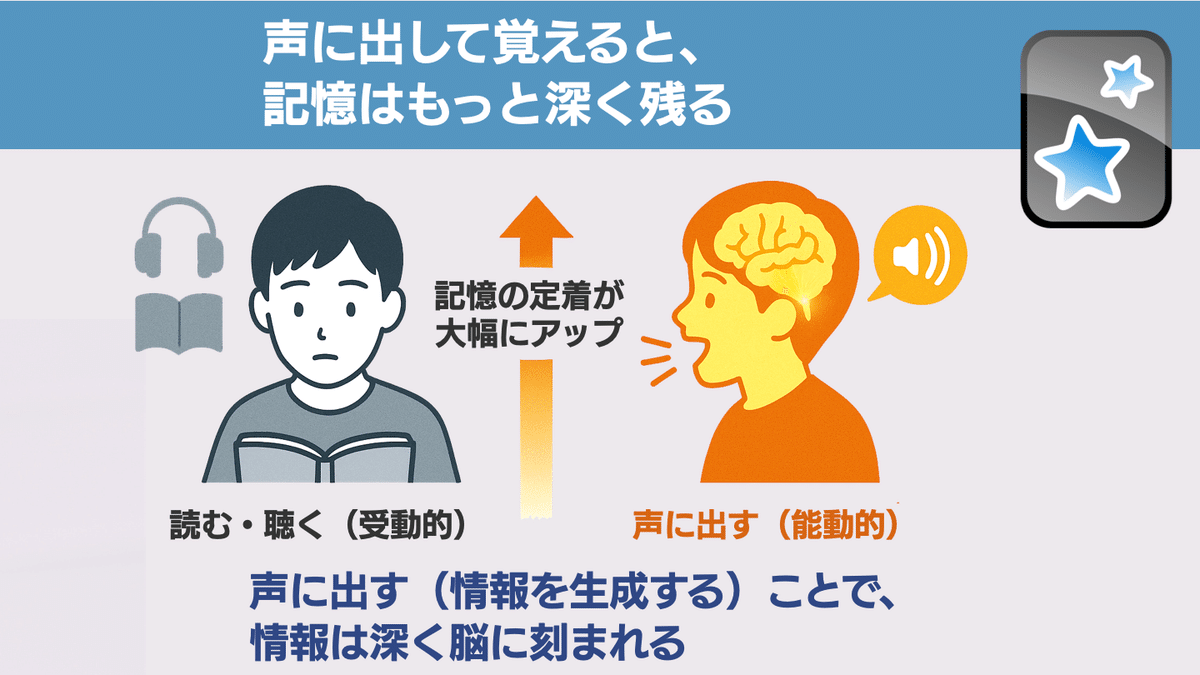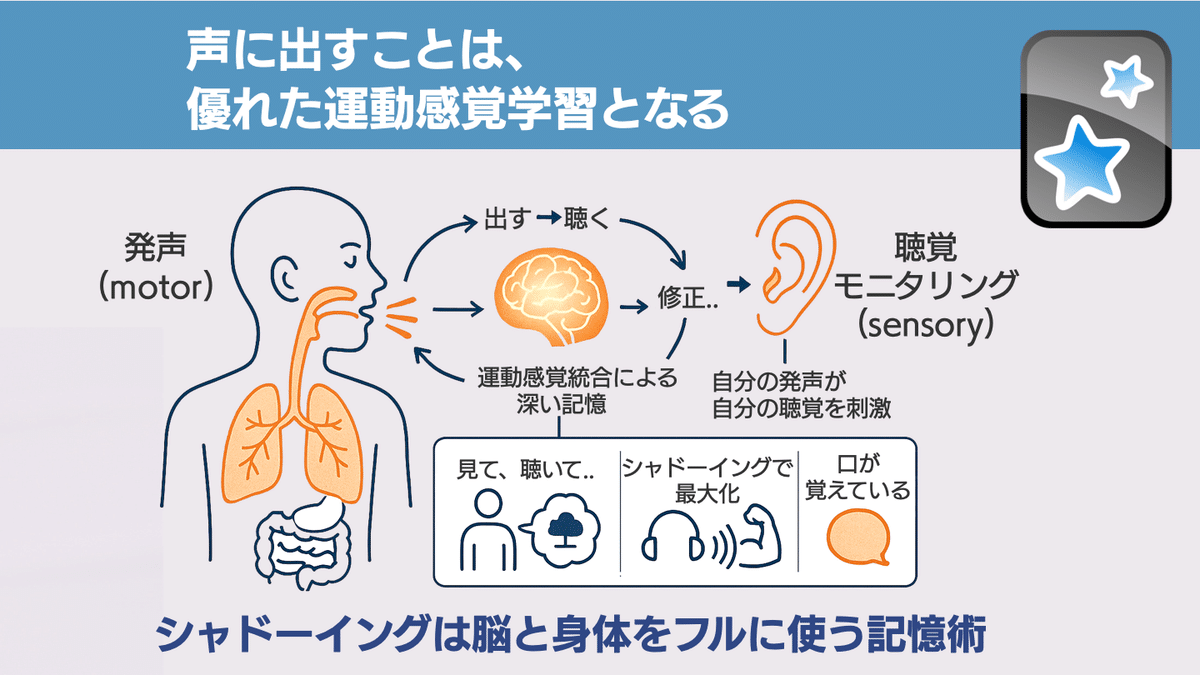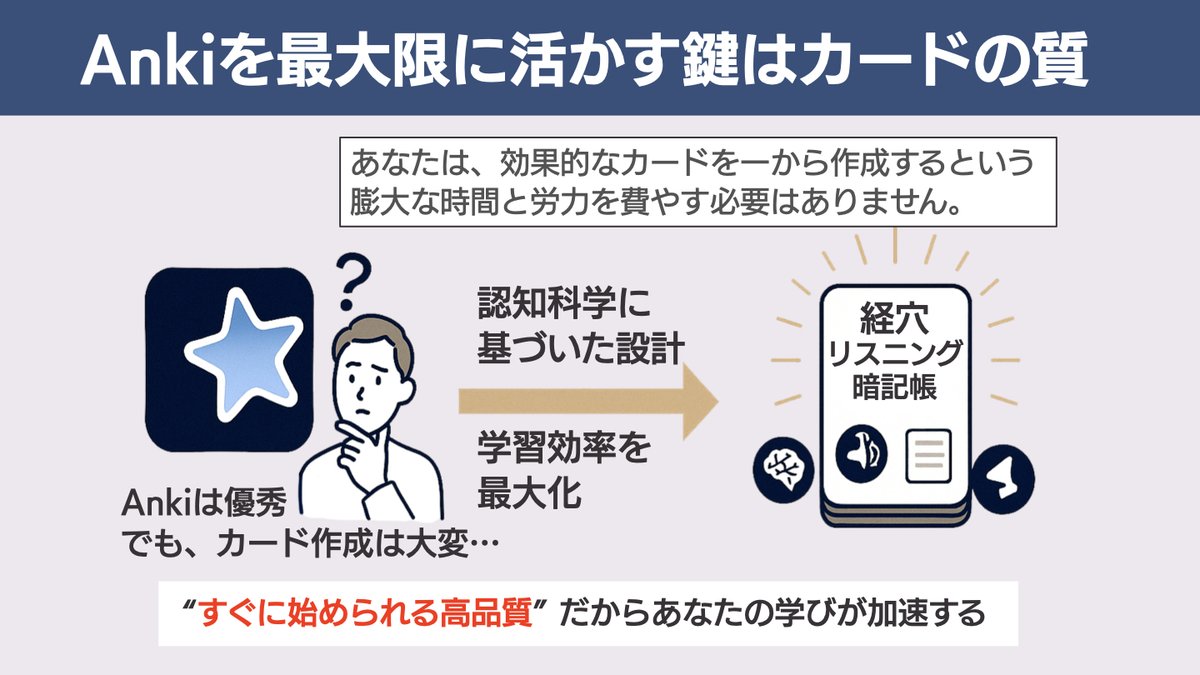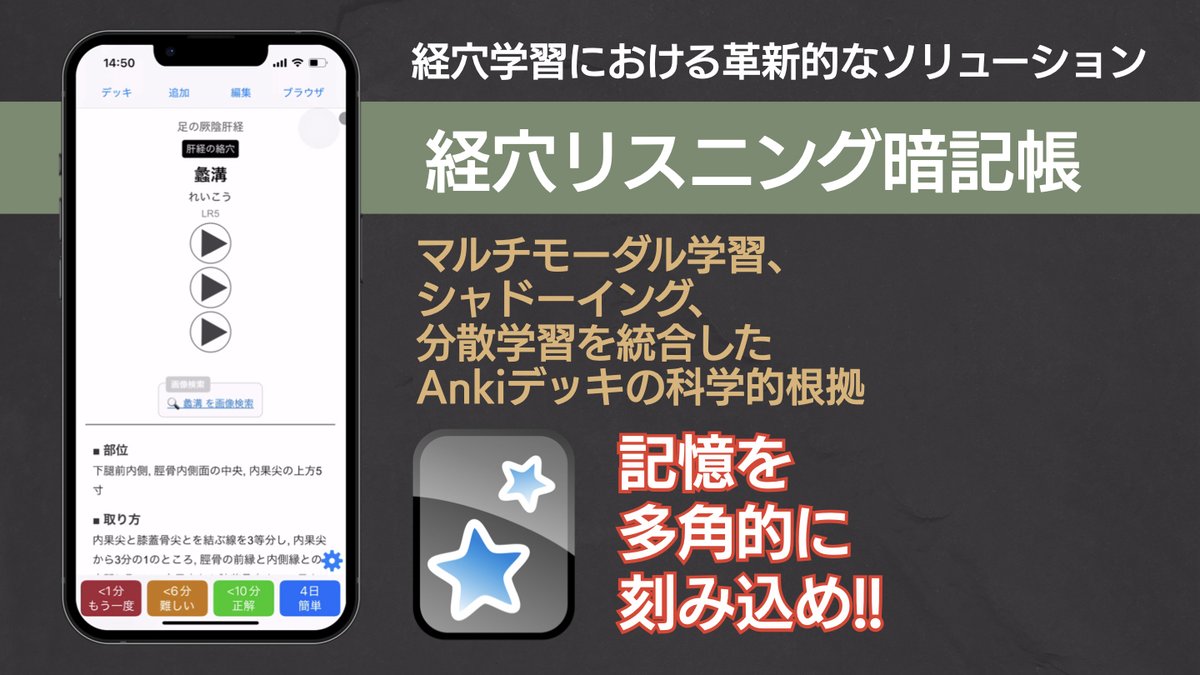引用論文
The efficacy and neural mechanism of acupuncture therapy in the treatment of visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome
「過敏性腸症候群における内臓過敏症治療のための鍼治療の有効性と神経メカニズム」
研究背景
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome; IBS)は、慢性腹痛、腹部膨満感、排便形態の変化を特徴とする機能性胃腸障害であり、全人口の5〜22%に影響を及ぼすと報告されている。中でも腹痛の主因となる内臓過敏症(Visceral Hypersensitivity; VH)は、患者が医療機関を受診する最大の動機となる重篤な症状である。従来、5-HT₃受容体拮抗薬や非吸収性抗生物質、セクレトゴーグ(リナクロチドなど)といった薬物療法が用いられるが、効果は限定的であり、副作用や再発の問題も多い。そのため、薬物以外の補完代替療法として、古くから鎮痛効果が知られる鍼治療(針刺、電気鍼、灸などを含む)が注目を集めている 。
目的
本論文は、IBSモデル動物および基礎研究を対象に、鍼治療がどのような末梢・中枢メカニズムを介してVHを緩和するかを系統的にレビューし、鍼の有効性を支持する神経内分泌・免疫学的作用経路を総合的に整理することを目的とした。これにより、臨床応用へ向けたプロトコル標準化およびエビデンス構築の基盤を提供することを狙いとしている 。
レビュー手法
PubMedおよびWeb of Scienceを2003年1月から2023年2月の期間で検索し、「irritable bowel syndrome」「acupuncture therapy」「electroacupuncture」「moxibustion」など多岐のキーワードを用いて文献探索を実施した。690件の文献から、重複・要旨欠如・臨床試験・レビュー論文・研究テーマ非該当の論文を除外し、最終的に68件の基礎研究論文を抽出した(動物モデル・細胞モデル含む)。抽出後、末梢の感覚終末、脊髄・脳内受容体・イオンチャネル、グリア細胞、HPA軸関連経路の4つのカテゴリーに分類し、各メカニズムを詳細に検討した 。
主要知見
-
末梢神経メカニズム
-
5-HT経路の調節:鍼刺激は腸管内のクロマフィン細胞(EC細胞)による5-HT過剰放出を抑制し、5-HT₃A受容体発現を低下させると同時に、抗炎症作用を有する5-HT₄受容体発現を上昇させる。これにより分泌亢進と蠕動亢進が抑えられ、下痢・腹痛の緩和が得られると報告されている 。
-
TRPV1活性化とグリア細胞抑制:一次感覚終末に発現するTRPV1チャネルを鍼刺激が活性化しつつ、腸管グリア細胞の過剰活性を抑制。これにより、サブスタンスPやCGRPといった疼痛関連神経伝達物質の局所分泌が低下し、末梢感作が軽減されると示唆されている 。
-
エンドゲノムオピオイド系の関与:鍼刺激によりエンドルフィンなどの内因性オピオイドペプチドの遊離が促進され、腸管レベルでの神経興奮が抑制される可能性が示されている。
-
-
中枢神経メカニズム
-
NMDA受容体抑制:脊髄後角および前部帯状回(ACC)におけるNMDAR(NR1, NR2A, NR2Bサブユニット)の活性化が鍼により抑制され、異常痛信号の伝達が遮断されることが報告された 。
-
P2X7・プロキネティン経路:脊髄および脳内グリア細胞におけるP2X7受容体やプロキネティン(PK2/PKR1, PKR2)経路を介して、神経炎症応答の制御が行われ、痛覚知覚および認知過程が調節される機序が示唆された 。
-
オピオイド中枢作用:エンドルフィンやSAP(preprodynorphin)系の誘導により、脳幹・大脳皮質レベルでの鎮痛信号が増強される側面がある。
-
-
HPA軸および情動調節機構
-
CRH/ACTH/CORTの抑制:腹部経穴ST36(三里)やST37(上巨虚)へのEAおよび灸刺激により、視床下部–下垂体–副腎(HPA)軸関連ホルモンであるCRH、ACTH、コルチコステロン(CORT)の発現が抑制される。これがストレス応答の緩和を通じてVHを改善することが報告されている 。
-
情動回路への入力:鍼刺激は扁桃体–中脳水道灰白質–島皮質経路を活性化し、BDNFやNPYの発現を促進することで、うつ・不安の併存症状を改善し、全体的なVH緩和に寄与する可能性がある。
-
作用機序の総括
これらの末梢・中枢・HPA軸経路は、鍼治療が神経–免疫–内分泌連関を介して「内臓過敏症」という多層的病態を統合的に緩和する機序を裏付ける。末梢では5-HTおよびTRPV1依存的シグナル経路が主に調節され、中枢ではNMDAR・P2X7・オピオイド経路が協調的に機能し、さらにHPA軸を介したストレス応答と情動制御がこれらを増強すると考えられる 。
臨床的インプリケーションと今後の課題
-
プロトコル標準化:ST25+ST37の組み合わせや、2〜10 Hzの低周波Sparse Wave EA、温度変動を伴う生姜灸などが頻用されるが、施術頻度・強度・モダリティ(針刺 vs. 灸 vs. 電気鍼)の最適化検討が必要である 。
-
多施設二重盲検RCTの実施:動物実験の知見を臨床へ展開するため、プラセボ鍼対照を含む高品質RCTによるエビデンス向上が急務である。
-
自律神経評価の導入:鍼刺激が交感・副交感バランスを回復する可能性が示唆されているが、自律神経機能評価(心拍変動解析など)の組み込みが望まれる。
-
腸内細菌叢との相互作用:鍼灸が腸内細菌叢を改善し、免疫–神経–内分泌経路を介してVHを抑制するメカニズムの解明も、将来的な研究の方向性として期待される 。
使用経穴
本レビューでVH改善に頻用される経穴は主に以下の3穴である :
-
ST25(天枢)
-
ST36(三里)
-
ST37(上巨虚)
これらの経穴は、腸管運動調節、分泌抑制、ストレス応答制御といった多面的作用を通じ、IBSに伴う内臓過敏症の改善において中心的役割を果たしている。