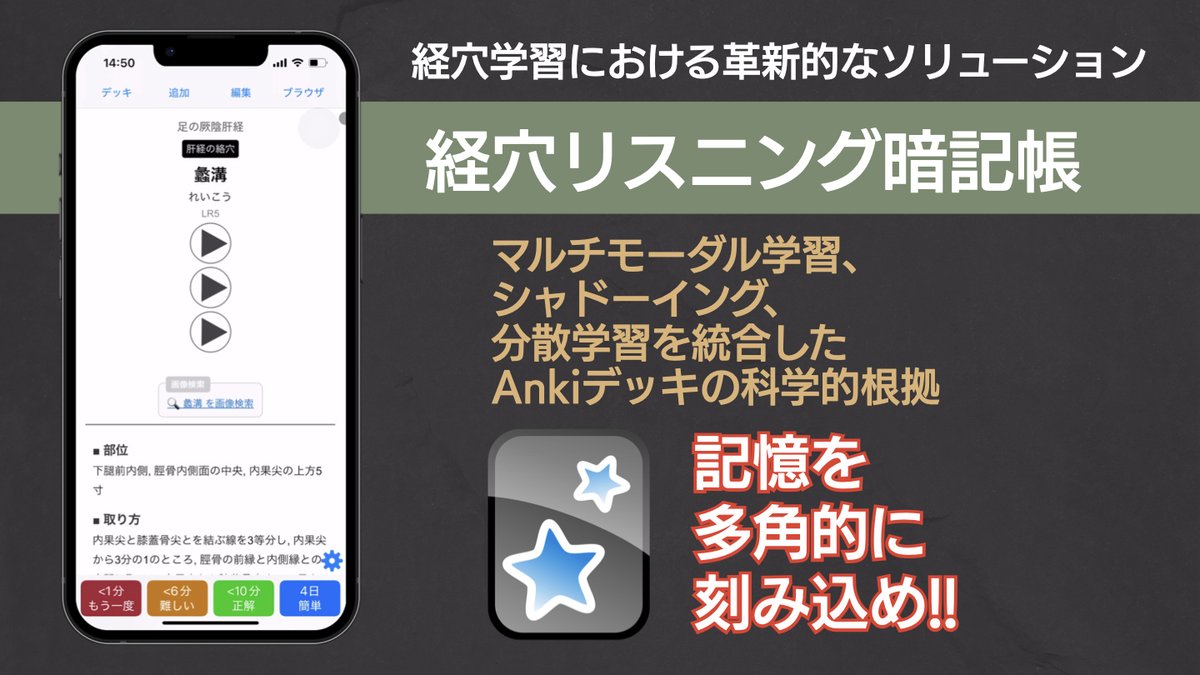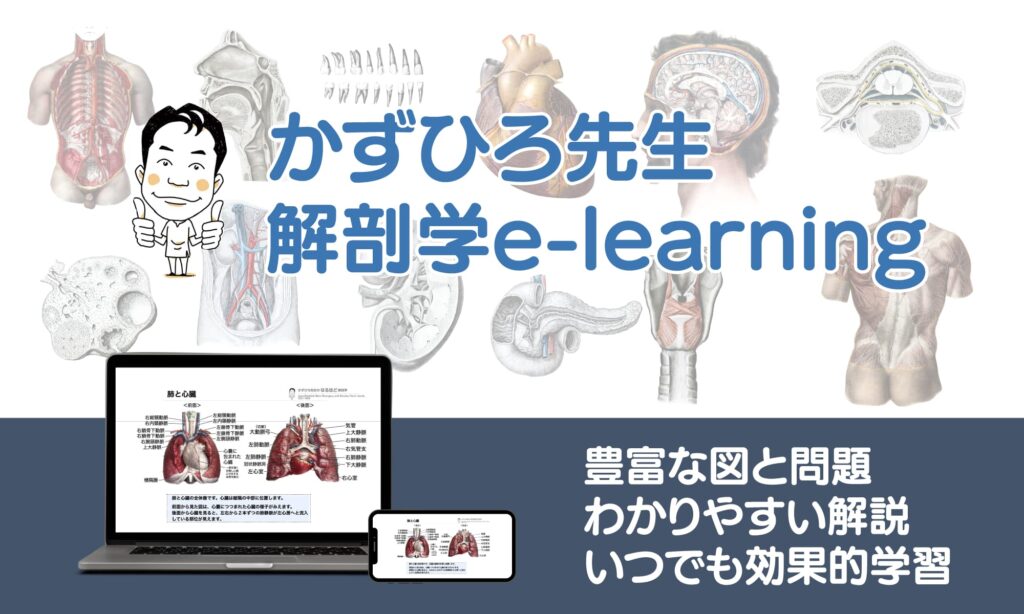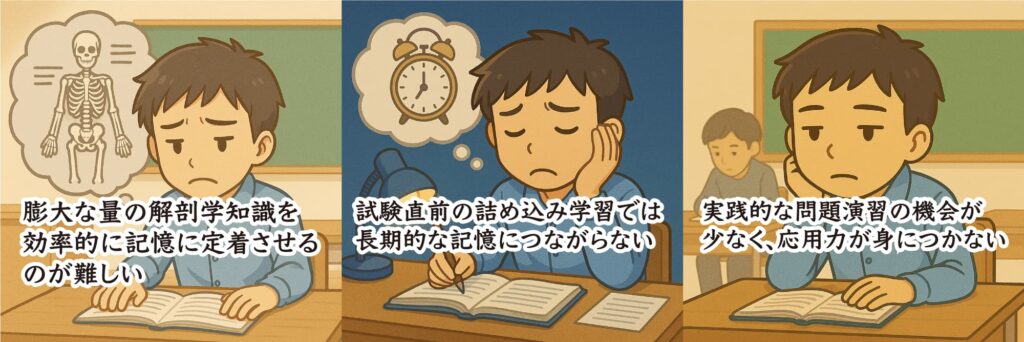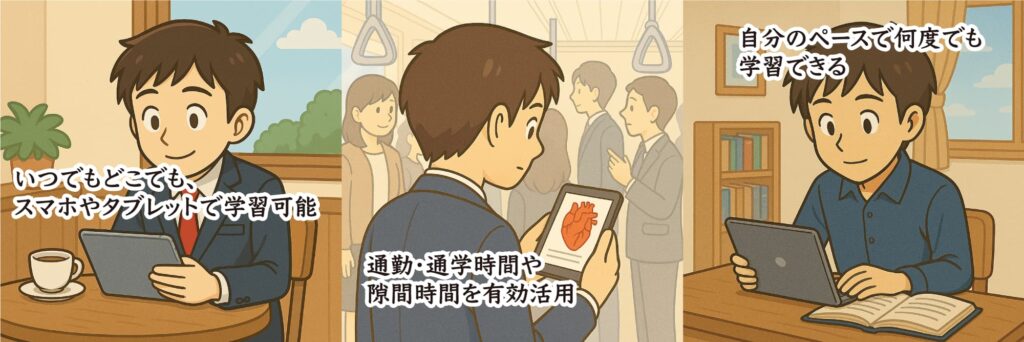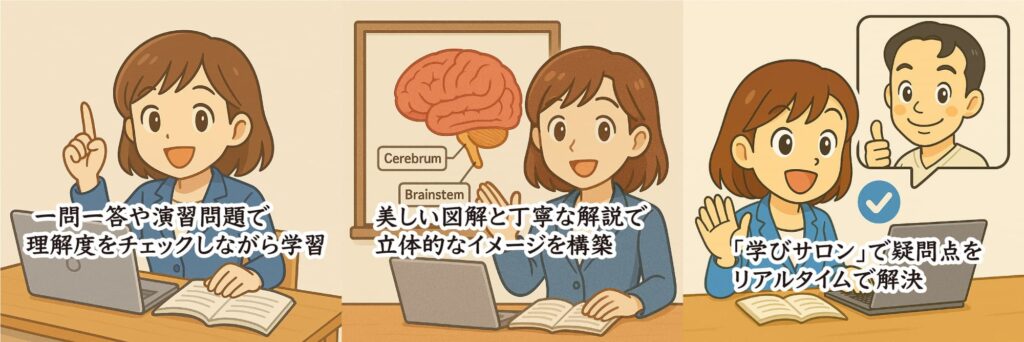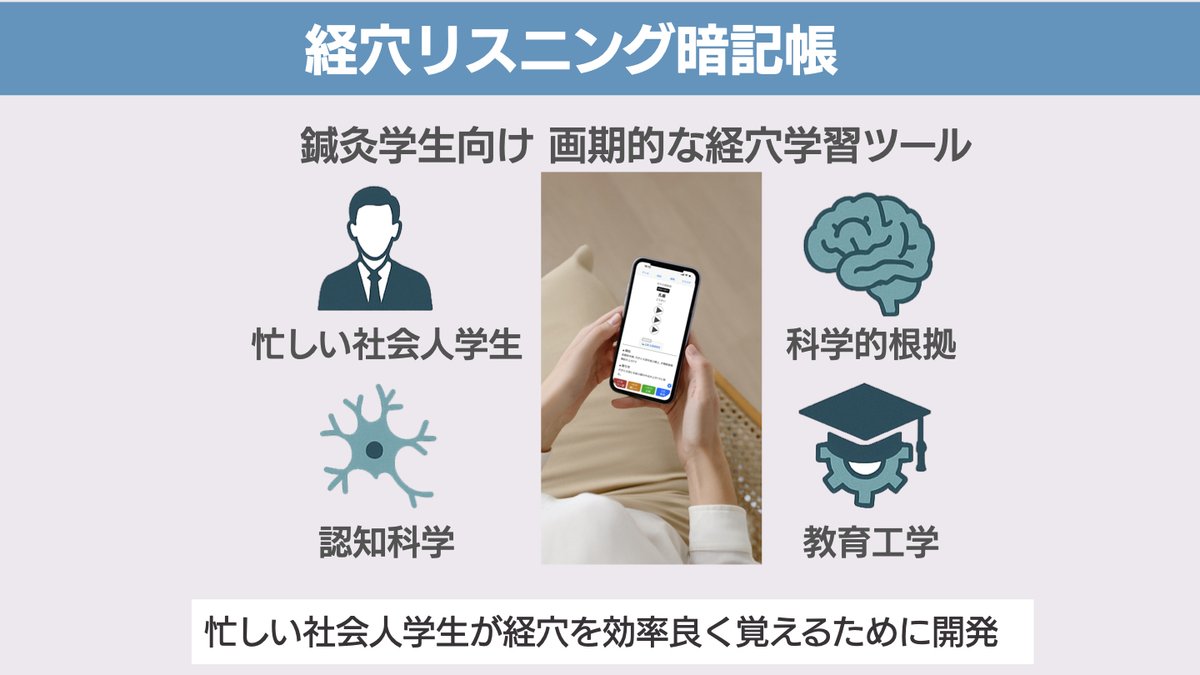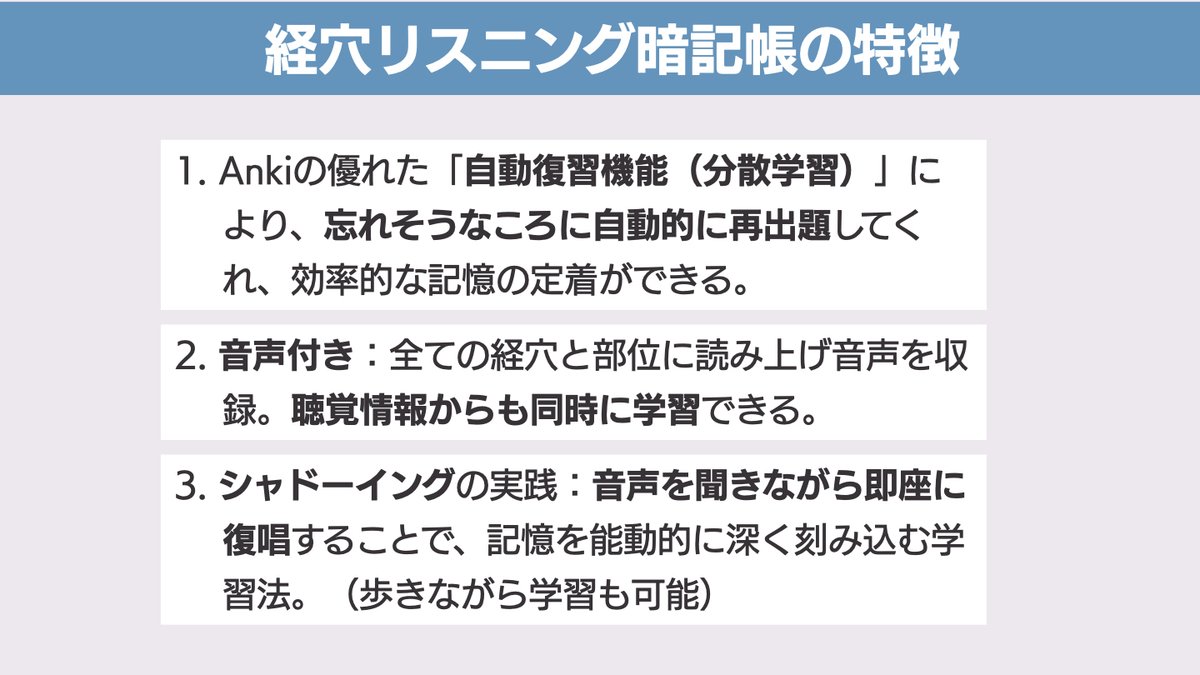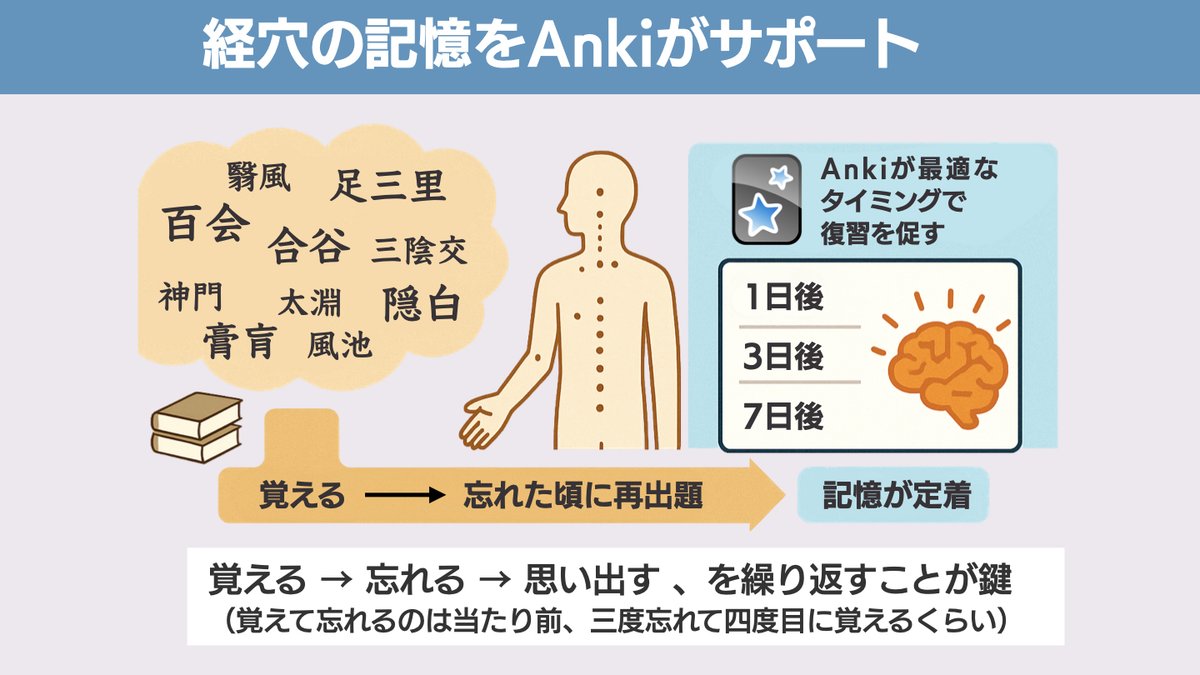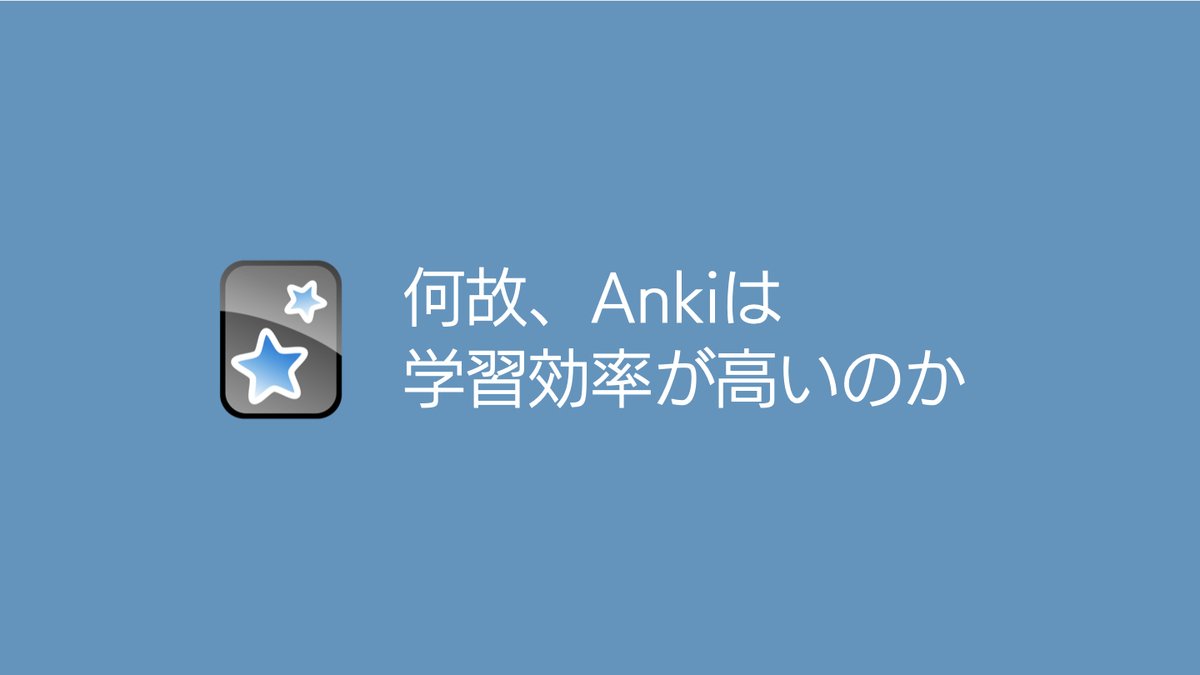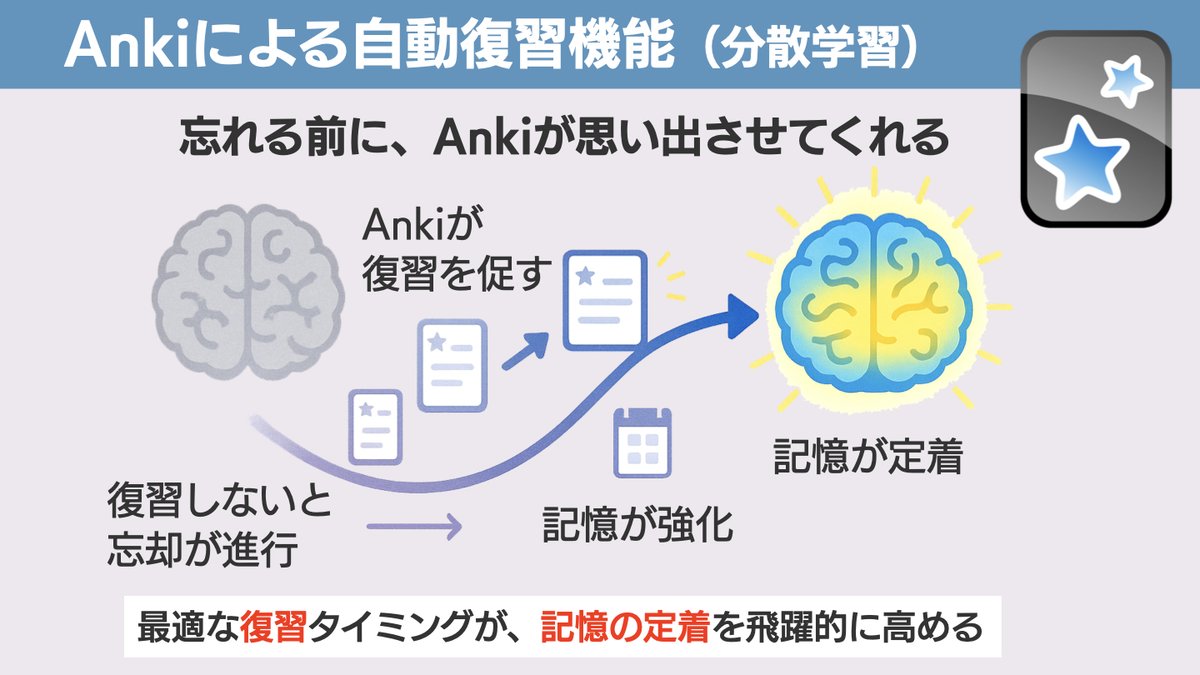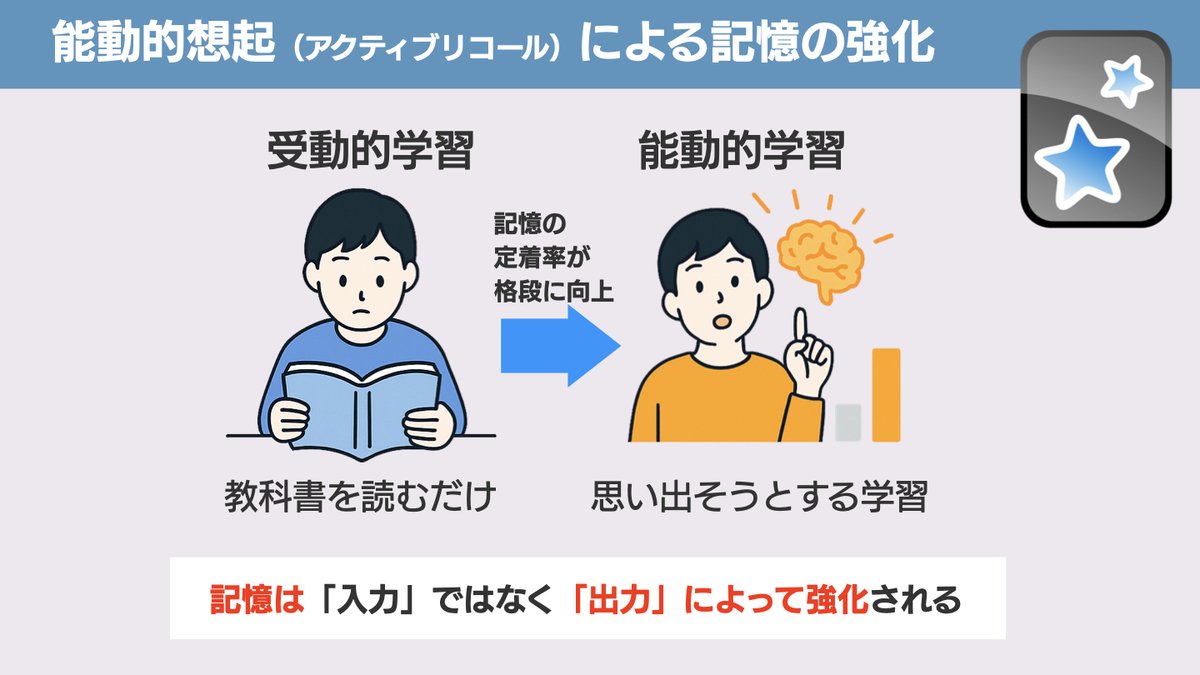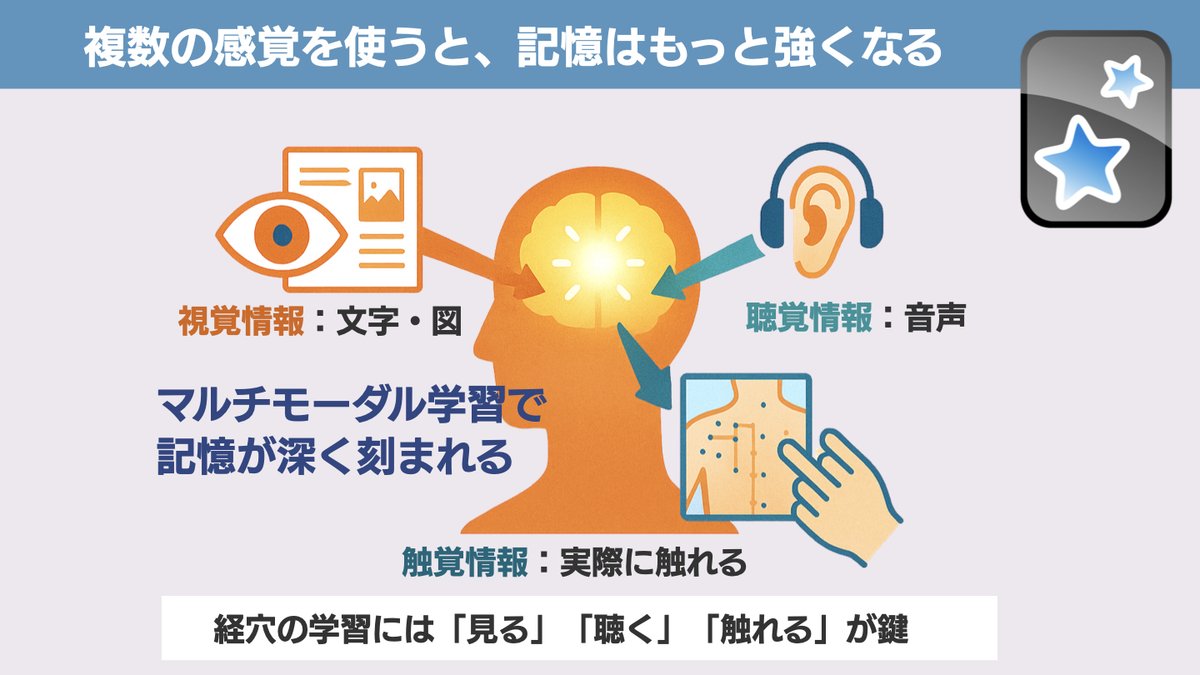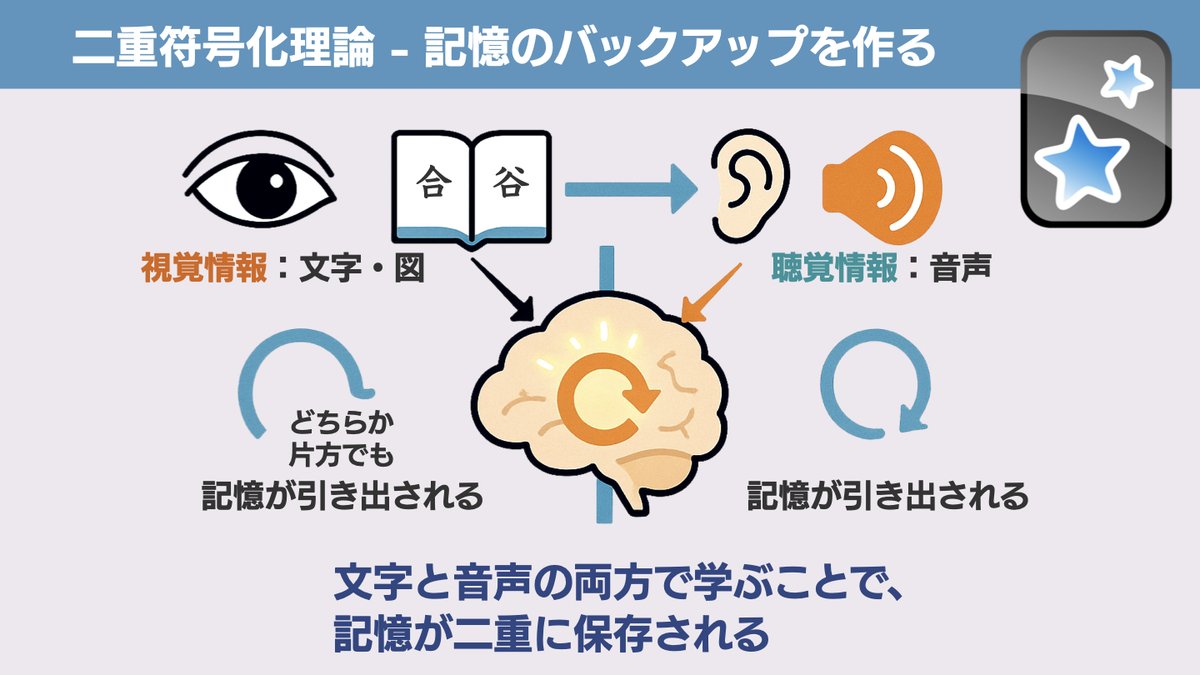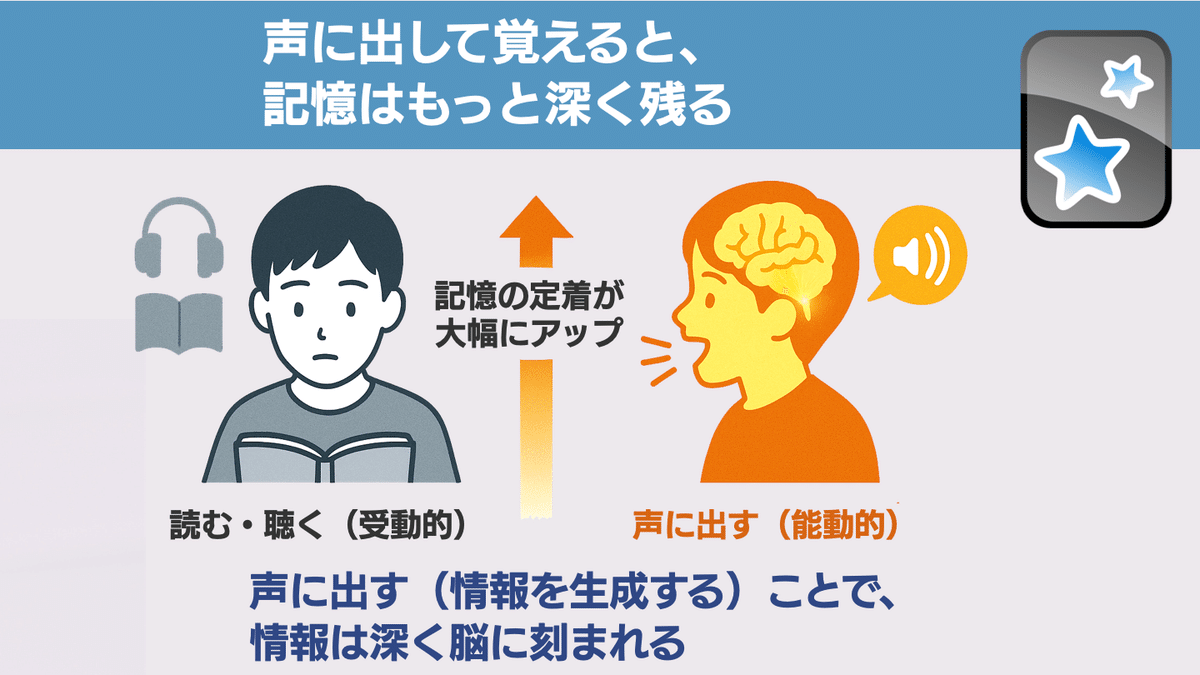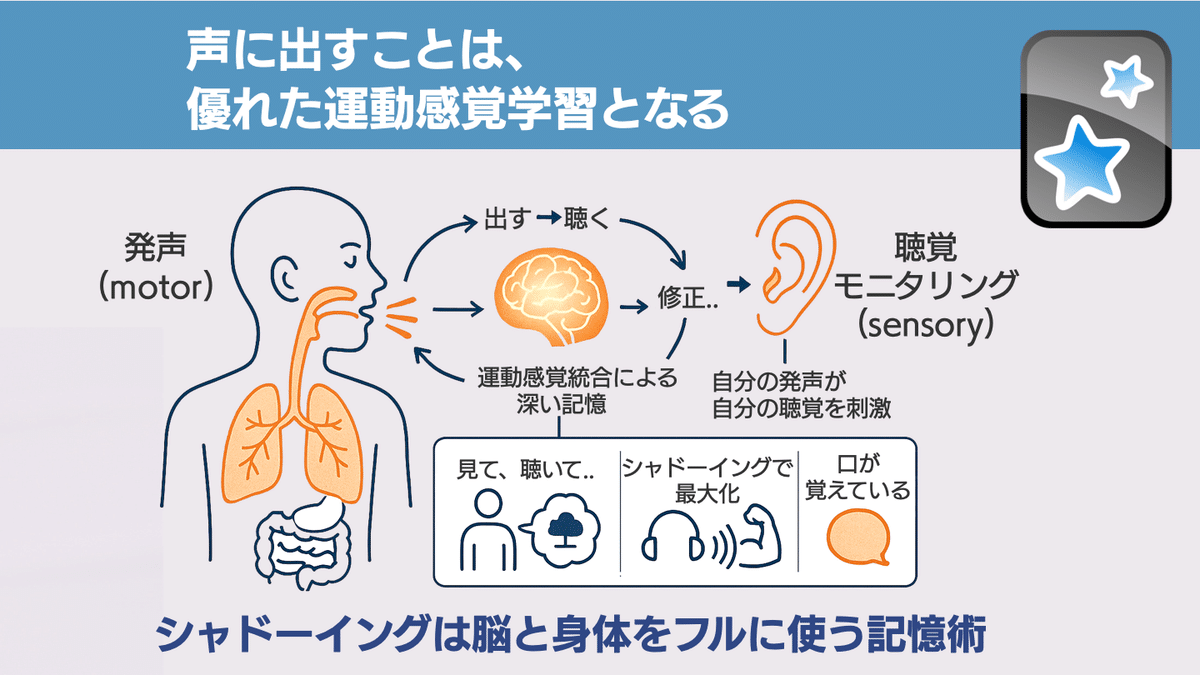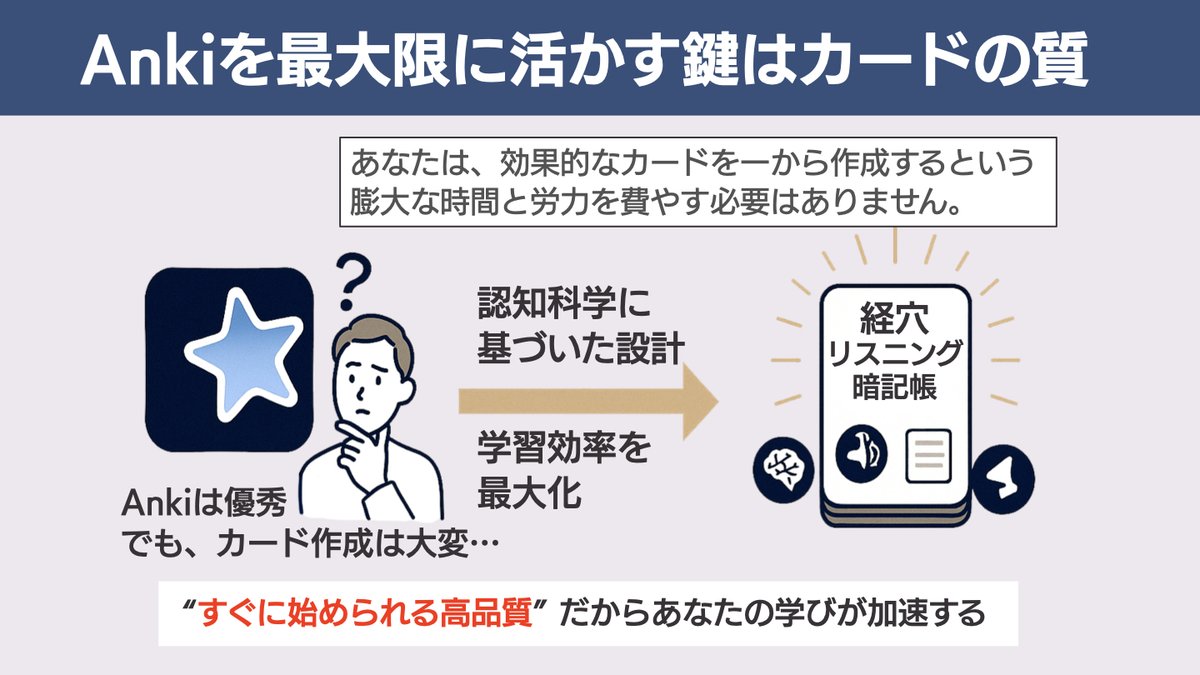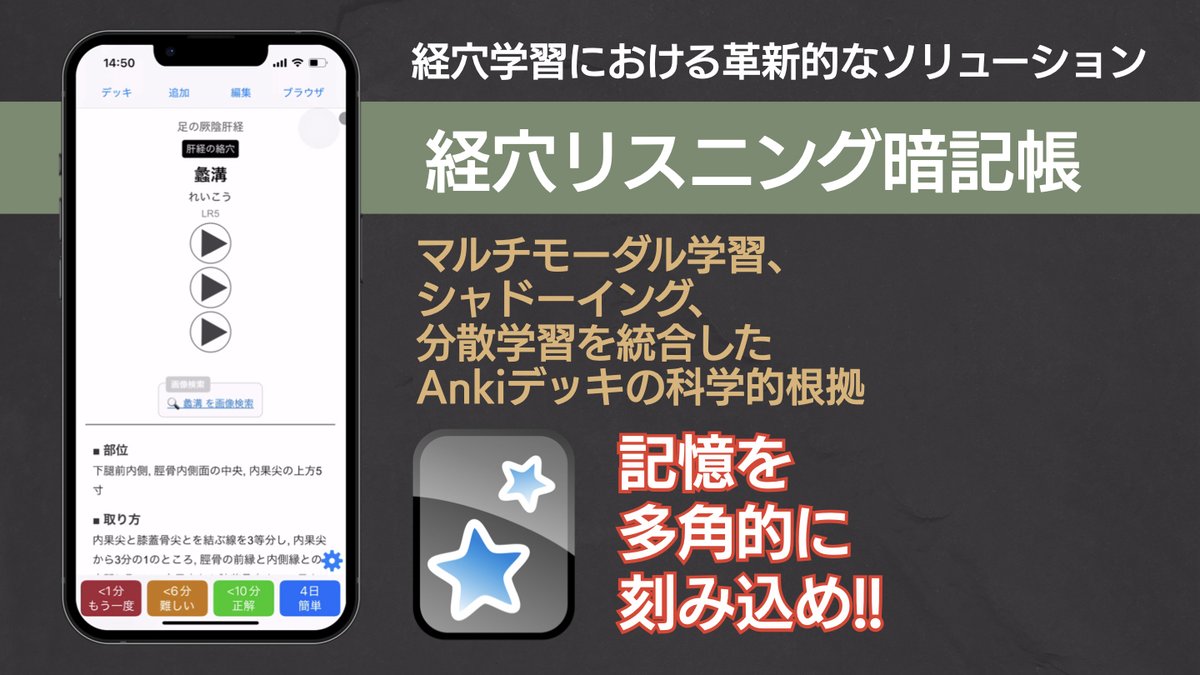引用論文
Effects of moxibustion at “Xinshu” (BL15) and “Feishu” (BL13) on myocardial transferrin receptor 1 and ferroptosis suppressor protein 1 in chronic heart failure rats
「慢性心不全ラットにおける「心兪」(BL15)および「肺俞」(BL13)への灸法が心筋トランスフェリン受容体1およびフェロトーシス抑制タンパク質1に与える影響」
1. 研究背景
慢性心不全(CHF)は、心筋のリモデリングと線維化が進行し、心収縮能の低下を伴う疾患である。近年、心筋細胞の鉄代謝異常とフェロトーシス(鉄依存性細胞死)がCHFの進展に深く関与することが示唆されている。特に、心筋トランスフェリン受容体1(TfR1)の発現亢進や、フェロトーシス抑制タンパク質1(FSP1)の発現低下は、鉄過負荷と細胞死を促進し、線維化を悪化させるメカニズムと考えられている。一方、鍼灸の灸法(moxibustion)は古典的に循環器機能改善や線維化抑制を目的として用いられてきたが、その分子機序は未だ十分に解明されていない。本研究は、慢性心不全ラットモデルにおいて、BL 15(心兪)およびBL 13(肺俞)への灸法が心筋のTfR1およびFSP1発現に及ぼす影響を評価し、灸法による鉄代謝・フェロトーシス制御機序を解析することを目的とした 。
2. 研究方法
被験者:Sprague–Dawleyラット50匹を用い、正常群(n=10)とモデリング群(n=40)に分けた。
CHFモデル作製:モデリング群では左前下行枝の結紮により心筋梗塞性心不全モデルを作製し、成功後に以下の4群に無作為割付した。
-
モデル群(n=9)
-
灸法群(n=8)
-
ラパマイシン(RAPA)群(n=9)
-
灸法+RAPA群(n=9)
介入:
-
灸法群では、両側BL 13およびBL 15に対し、各部位15分間、1日1回、4週間連続で艾条灸(mild moxibustion)を施行。
-
RAPA群では1 mg/kgのラパマイシンを腹腔内投与(1日1回・4週間)。
-
灸法+RAPA群では灸法後に同量のラパマイシン投与 。
評価項目:
-
心機能指標:駆出率(EF)および心室短縮率(FS)
-
心筋組織学:HE染色・Masson染色による線維化評価
-
鉄含有量:心筋組織の総鉄量(比色法)
-
分子発現:TfR1、FSP1、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)、CollagenⅠのタンパク質およびmRNA発現量(Western blot・qPCR) 。
3. 使用経穴
-
BL 15(心兪/Xinshu):第5胸椎棘突起下縁外方1.5寸に位置し、心機能調整・精神安定に用いられる背兪穴。
-
BL 13(肺俞/Feishu):第3胸椎棘突起下縁外方1.5寸に位置し、呼吸器機能・免疫調整に用いられる背兪穴。
4. 主な結果
-
心機能改善
-
灸法群はモデル群に比べてEFおよびFSが有意に上昇し(P<0.01)、心収縮能の改善を示した。
-
-
線維化抑制
-
Masson染色で灸法群はコラーゲン沈着量が大幅に低下し(P<0.01)、心筋線維化の抑制が確認された。
-
-
鉄代謝調整
-
モデル群では心筋鉄含有量およびTfR1発現が上昇し、FSP1発現が低下していたが、灸法群ではこれらが正常群に近い水準まで改善した(P<0.01)。
-
-
分子マーカー
-
灸法群はTfR1タンパク質・mRNAとANP、CollagenⅠの発現が有意に低下し、FSP1発現が有意に上昇した(P<0.01)。
-
-
併用効果
-
灸法+RAPA群と比べても、単独の灸法群で最も顕著な改善が見られ、灸法単独の効果がラパマイシン併用を凌駕する傾向が示唆された 。
-
5. 考察
本研究により、BL 15およびBL 13への灸法がCHFラットにおける心筋線維化を緩和し、心機能を改善することが示された。特に、鉄代謝関連分子の制御を介したフェロトーシス抑制が主要作用機序と考えられる。すなわち、灸法によりTfR1の過剰発現を抑え、鉄過負荷を軽減すると同時に、FSP1を賦活化してフェロトーシス抑制機構を強化することで、心筋細胞死と線維化進展を抑制するものと推察される 。
臨床的には、CHF患者に対する灸法の補助療法として、従来の薬物治療と併用することで心機能維持・QOL向上が期待できる。また、BL 15・BL 13はベッドサイドでも簡便に施術可能な部位であり、安全性・経済性に優れる点も大きな利点である。
6. 限界と今後の展開
-
動物モデルの限界:ラットモデルにおける結果であり、ヒト臨床への直接的な適用にはさらなる検証が必要。
-
手技の標準化:灸法の深度・温度・時間などパラメータ最適化が未完。
-
長期効果:4週間介入後の短期効果評価にとどまり、持続的改善や再発予防については未検討。
-
分子機序の詳細:上流・下流シグナル伝達経路や他のフェロトーシス関連因子との相互作用解析が今後の課題。
本論文は、伝統的な灸法の作用機序を現代分子生物学的視点で解明した先駆的研究として評価される。