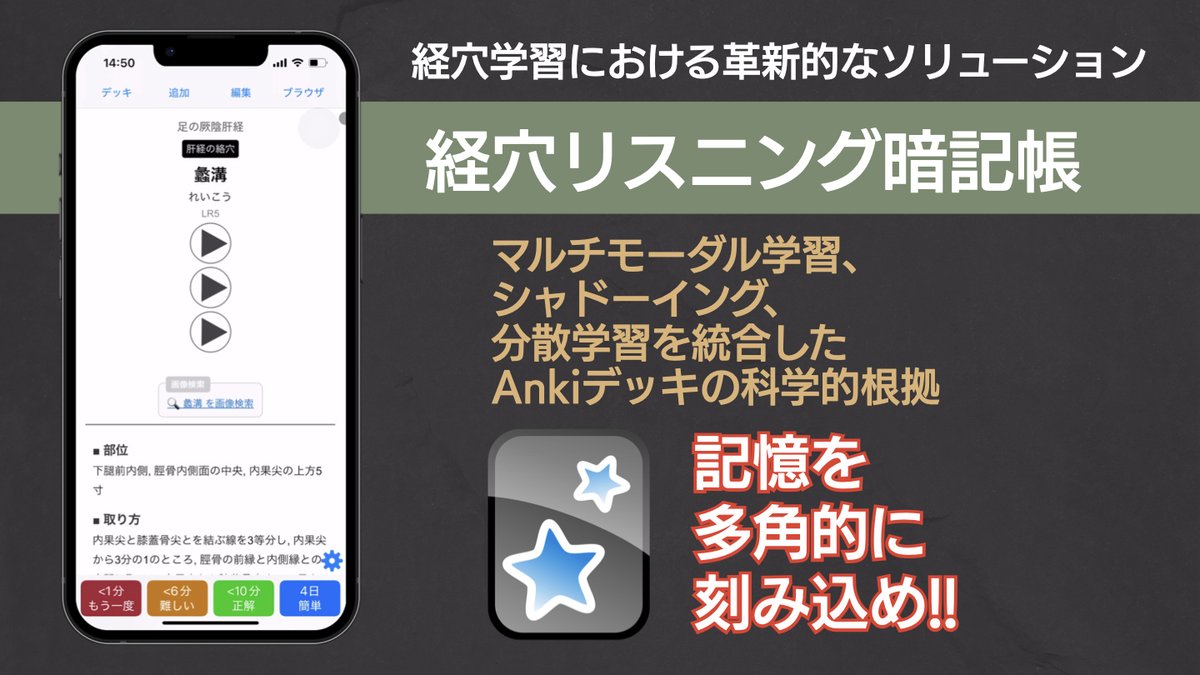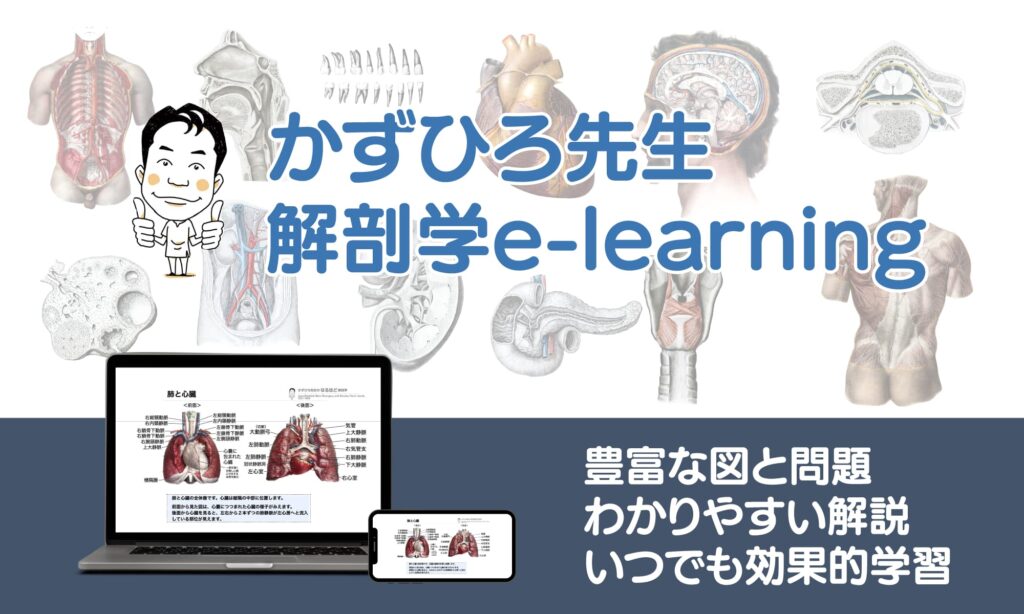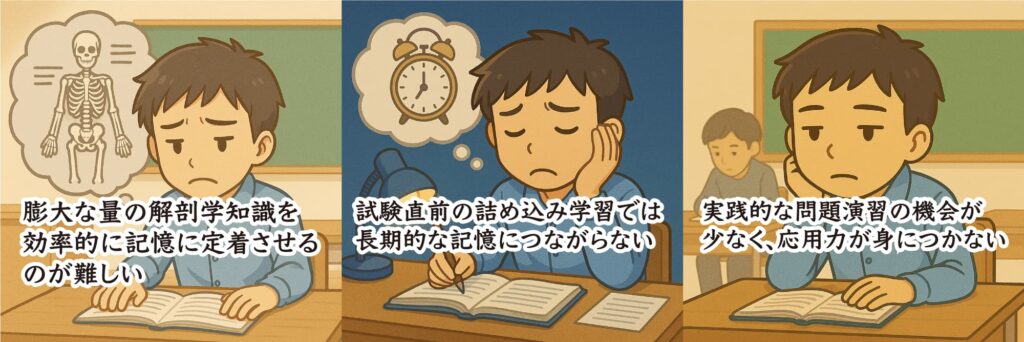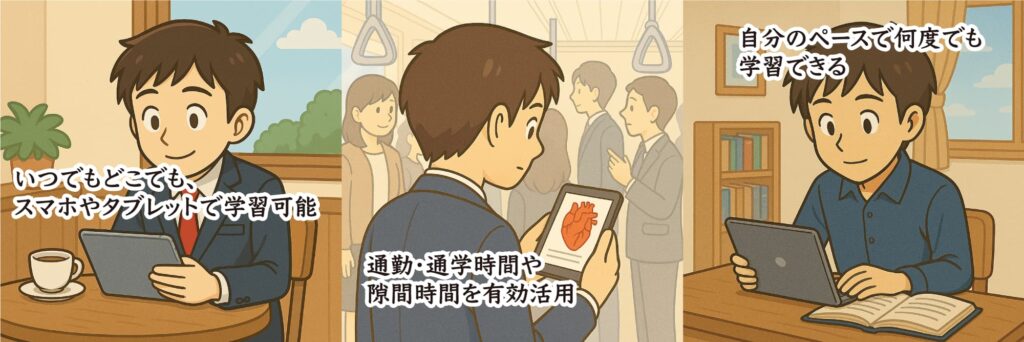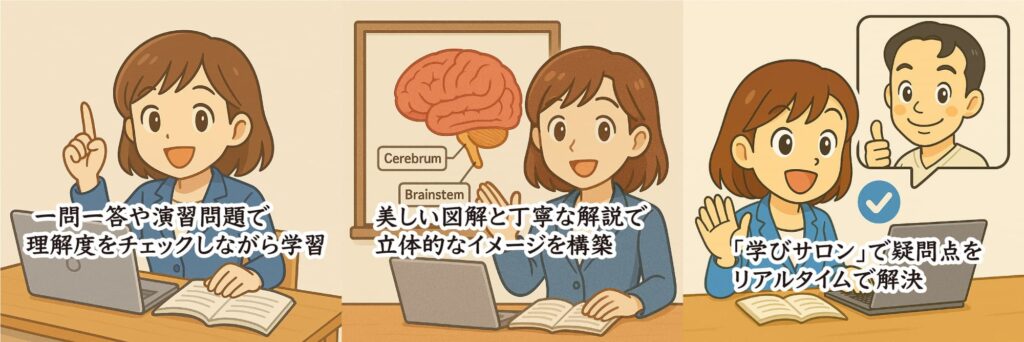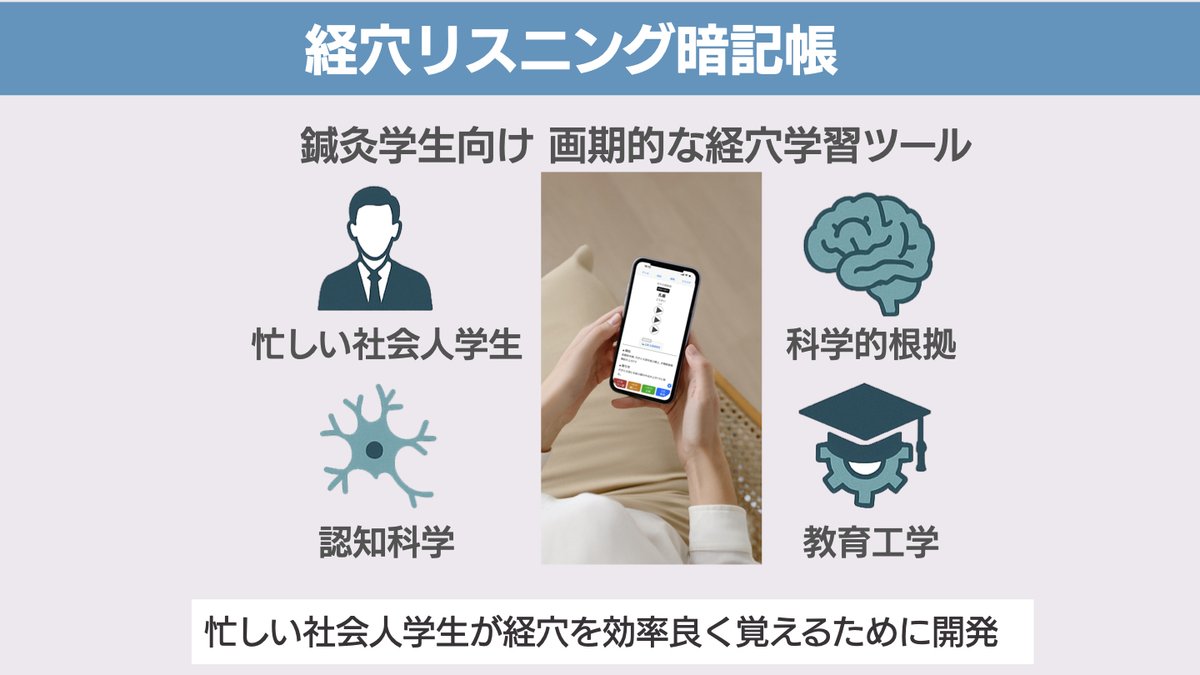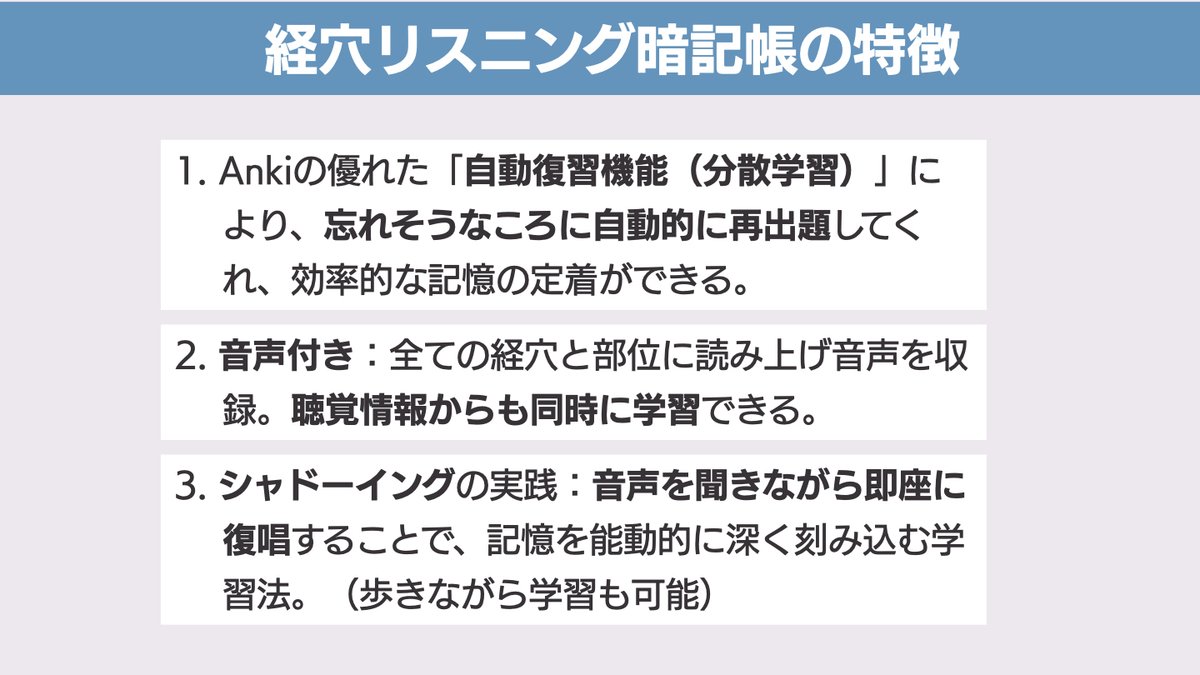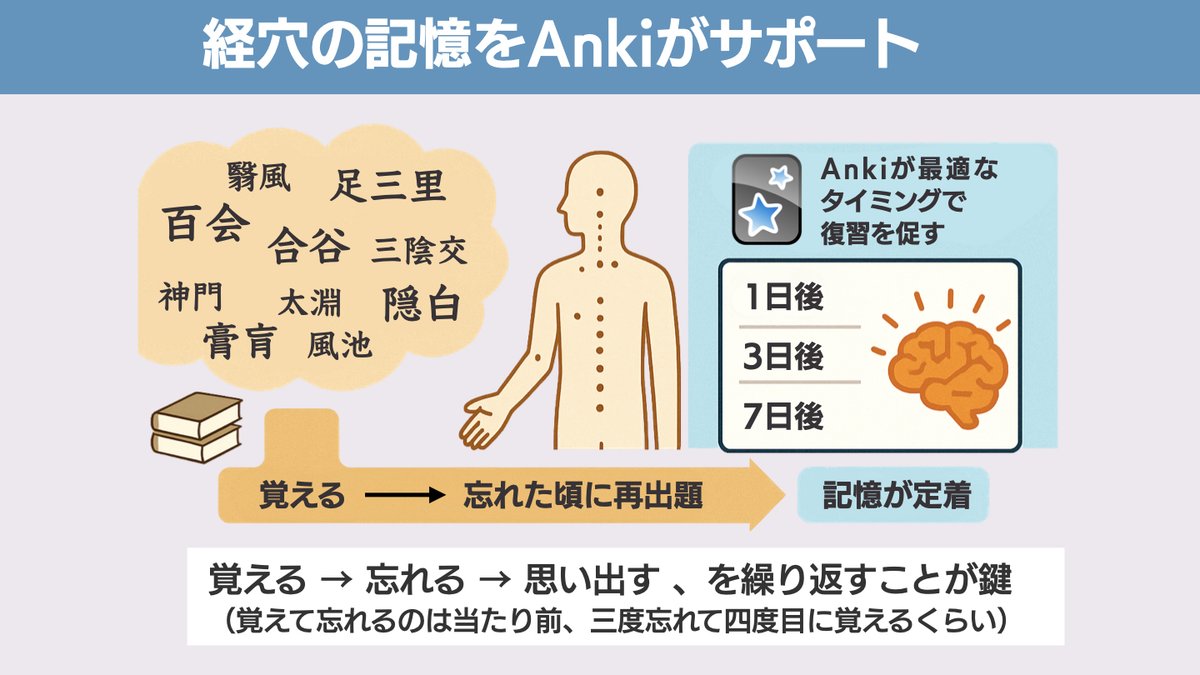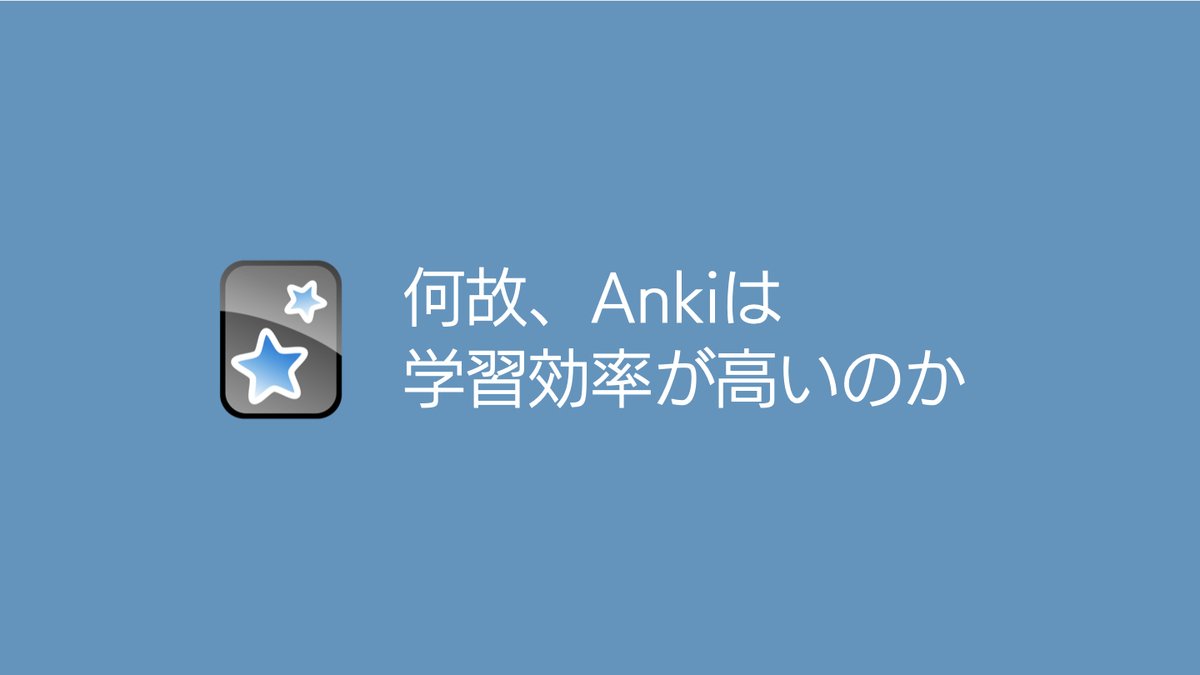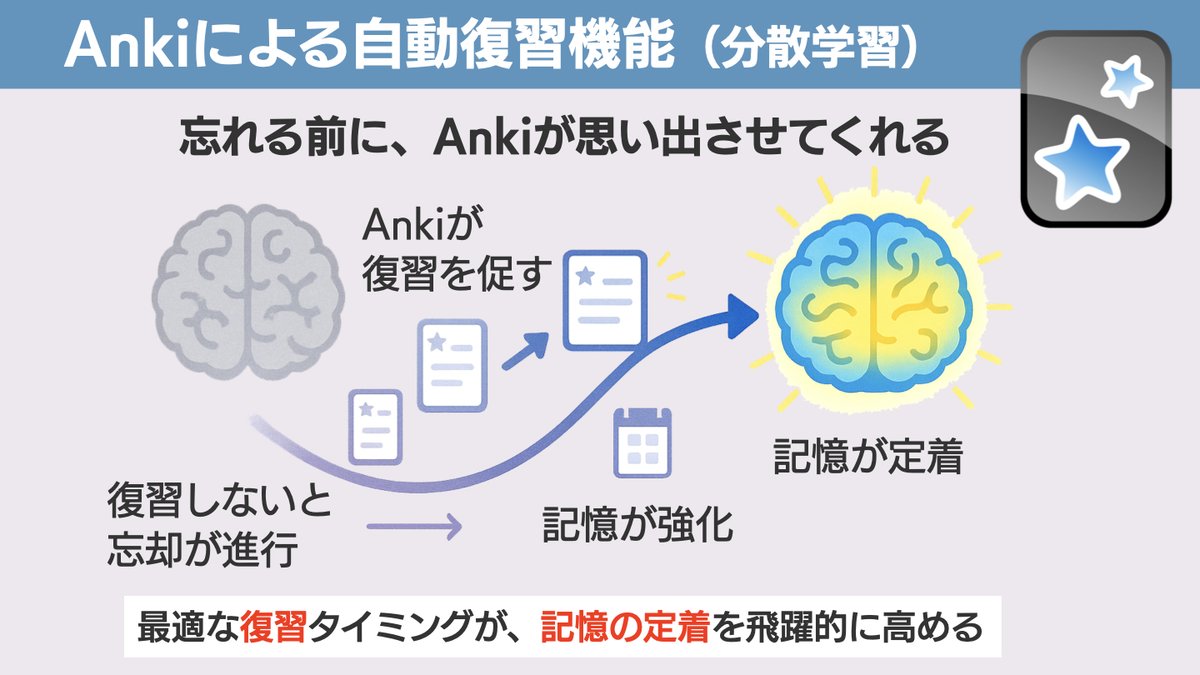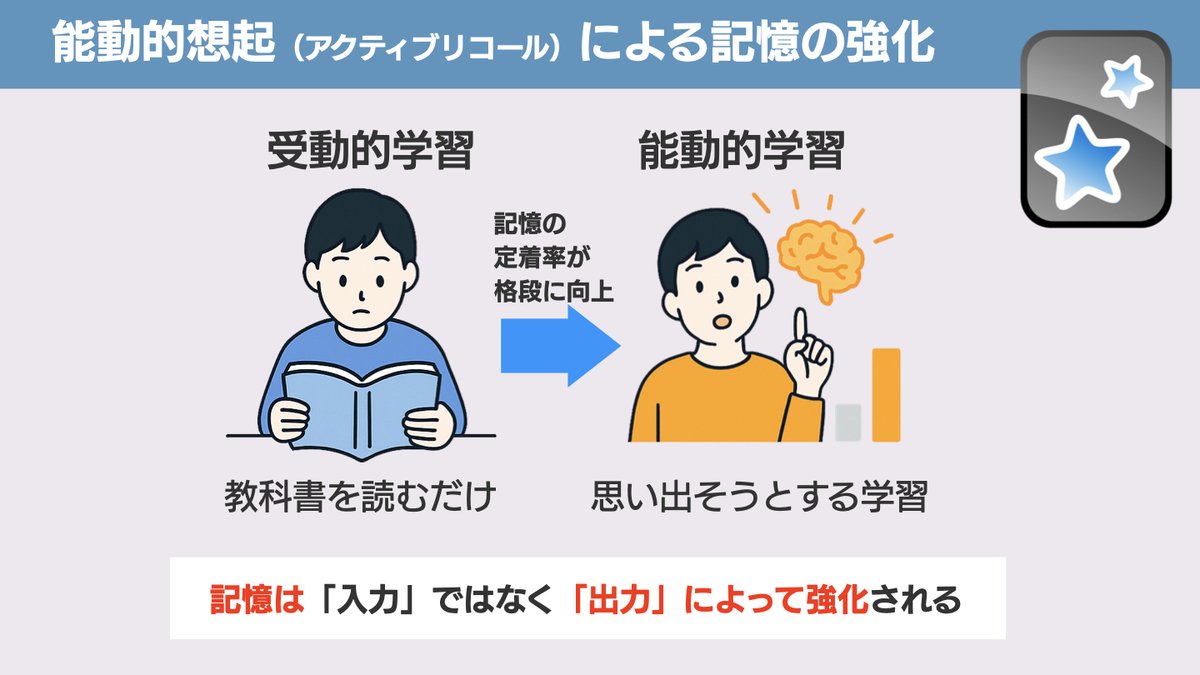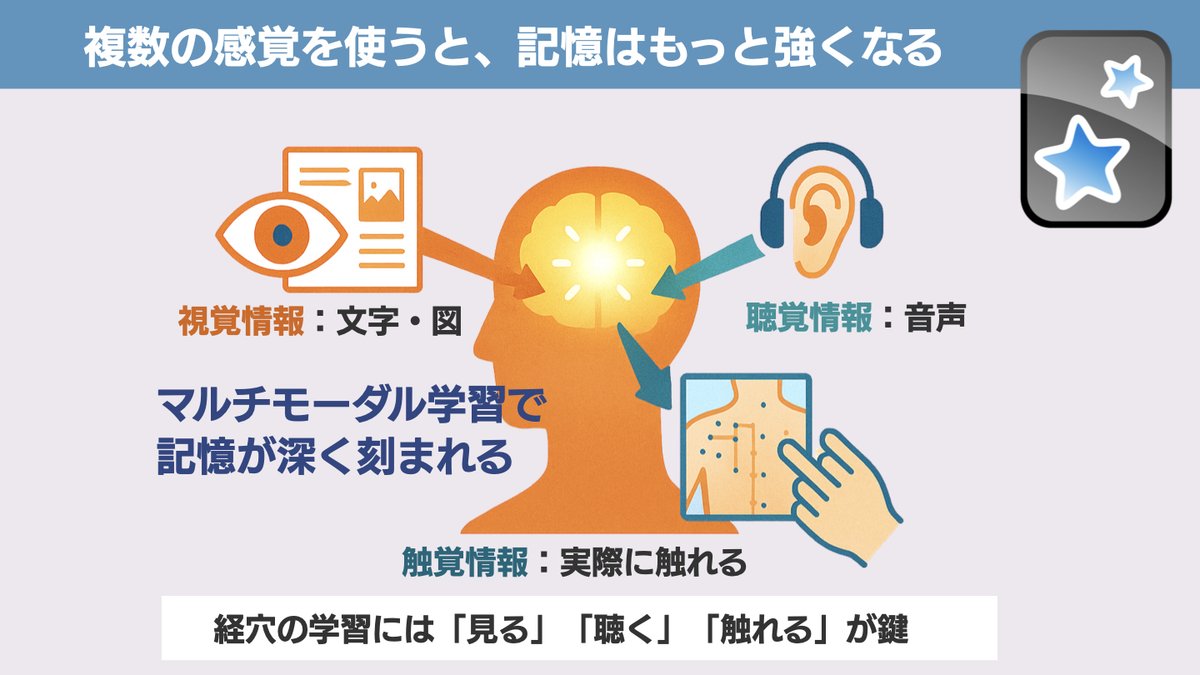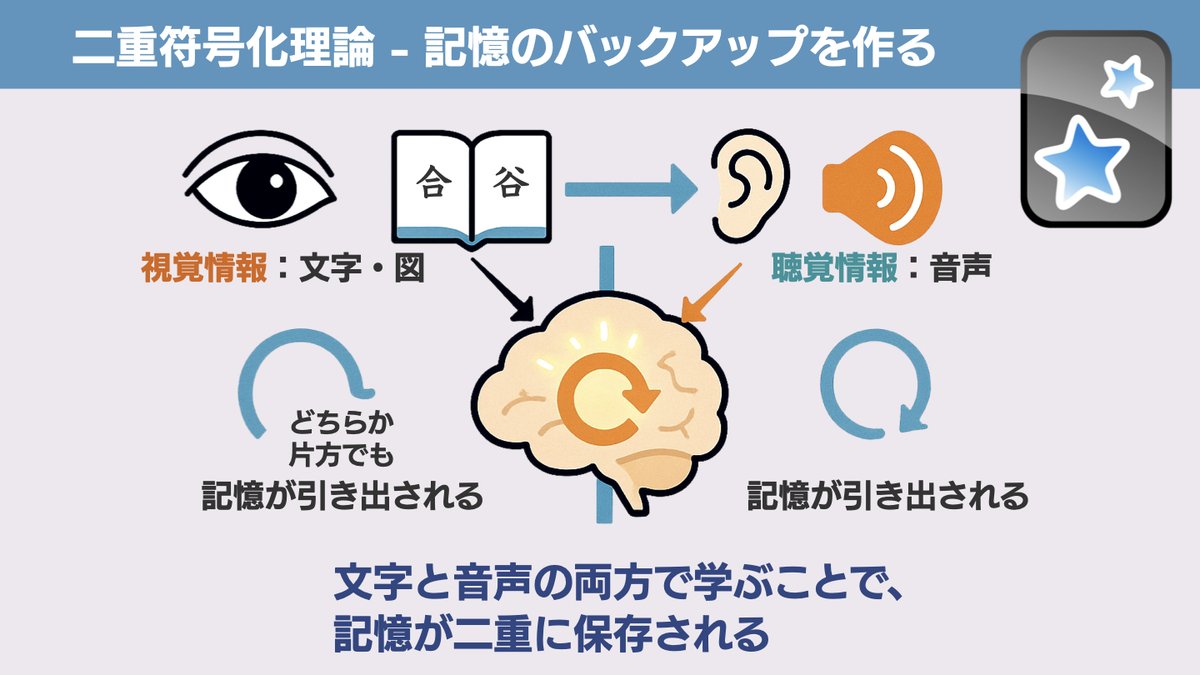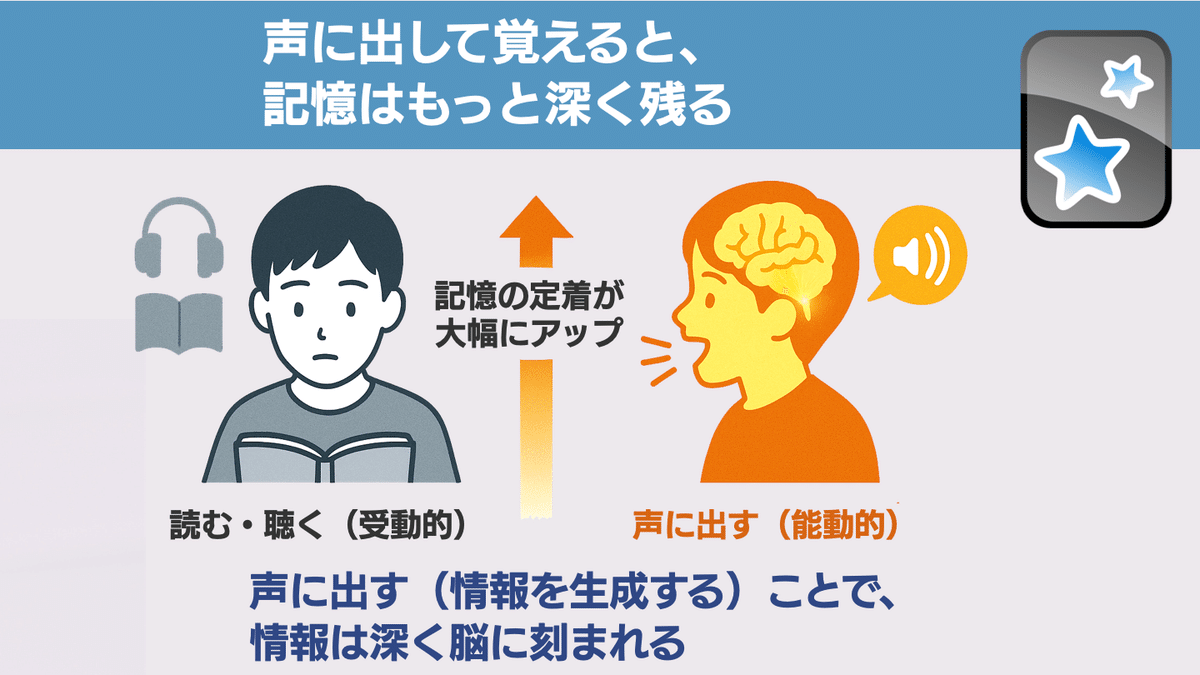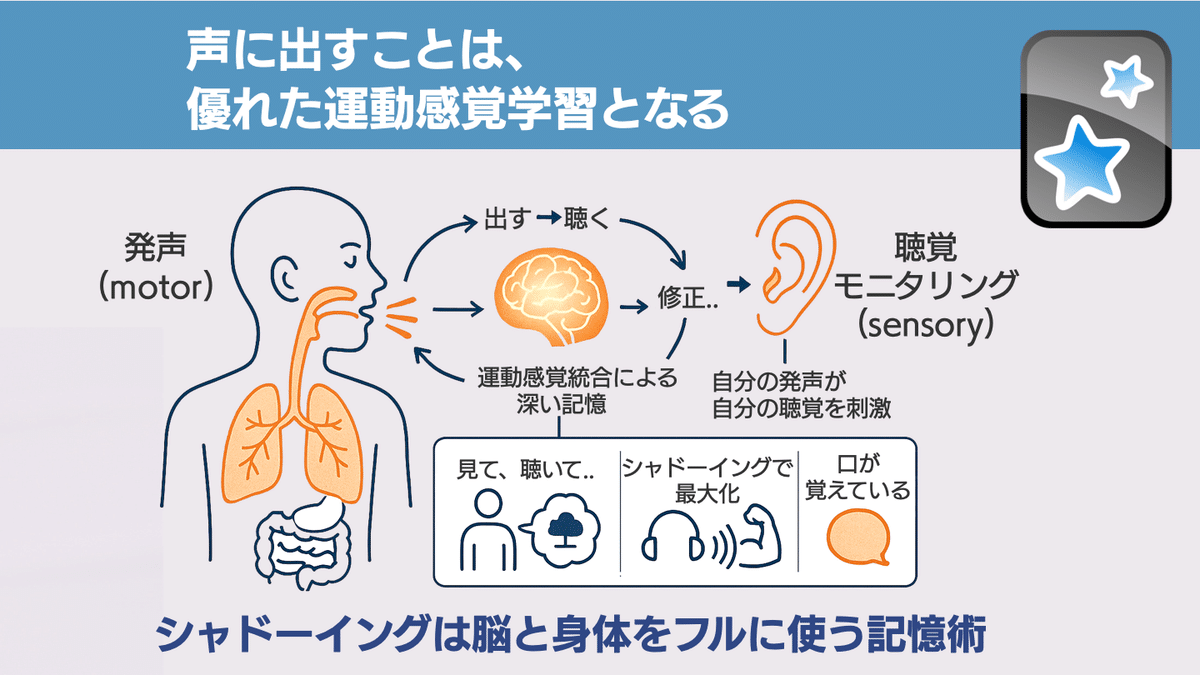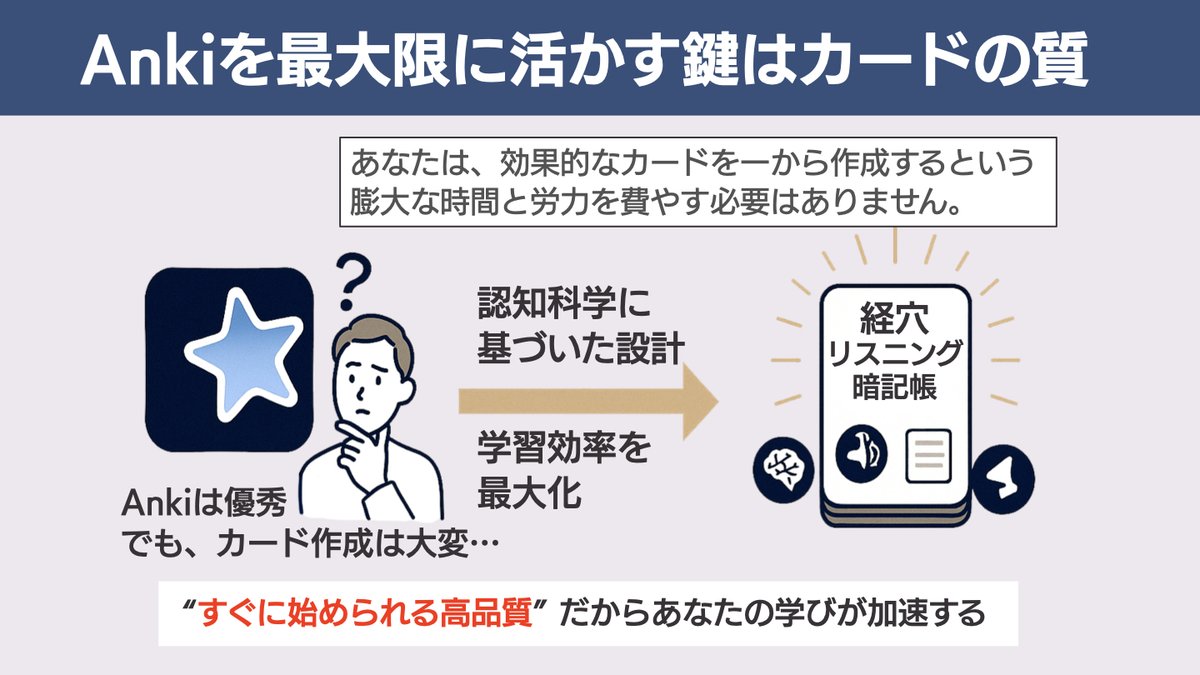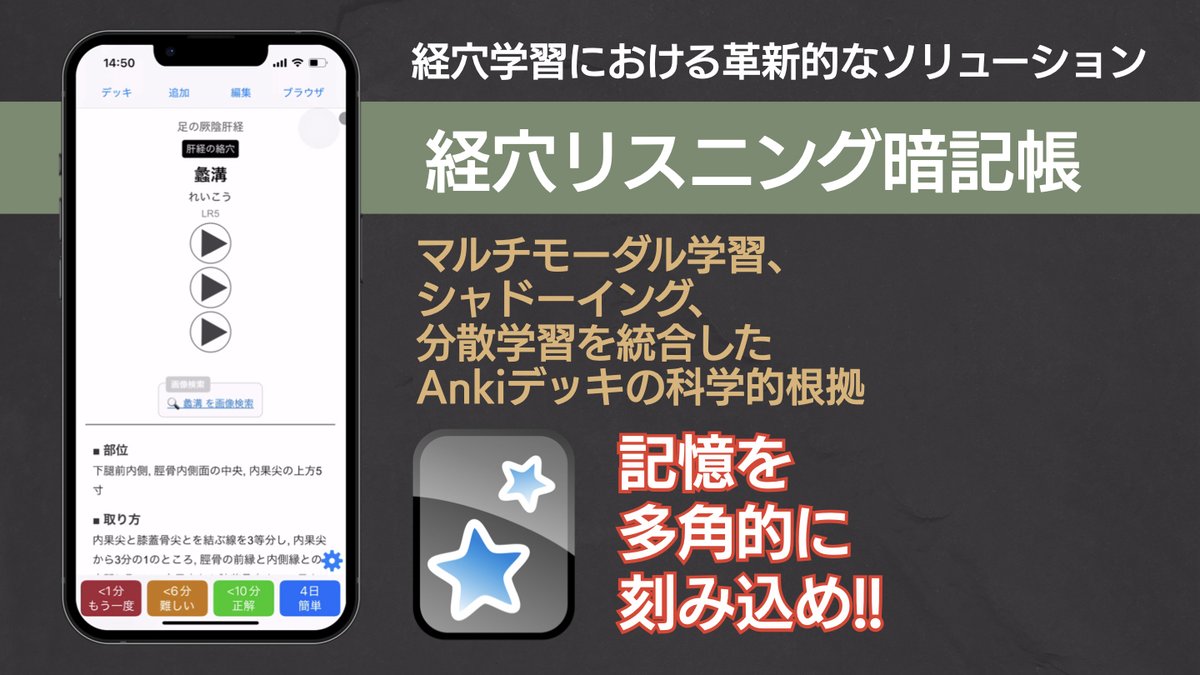引用論文
The Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Sciatica: A Systematic Review and Meta-Analysis
「坐骨神経痛治療における鍼治療の有効性:系統的レビューおよびメタアナリシス」
研究背景
坐骨神経痛(sciatica)は腰部または臀部から下肢に放散する痛みやしびれを主症状とし、人口統計学的調査では有病率が1.2%から43%と大きく変動するものの、成人の10~40%が一度は経験すると報告されている一般的な神経障害性疼痛です。その慢性化は生活の質(QoL)を著しく低下させ、社会的・経済的な生産性の損失を招くことが知られています 。従来、鎮痛薬や理学療法、神経ブロックなどが第一選択とされるものの、治療効果が不十分であったり、副作用による継続困難例が少なくないため、代替・補完療法としての鍼治療への関心が高まっています。
東洋医学(TCM)の視点では、坐骨神経痛は足の少陽胆経(GB)および足の太陽膀胱経(BL)に属する経絡の病証とみなされ、特に陽陵泉(GB34)や環跳(GB30)が主要な治療点として古来より用いられてきました 。鍼刺激は気血の流れを調整し、経絡の閉塞を除いて痛みを緩和するとされ、近年の臨床研究でもその有効性が示唆されている一方で、既存の研究の多くは方法論的品質に課題が残り、系統的な評価や定量的メタアナリシスは限られていました。
目的
本研究は、2015年4月までに発表された英中両言語のランダム化あるいは準ランダム化試験を対象に、鍼治療と西洋薬治療(NSAIDs、ステロイド、ビタミン剤など)を比較した臨床試験を網羅的にレビューし、以下の観点から鍼治療の有効性と安全性を評価することを目的としました:
-
臨床症状改善率(total/partial improvement)の比較
-
痛み強度(VAS)および痛み閾値の変化
-
副作用および離脱例の集計
方法
中国語データベース(CNKI、CBM、Wanfang Data)3件、英語データベース(Cochrane Library、PubMed、Web of Science、Science Direct、FMRS)5件の計8データベースを2015年4月30日まで検索し、“acupuncture”や“electroacupuncture”、“sciatica”などの英中両言語のキーワードを組み合わせて文献検索を実施しました 。ランダム化または準ランダム化臨床試験、坐骨神経痛患者、鍼治療(手技鍼、電気鍼、温鍼、レーザー鍼いずれも可)対西洋薬治療比較を含む研究を選定し、タイトル・抄録の重複排除後、156報の全文を精査し、最終的に12報(計1,842名)がメタアナリシスに組み込まれました 。
データ抽出は2名の査読者が独立して行い、STRICTAガイドラインに基づき鍼治療プロトコール(使用経穴、刺入深度、得気、刺激法、保持時間、施術頻度)を詳細に記録しました 。品質評価はCochrane Handbook(V5.1.0)による7つのバイアスドメインで実施し、RevMan 5.3を用いてリスク比(RR)ならびに平均差(MD)を固定効果モデルまたはランダム効果モデルで統合しました 。
結果
12報のうち、9報(780名対771名)で有効性(症状改善率)、3報(121名対120名)で痛み強度(VAS)、3報(160名対150名)で痛み閾値が評価されました。
-
有効性:鍼治療群は西洋薬群に対し改善率が有意に優れ、RR=1.21(95%CI: 1.16–1.25、P<0.00001)を示しました(I²=36%, 固定効果モデル) 。
-
痛み強度:VASではMD=−1.25(95%CI: −1.63~−0.86、P<0.00001)と鍼治療が有意に痛みを軽減し(I²=41%, 固定効果モデル) 。
-
痛み閾値:痛み閾値はMD=1.08(95%CI: 0.98–1.17、P<0.00001)と鍼治療群が優れていました(I²=44%, 固定効果モデル) 。
-
副作用:12報中3報で軽度の皮下出血などが報告され、いずれも数日で改善。重大な有害事象は認められませんでした 。
サブグループ解析(薬剤種類別、投与経路別)および逐次除外による感度解析ともに結果は一貫して安定しており、出版バイアス解析では若干の非対称性が示唆されましたが、大きな影響は認められませんでした 。
考察
本メタアナリシスにより、鍼治療は西洋薬治療と比較して有効性・鎮痛効果・痛み閾値改善において臨床的に意義ある効果を示すことが明らかになりました。TCMの観点では、鍼刺激により深部組織の高閾値小径神経が活性化され、内因性オピオイド(エンドルフィン)やアデノシンの分泌が促進されることで速効性の鎮痛が得られると考えられています 。
一方、多くの試験でランダム化手法や盲検化が不十分であり、用量反応関係や経穴選択の統一性欠如、フォローアップ期間の短さなど方法論的・臨床的多様性が存在しました。そのため、結果解釈には慎重を要し、今後はSTRICA遵守、二重盲検設計、適切なサンプルサイズ算出、長期フォローアップを含む高品質RCTの実施が強く求められます 。
結論
坐骨神経痛患者に対する鍼治療は、西洋薬治療に対し症状改善率、痛み強度および痛み閾値で優れた効果を示し、安全性も良好であった。しかしながら、既存試験の質的限界から確定的結論には至らず、より厳密に設計された高品質試験による検証が必要である。
使用経穴
-
BL23(腎兪)
-
BL25(大腸兪)
-
BL27(小腸兪)
-
BL32(次髎)
-
BL36(承扶)
-
BL37(陰門)
-
BL40(委中)
-
BL53(胞肓)
-
BL54(秩辺)
-
GB29(居髎)
-
GB30(環跳)
-
GB34(陽陵泉)
-
GB39(懸鐘)
-
GB40(丘墟)
-
BL57(承山)
-
ST40(豊隆)
-
EX-B2(俞兪点/Jiaji穴)
-
Ashi(阿是穴)
-
BL60(崑崙)
-
SP9(陰陵泉)
-
SP6(三陰交)
-
ST36(足三里)
-
BL20(脾兪)
-
BL17(膈兪)
-
GV3(腰陽関)
-
GV16(風府)
-
LR3(太衝)