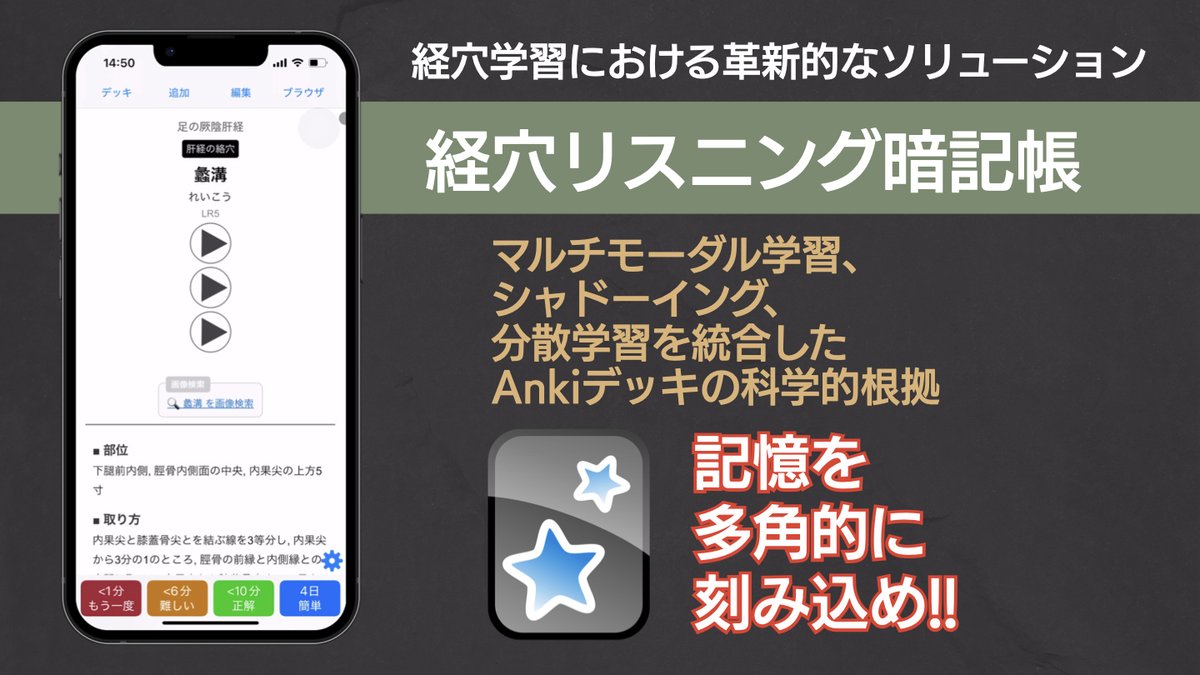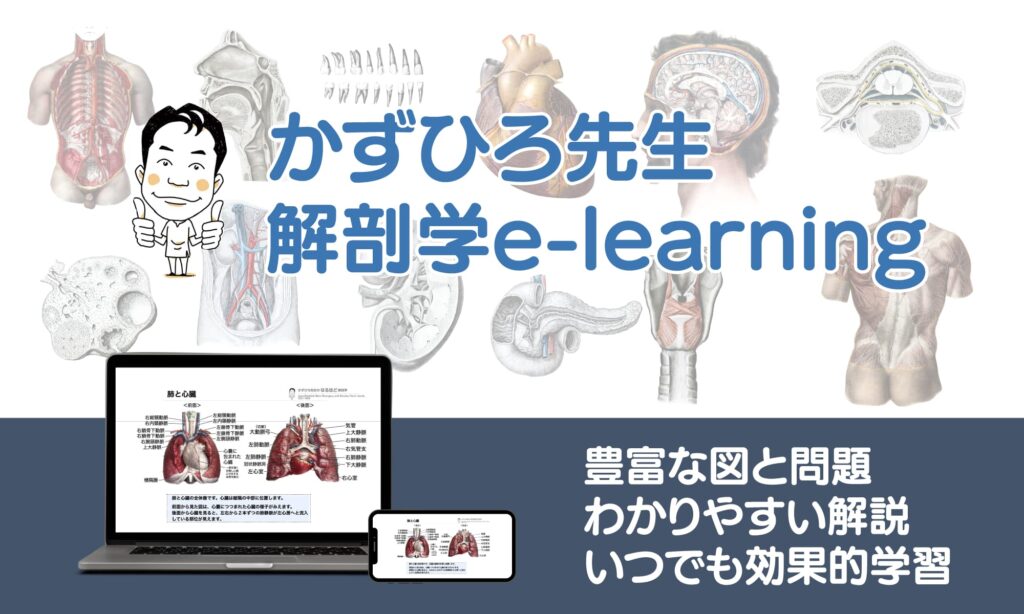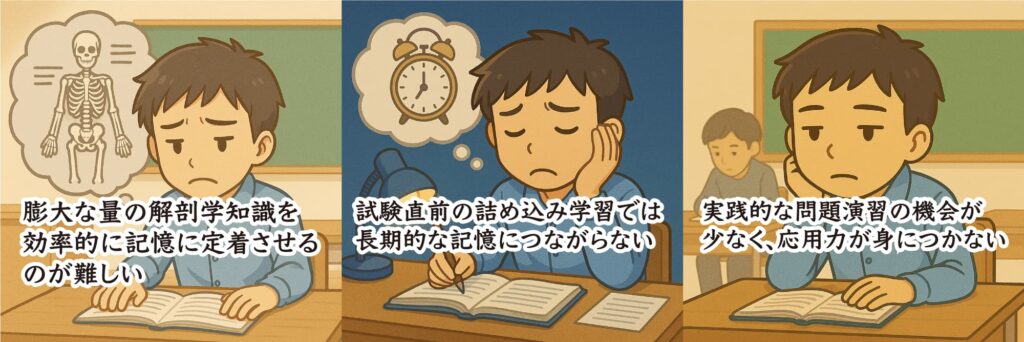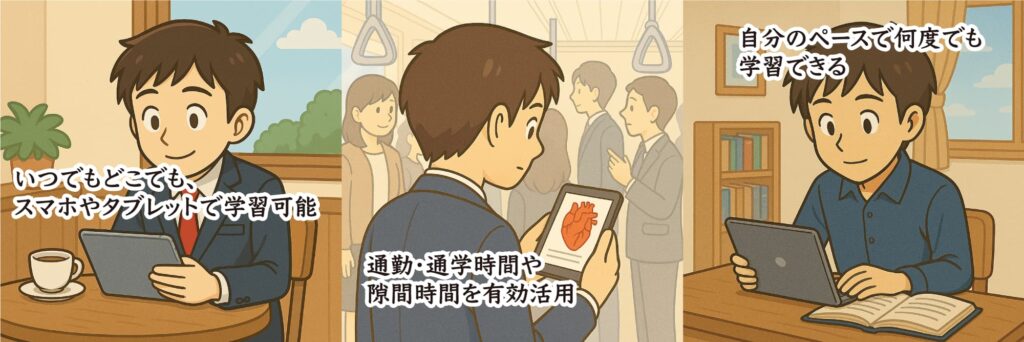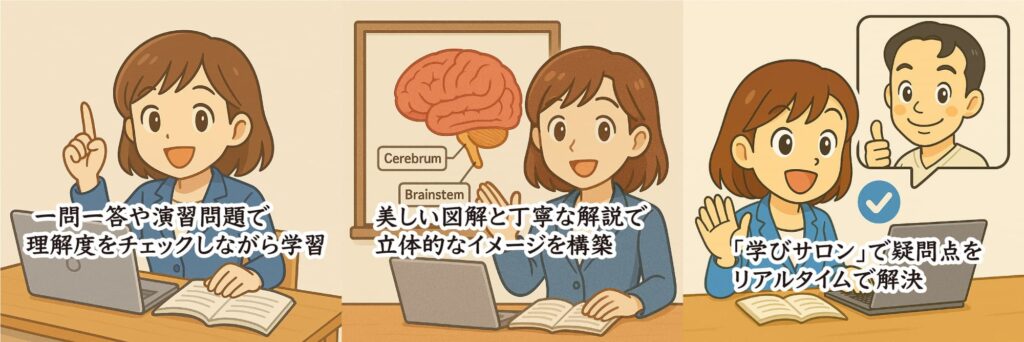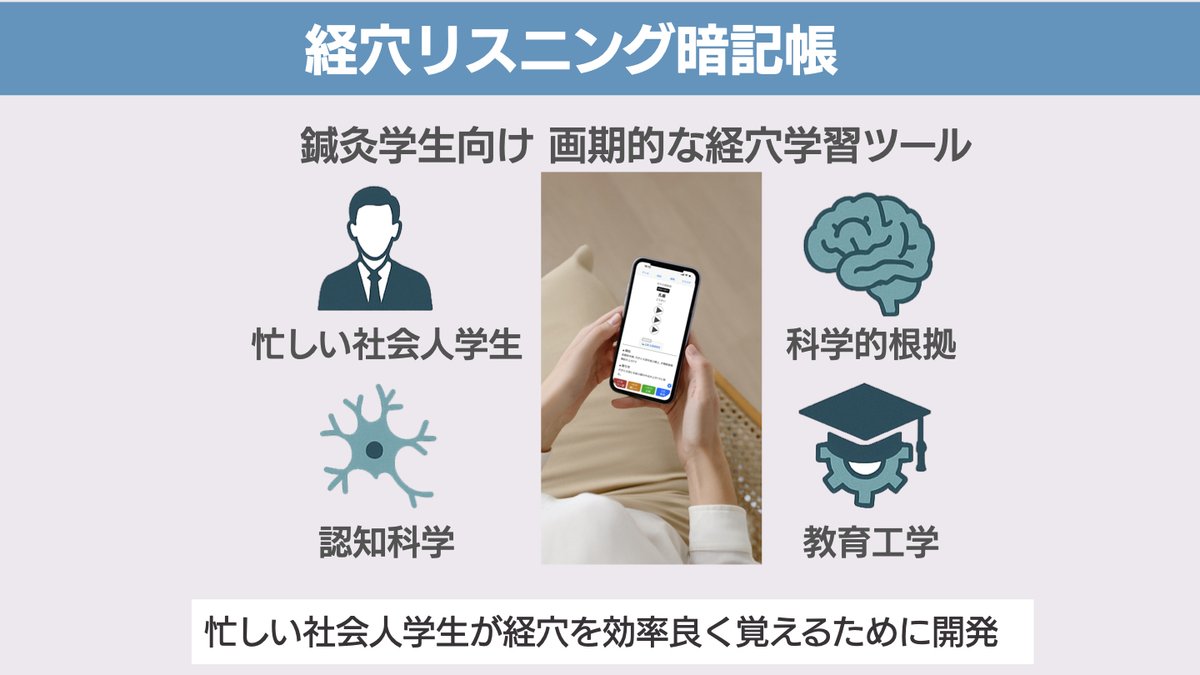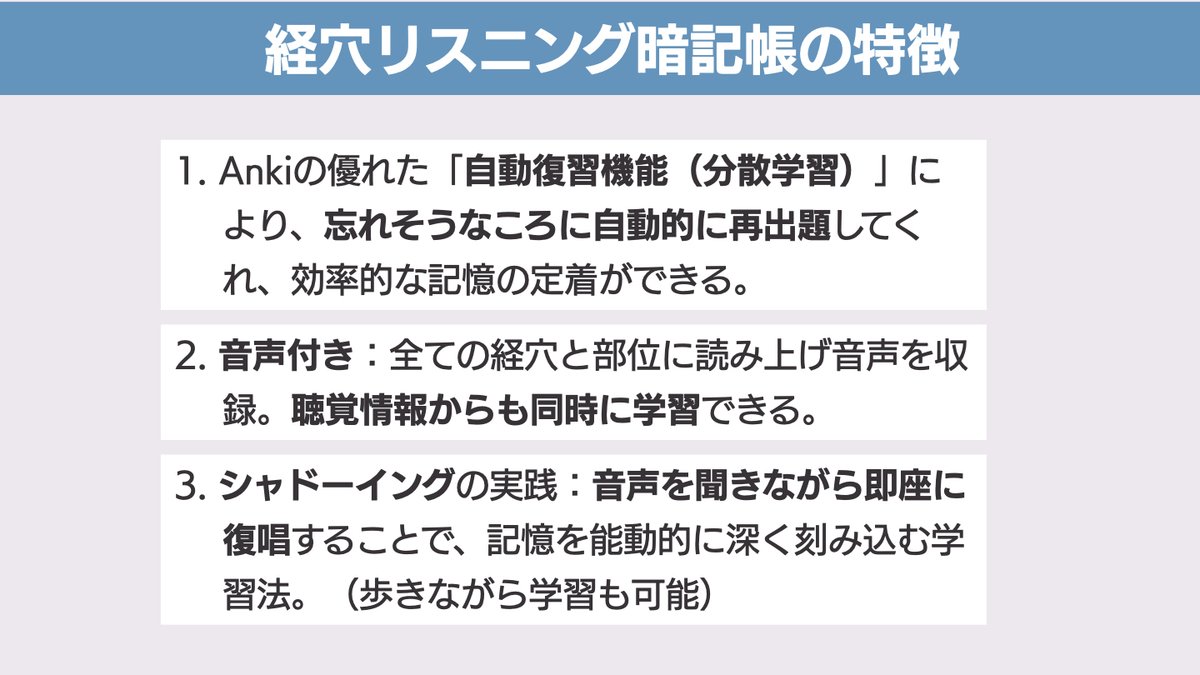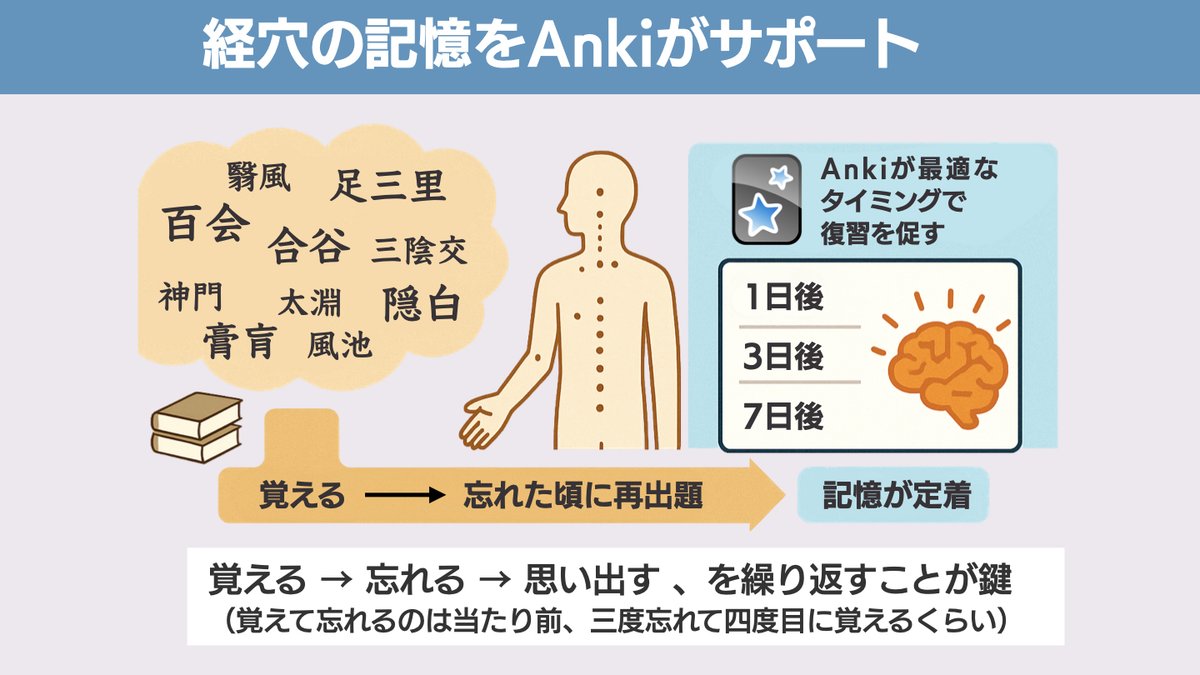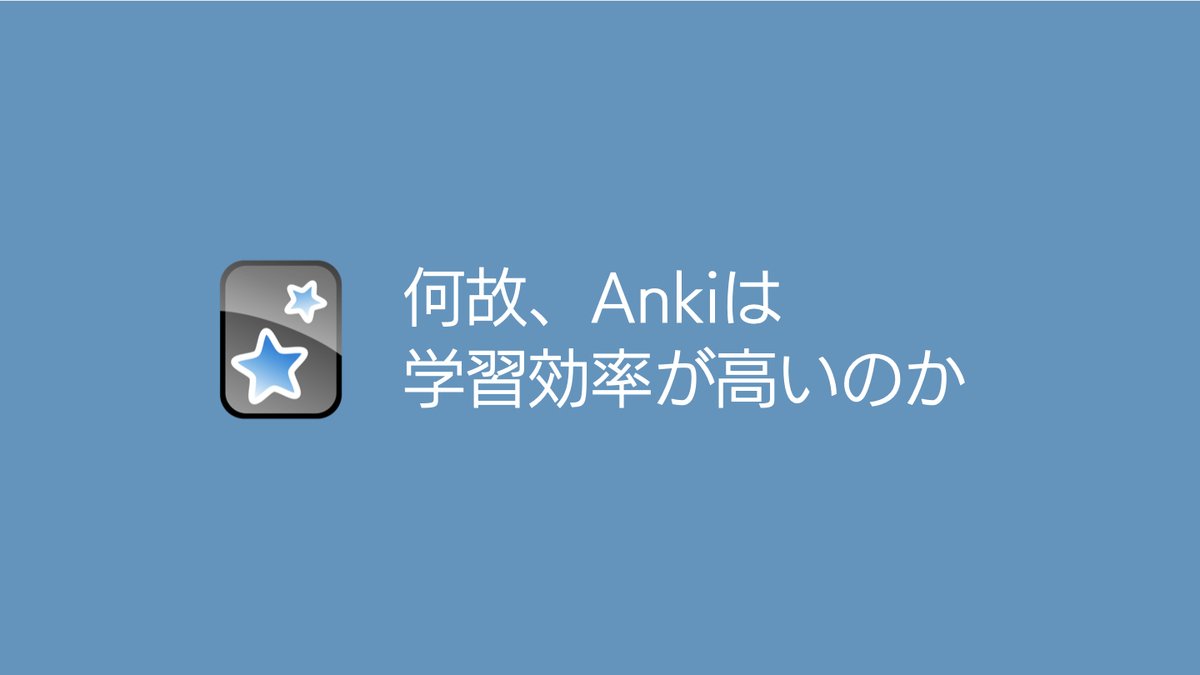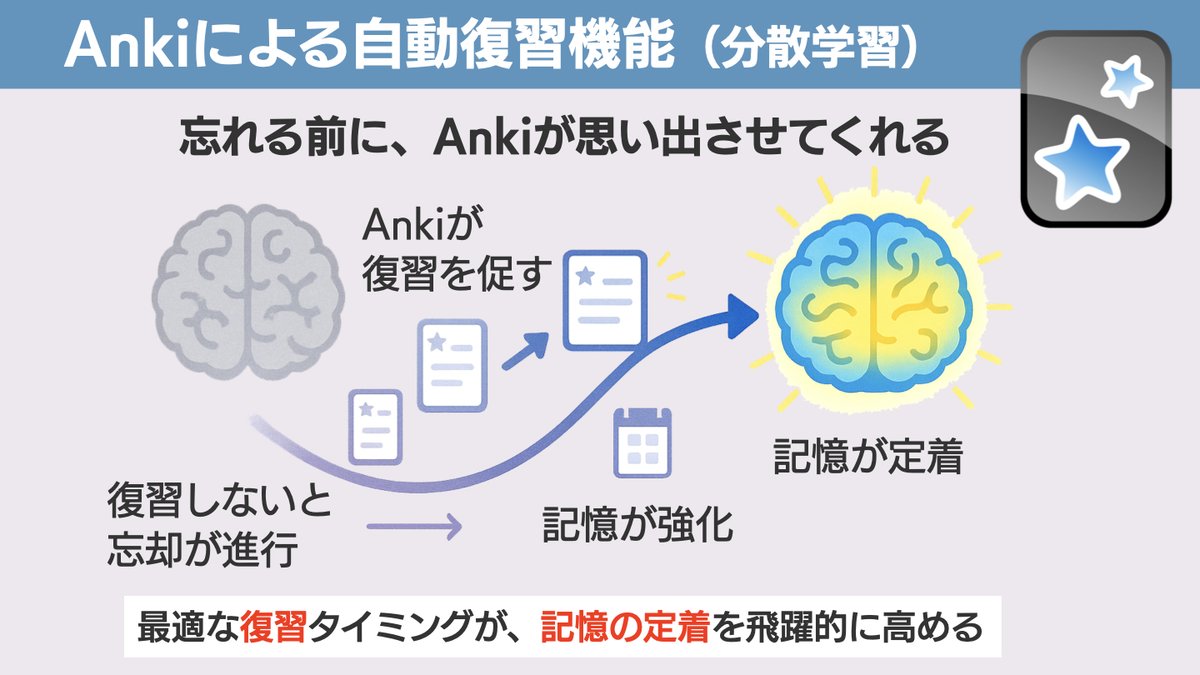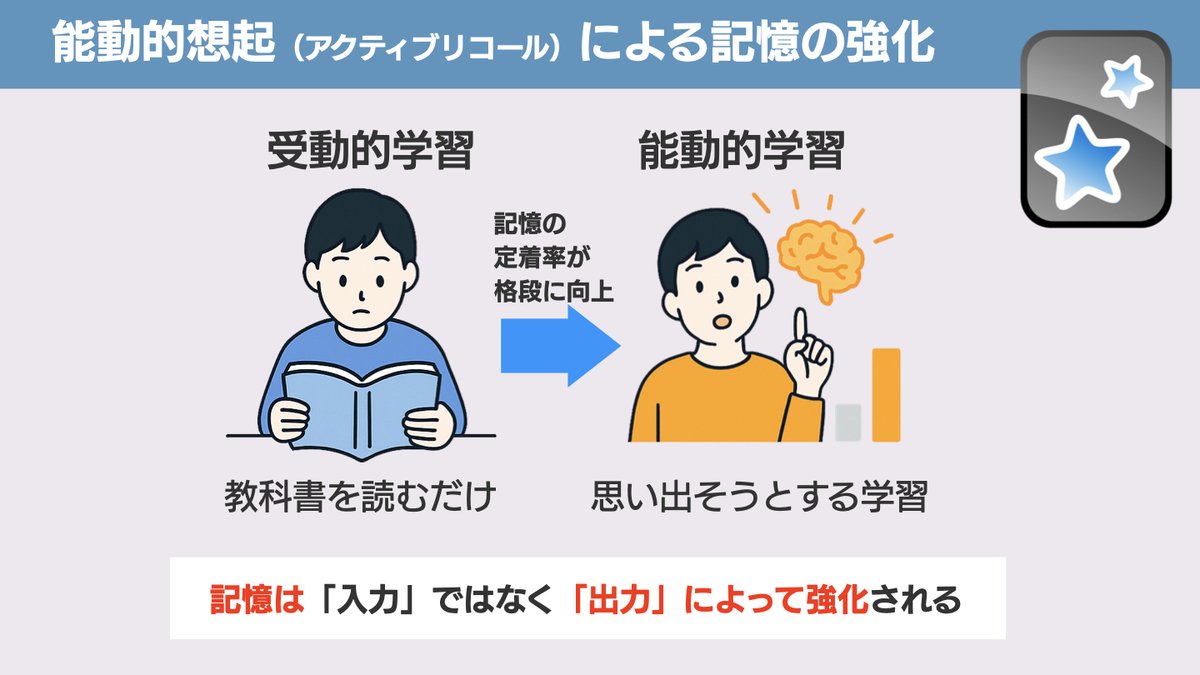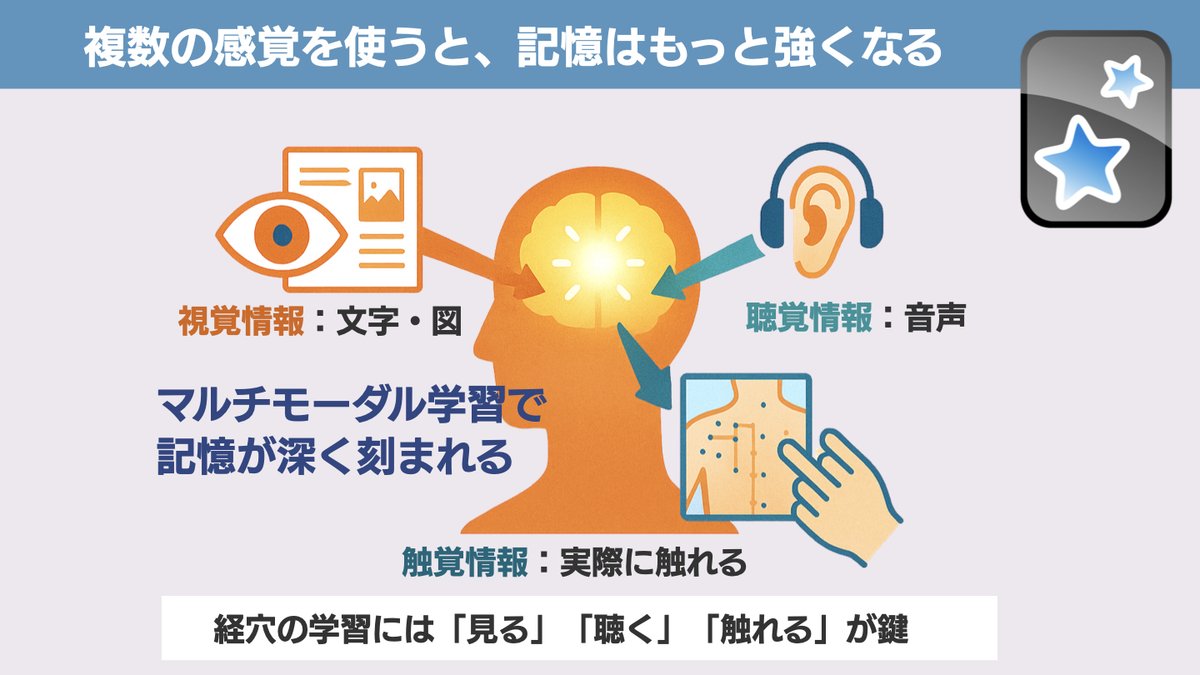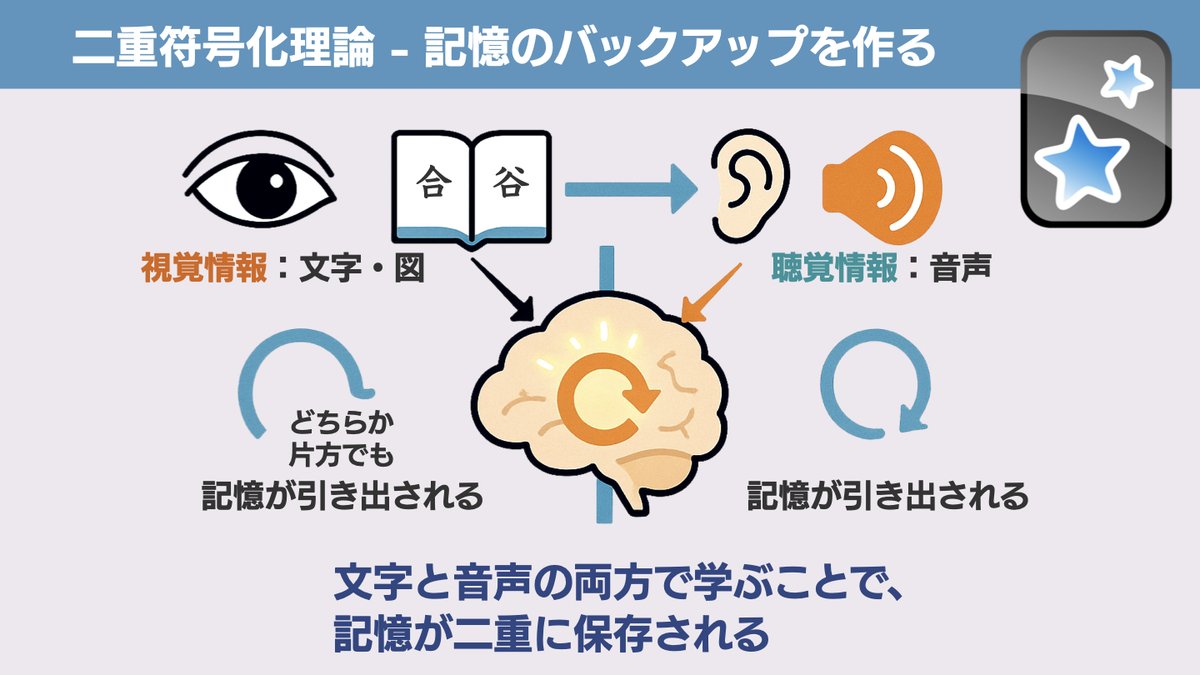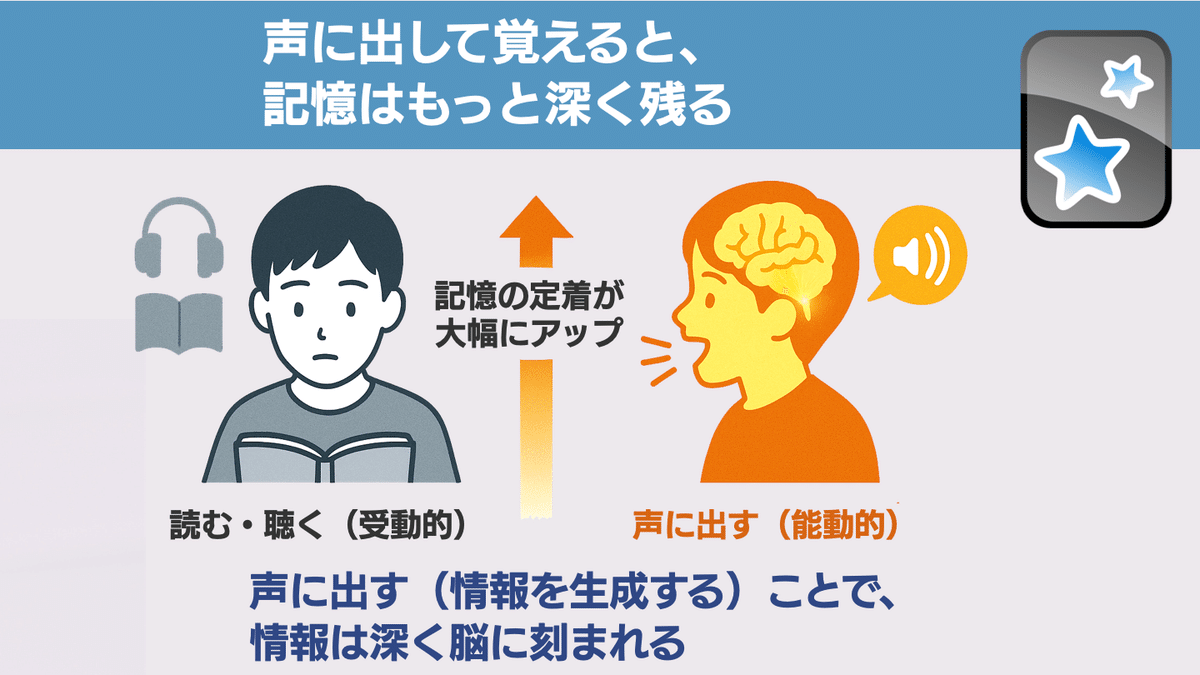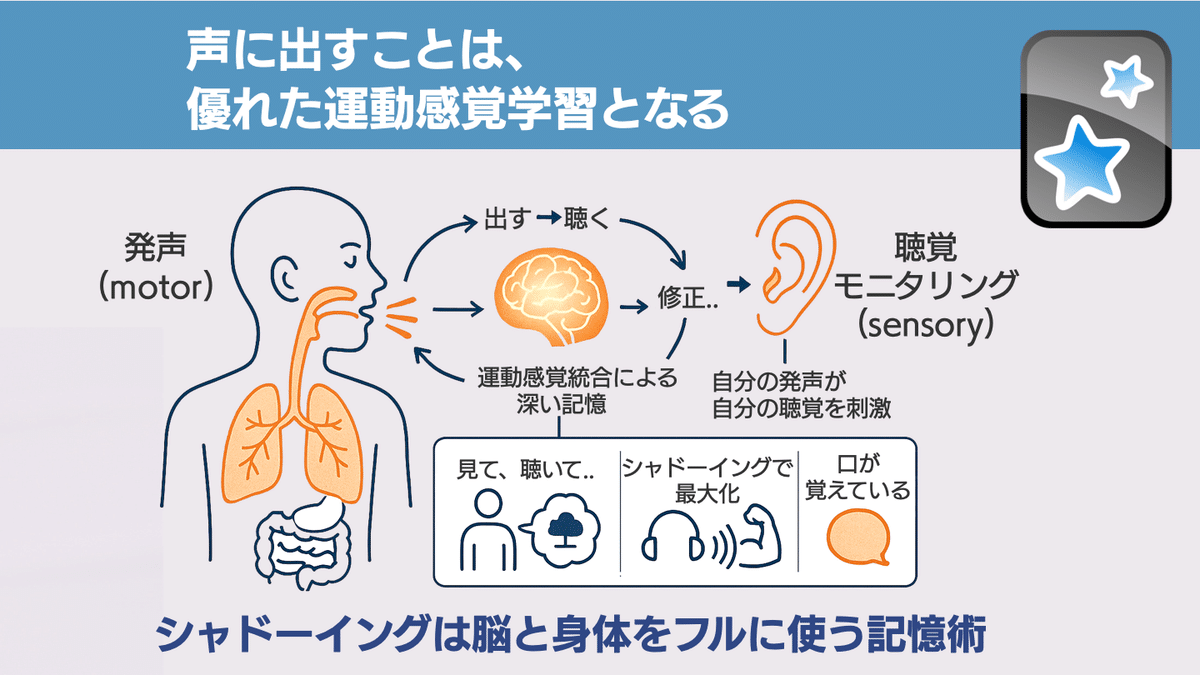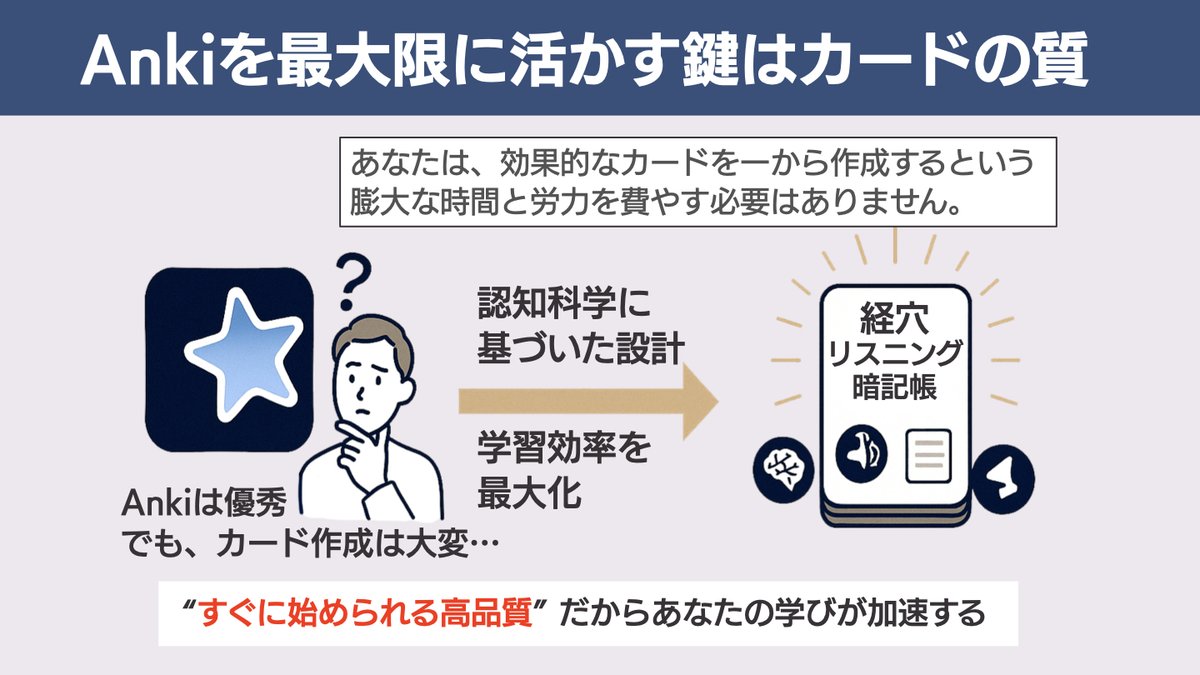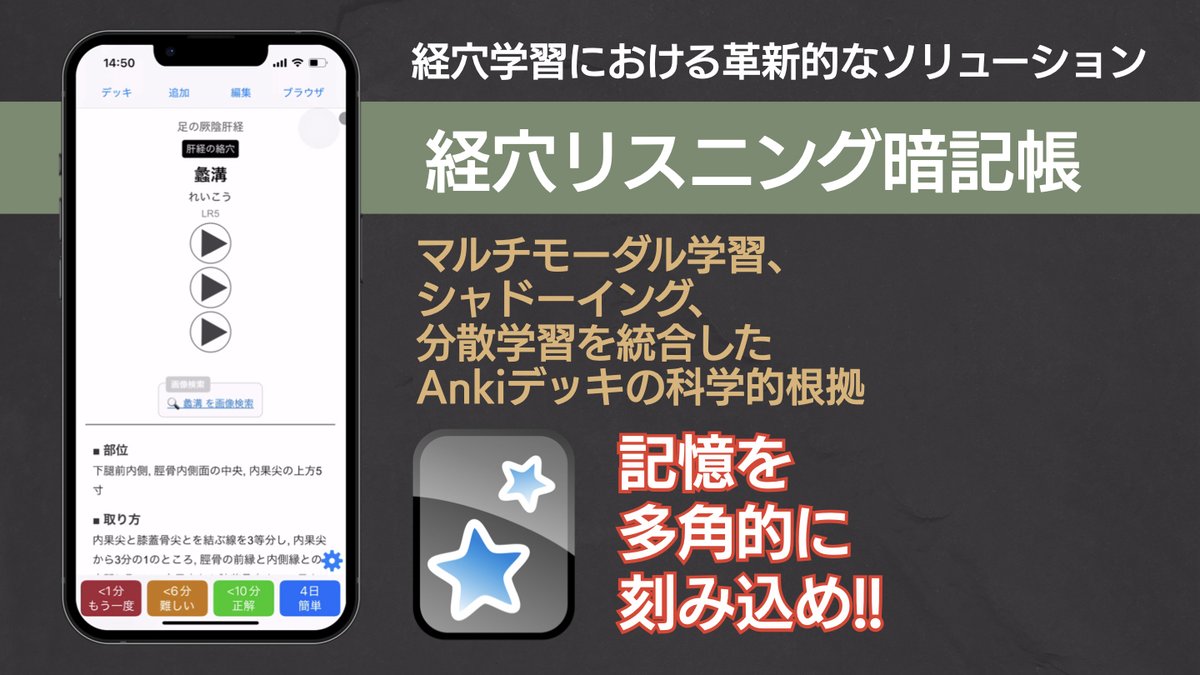引用論文
Analysis of Electroacupuncture Parameters for Irritable Bowel Syndrome: A Data Mining Approach
「過敏性腸症候群に対する電気鍼刺激パラメータのデータマイニング解析」
背景
過敏性腸症候群(IBS)は、再発性の腹痛や不快感、排便習慣の変動を主徴とする機能性消化管障害であり、全人口の約11.2%に影響を及ぼすとされます。その慢性再発性の症状は医療コストを押し上げ、患者の生活の質(QOL)を著しく低下させる一方、従来の薬物療法(下痢型には消化管運動調節薬、便秘型には下剤など)は副作用や奏功率の限界が指摘されており、補完代替医療への関心が高まっています。鍼治療、特に電気鍼(EA)は消化管運動の正常化、内臓過敏性の抑制、腸脳相関の調節、免疫・腸内細菌叢への影響など多様な生物学的メカニズムを介してIBS症状を軽減すると報告されてきました。しかし、臨床で用いられるEAの具体的な刺激パラメータ(周波数、波形、治療時間、コース期間)や経穴処方の最適組み合わせをまとめた体系的な知見は未だ不足しています。本論文では、2013年から2024年に発表されたIBSに対するEAランダム化比較試験(RCT)を対象に、データマイニング技術を駆使して効果的なEA刺激条件および経穴処方ルールを抽出し、エビデンスにもとづくEAプロトコルの確立を目指しました 。
目的
本研究は以下の二点を主たる目的とします。
-
IBS患者に対するEA介入試験から、頻用される刺激周波数、波形、刺激持続時間、治療コース、施術頻度といったEAパラメータの実態を抽出し、その関連性を規則化する。
-
RCTで報告された32件の経穴処方から、最も効果的と考えられる経穴の組み合わせを特定し、IBS治療におけるコア経穴ネットワークを可視化・階層化する。 。
方法
-
文献検索と選定:PubMed、Cochrane Library、Embase、Web of Science、OVID、PubScholar、CNKI、Chongqing VIP、万方データベースの9つを対象に、2013年1月〜2024年12月の期間で「electroacupuncture」「acupoints」「Irritable Bowel Syndrome」をキーワードに検索。英語・中国語論文を含め、EAパラメータと経穴記載が明確なRCTを抽出し、最終的に30件、計2,906例を解析に組み入れた。
-
品質評価:抽出論文のバイアスリスクをCochrane RoB 2ツールで評価し、「低リスク」「懸念あり」「高リスク」の三段階に分類。多くはランダム化手順と盲検化不足が問題となっていた。
-
データマイニング手法:
-
Excel®で基本的集計および記述統計を実施。
-
SPSS ModelerのAprioriアルゴリズムで、EAパラメータと経穴処方の「アソシエーションルール解析」を行い、高支持(support)かつ高信頼(confidence)な組合せを抽出。
-
Gephiによる「複雑ネットワーク解析」で経穴間の共起ネットワークを構築し、ノード(経穴)の中心度を可視化。
-
k-core階層化分析で、経穴ノードのコア度を算出し、IBS治療における「コア経穴群」を同定。 。
-
結果
-
EA刺激パラメータ:頻出条件は「周波数2 Hz」「波形は連続または拡張波(dilatational wave)」「1回30分」「コース期間4週間」「1日1回の施術」であった。特に周波数2 Hzと波形の組合せが、緩和的効果に最も多く報告されていた。
-
経穴処方:32の処方から合計27経穴を抽出。胃経(ST)と膀胱経(BL)が最頻用経絡で、ST25(天枢)、ST37(上巨虚)、ST36(足三里)の三穴が単独でも最も多用された。
-
アソシエーションルール:「ST25→ST37」の組合せが最高の支持度を示し、次いで「ST36→SP6」「LR3→ST37」などが高い信頼度を得た。
-
複雑ネットワーク解析:経穴ノードの中心度に基づく階層化では、下記8穴が「コア経穴」として浮上した。
-
ST25(天枢)
-
ST37(上巨虚)
-
ST36(足三里)
-
SP6(三陰交)
-
LR3(太冲)
-
BL25(大腸兪)
-
LI11(曲池)
-
RN4(関元) 。
-
考察
解析結果は、IBS治療におけるEAプロトコル設計の方向性を示唆します。低周波(2 Hz)は鎮痛および副交感神経優位へのシフトを誘導しやすく、連続・拡張波はより安定的な神経調節をもたらすと考えられます。また、ST25・ST37・ST36は腹部および下肢の消化管運動・内臓感覚に関連し、SP6・LR3は肝脾の気血調整、BL25・LI11・RN4は下腹部の気血循環促進と腸管アクシス制御に寄与するとされ、TCM理論と臨床データが整合する結果です。ただし、RCTの一部に盲検化不十分や対照群のバリエーションが大きいといった方法論的制限があるため、本研究で同定されたEAプロトコルは「有望性」を示すものであり、厳密な多施設共同RCTによる再検証が必要です 。
結論
IBSに対するEA治療では、「2 Hz・連続または拡張波・30分・4週間・1日1回」といった基本刺激条件に、コア経穴群(ST25→ST37を中心に、ST36、SP6、LR3、BL25、LI11、RN4の併用)が有効性の高いプロトコル候補として浮上しました。これらの知見は、今後の臨床プロトコル標準化やガイドライン策定に資する基礎データとなりますが、さらなる高品質RCTによる検証が望まれます 。
使用している経穴
-
ST25(天枢)
-
ST37(上巨虚)
-
ST36(足三里)
-
SP6(三陰交)
-
LR3(太冲)
-
BL25(大腸兪)
-
LI11(曲池)
-
RN4(関元)