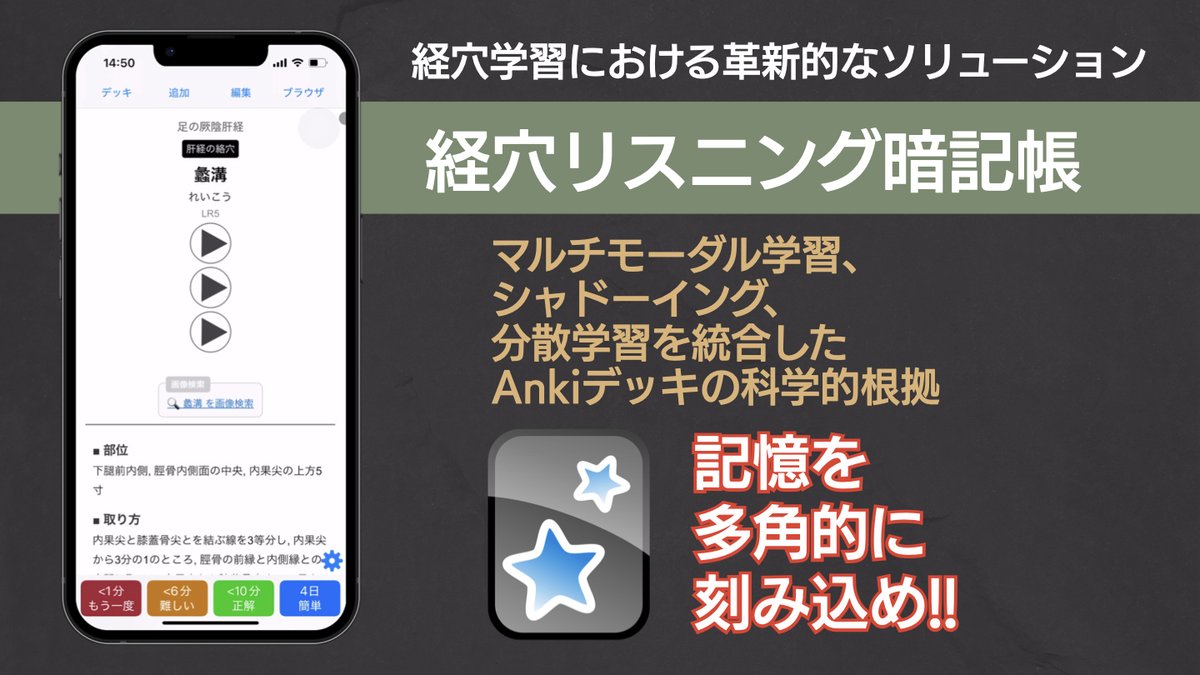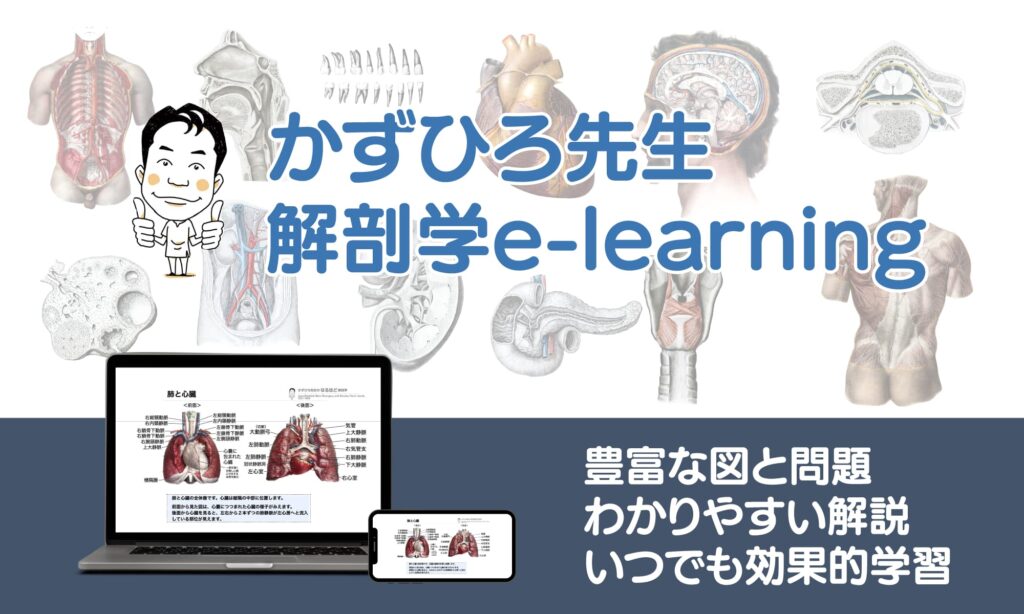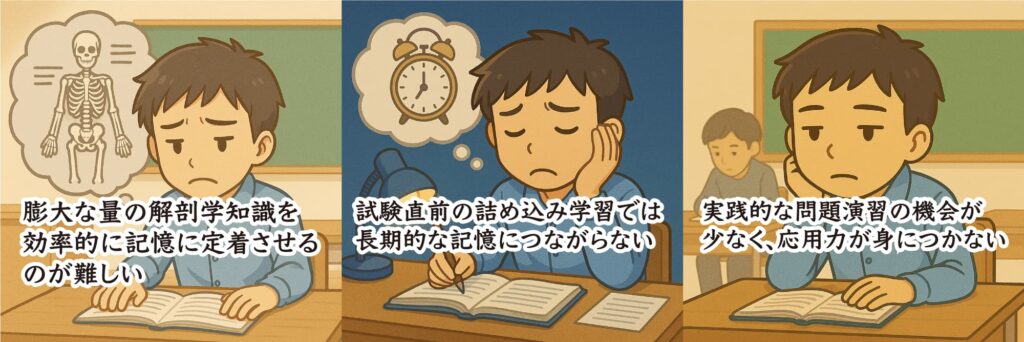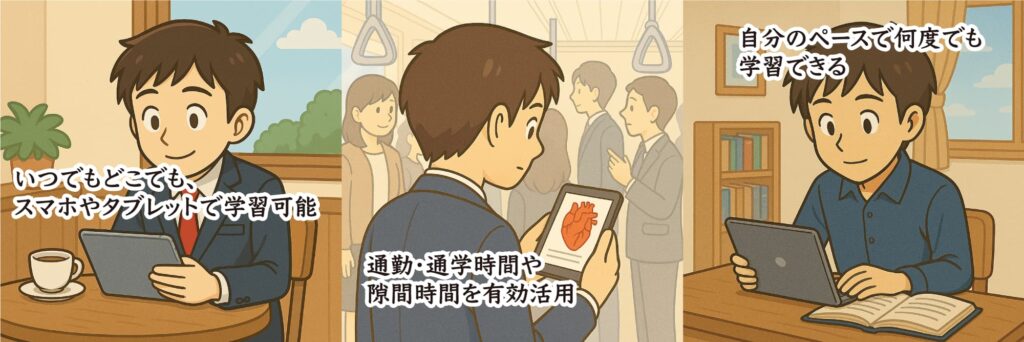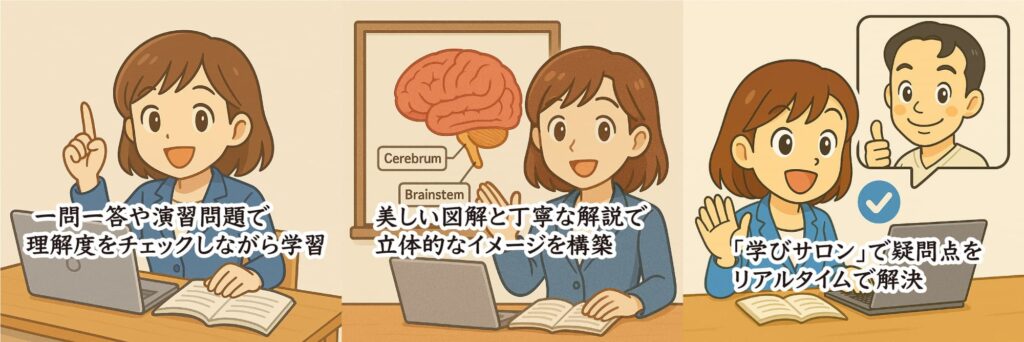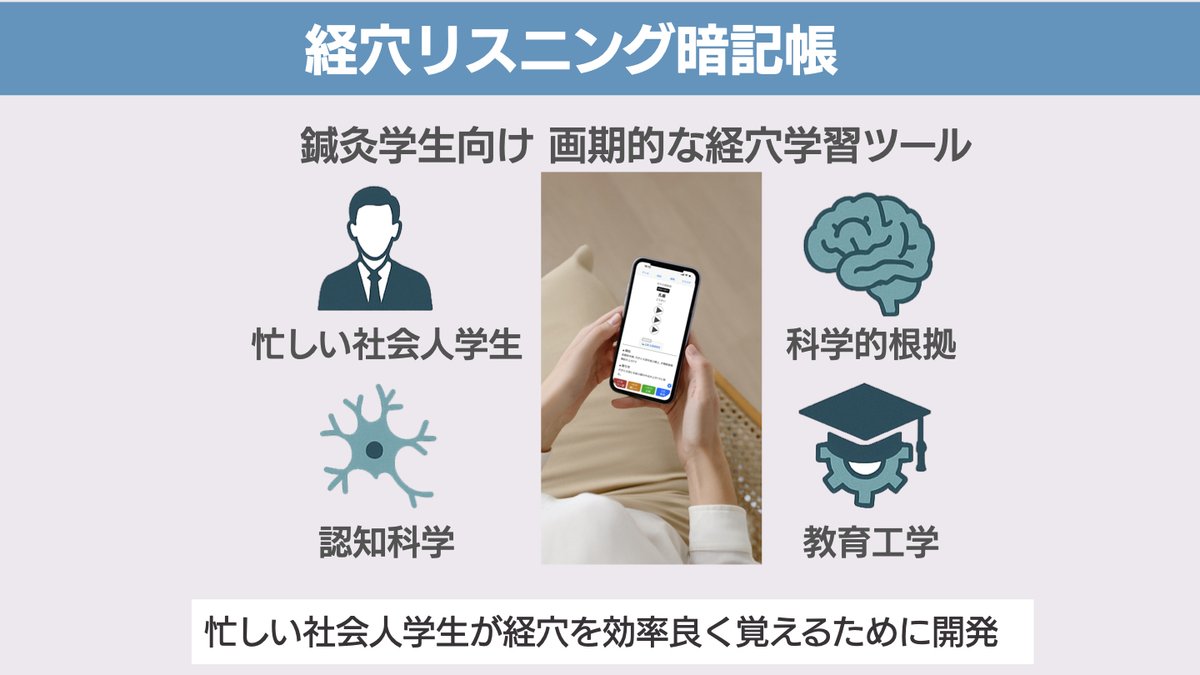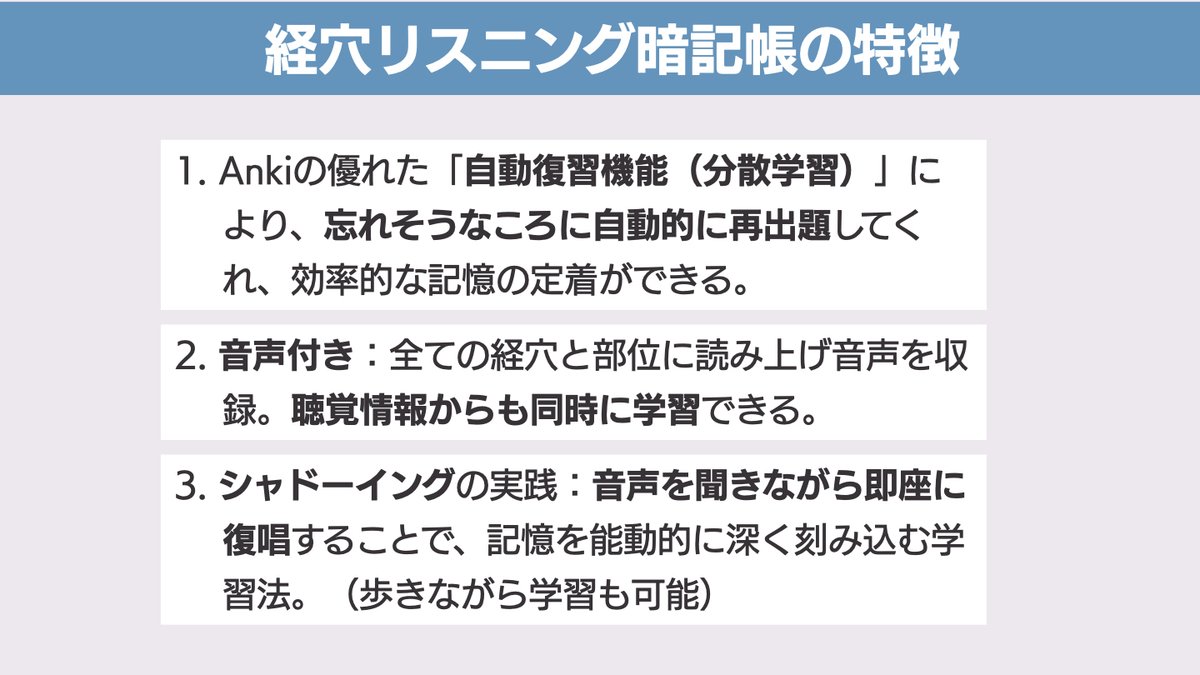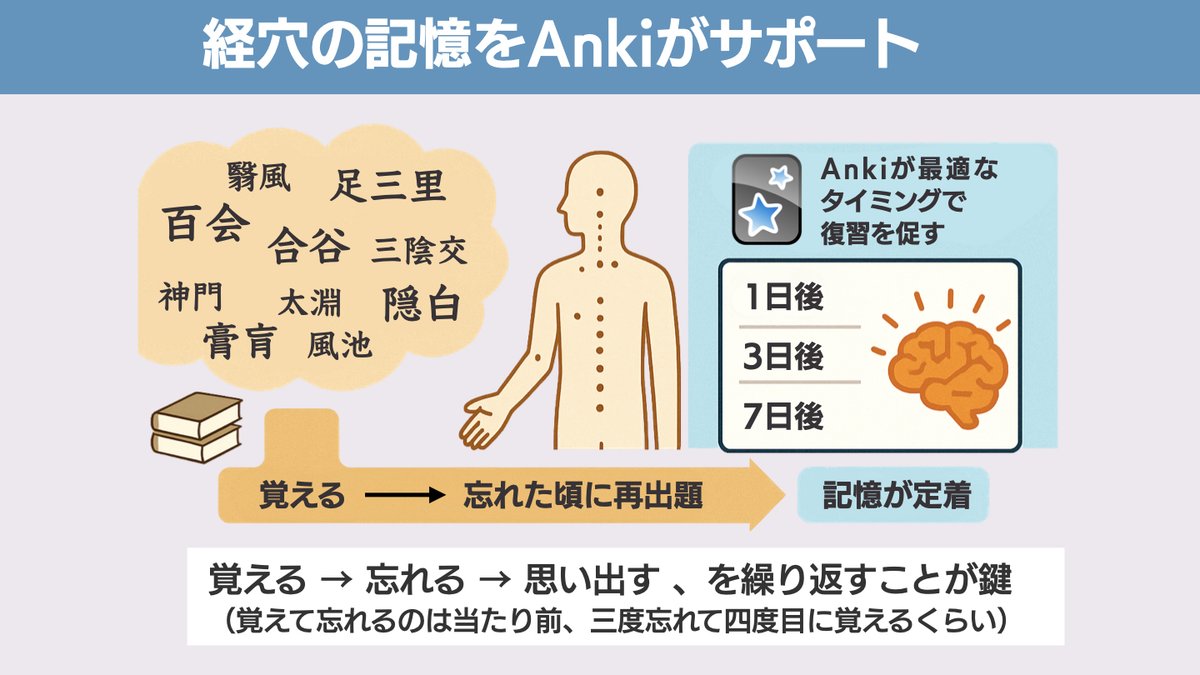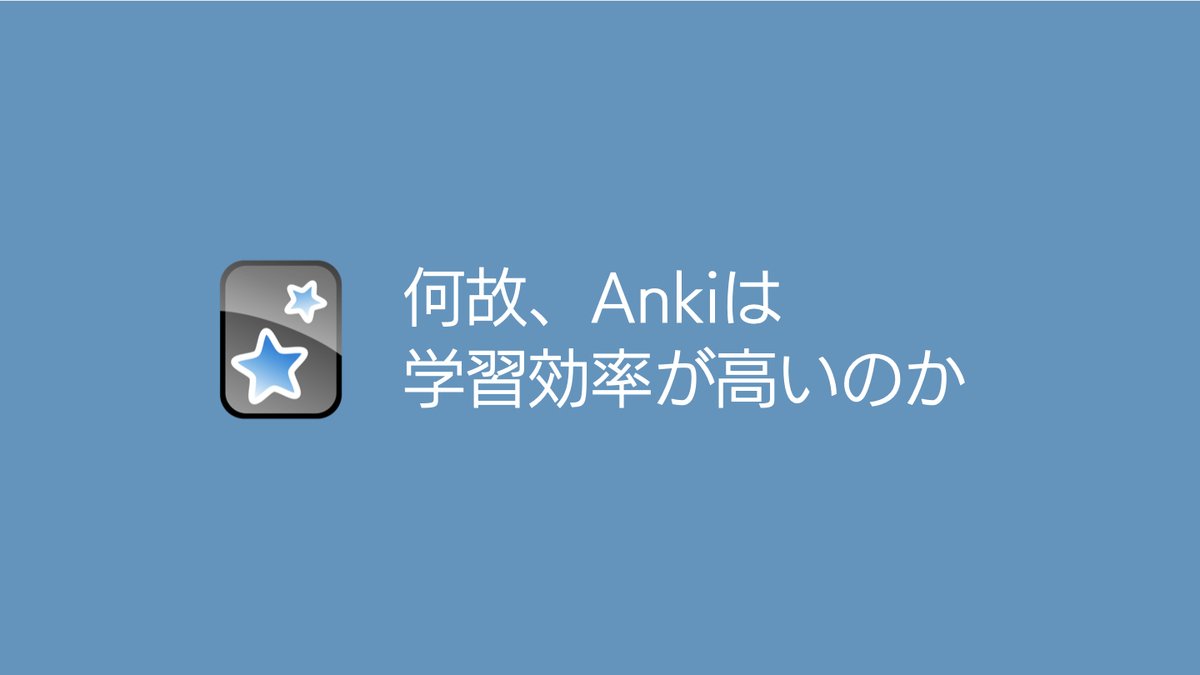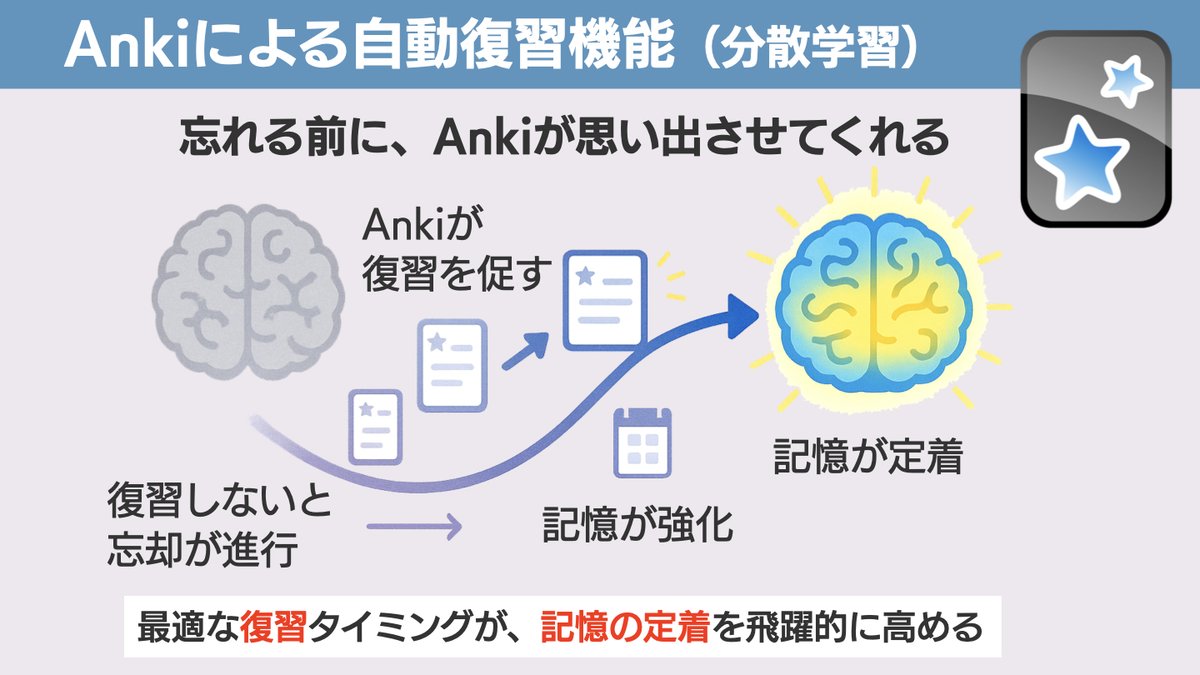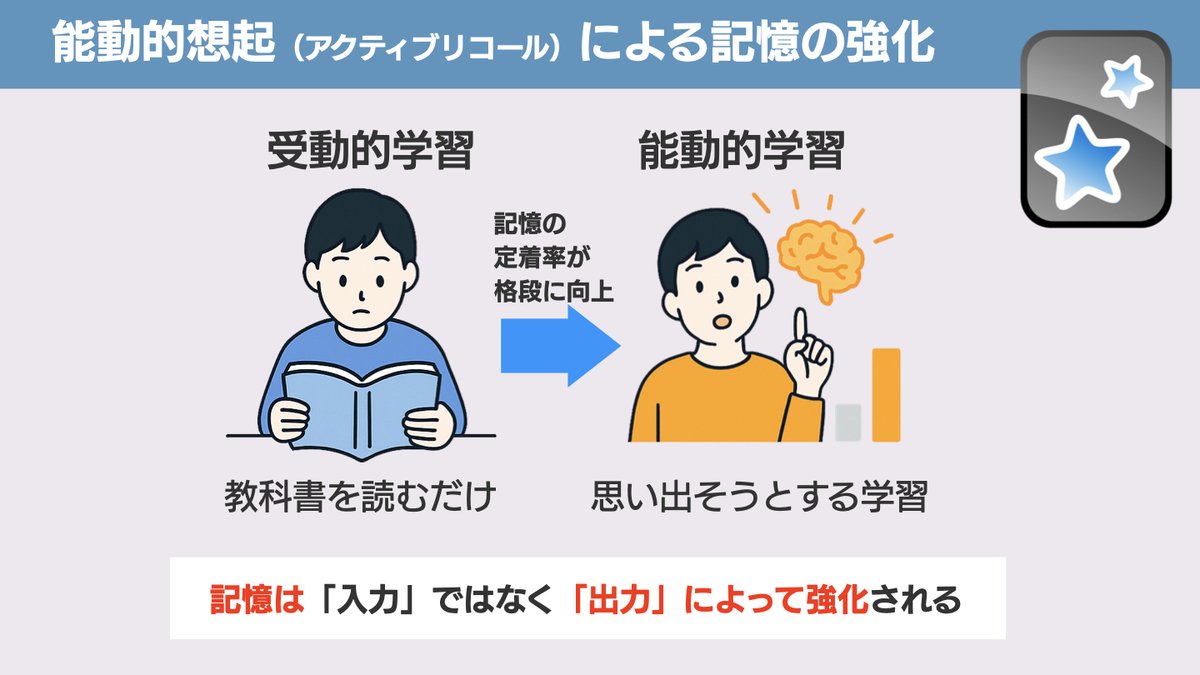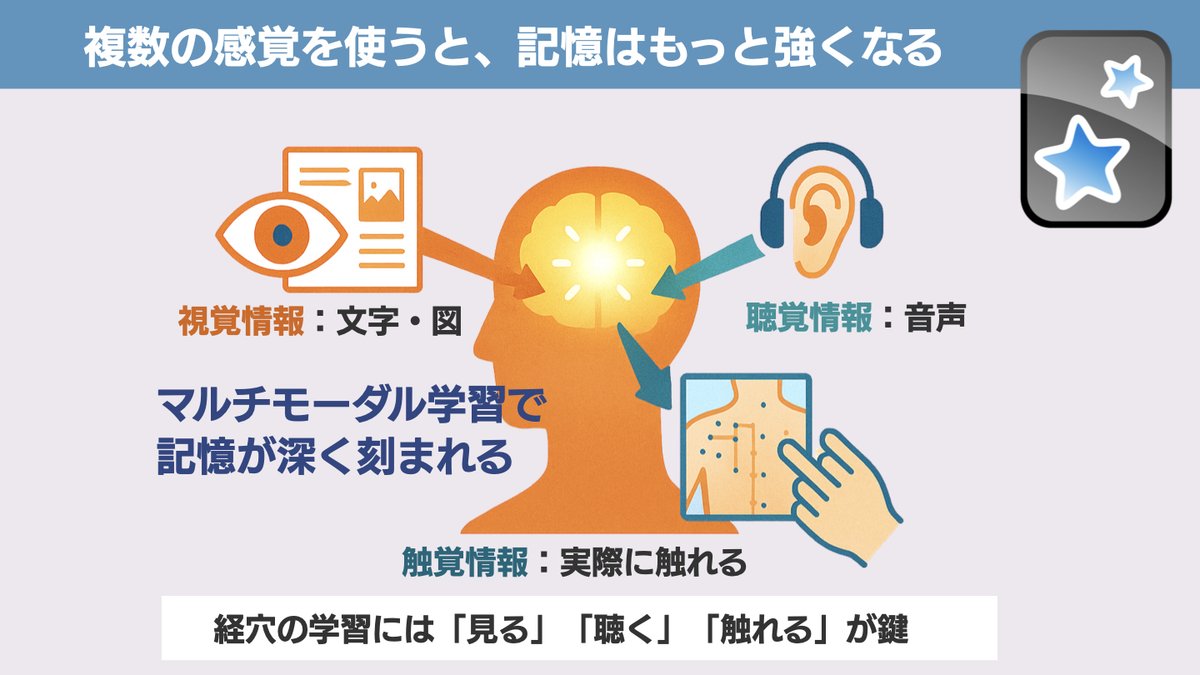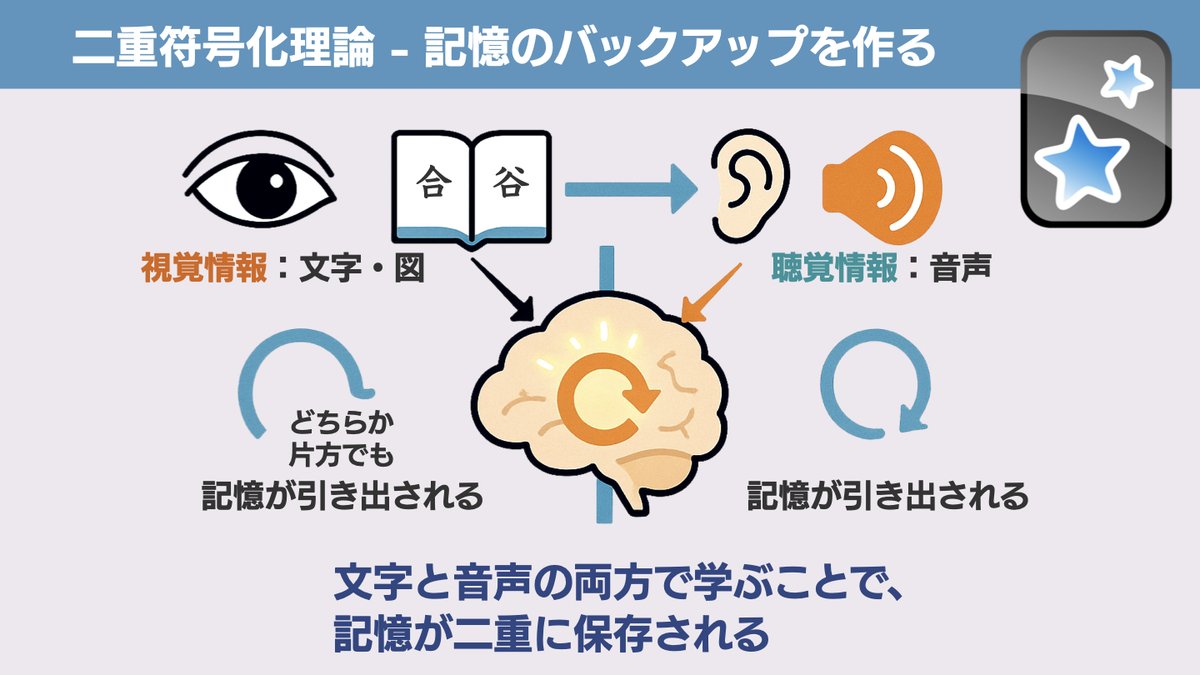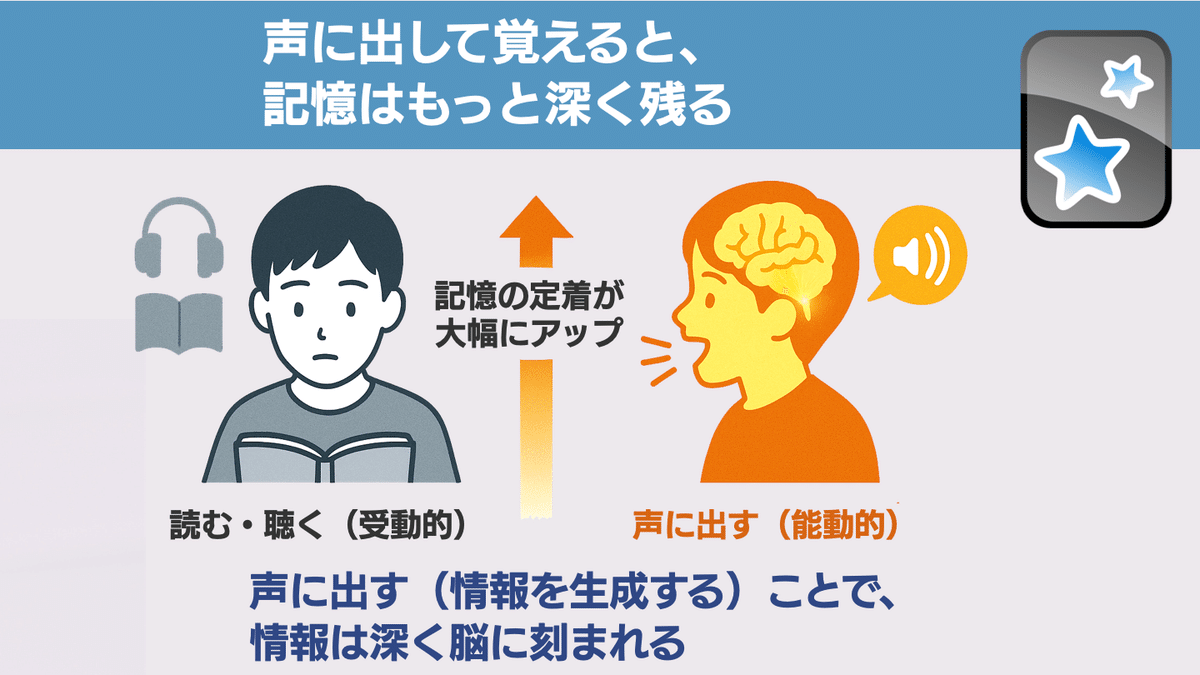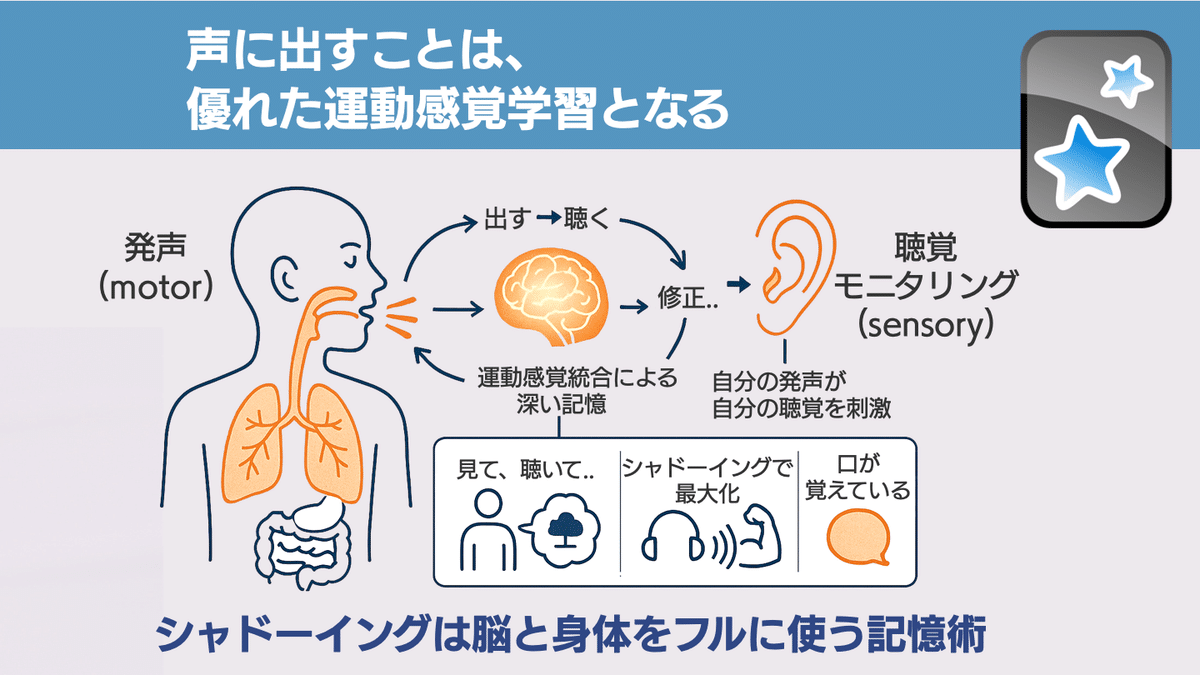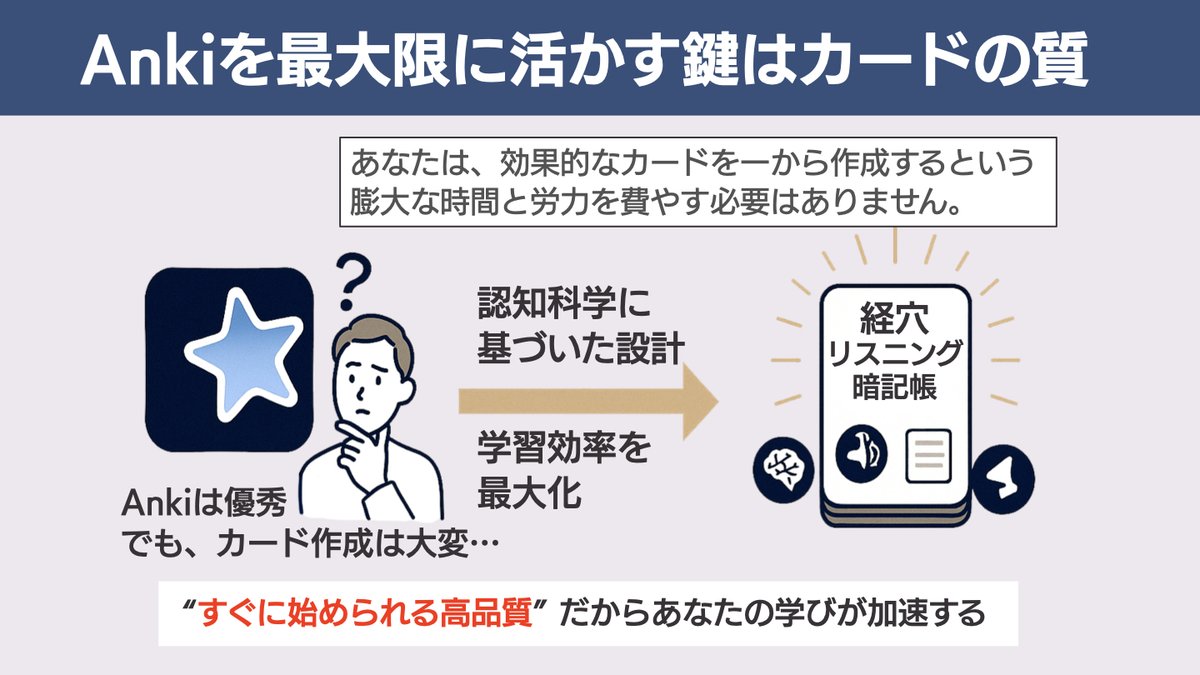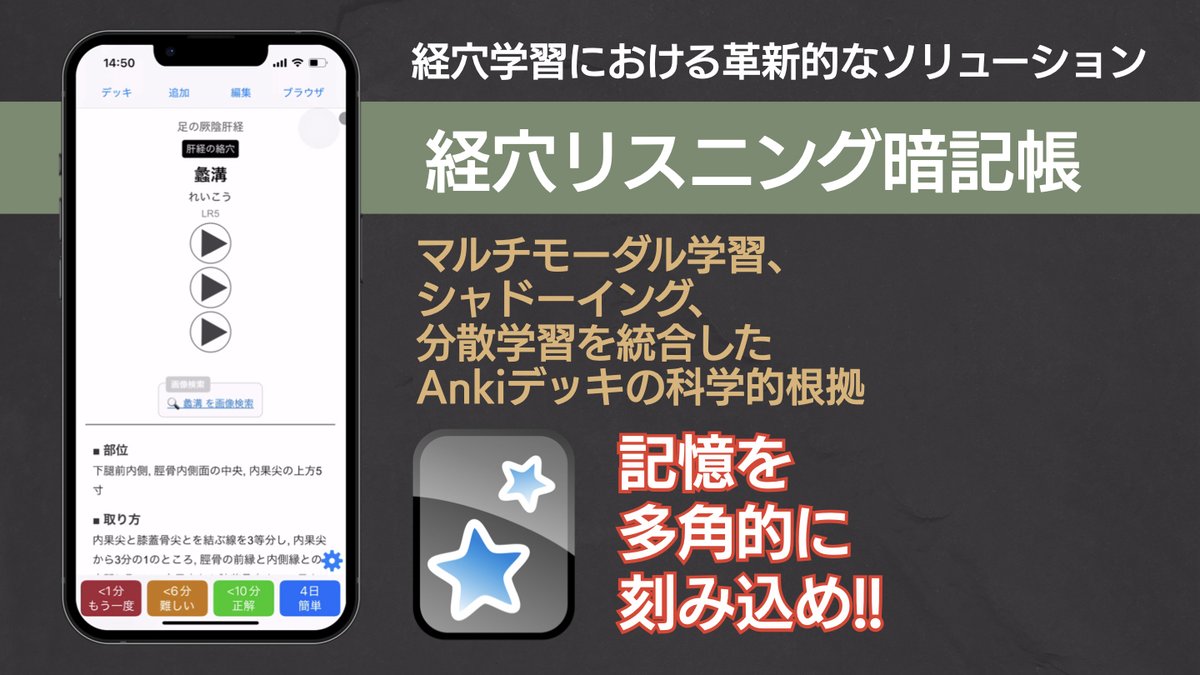引用論文
Effects of Electroacupuncture for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis
「膝骨関節炎に対する電気鍼治療の効果:系統的レビューおよびメタアナリシス」
背景
膝骨関節炎(KOA)は高齢者に多くみられる変性関節疾患であり、関節軟骨の摩耗や骨棘形成、滑膜炎などを通じて持続的な疼痛と運動機能障害を引き起こします。日本国内でも有病率は上昇傾向にあり、日常生活動作の制限からQOL(生活の質)の低下を招く深刻な課題となっています。従来の治療はNSAIDsやリハビリテーション、さらには人工膝関節置換術などが中心ですが、副作用や侵襲性、コスト面での問題も指摘されています。その一方で、電気鍼(Electroacupuncture; EA)は従来の手技鍼(manual acupuncture; MA)に低周波あるいは高周波の通電を組み合わせることで、末梢および中枢神経系を介した疼痛緩和と局所循環改善を同時に図るアプローチとして注目されています。しかし、EAのKOAに対する有効性と安全性を系統的に評価した報告は限られており、本研究ではEAの臨床的効果を明らかにすることを目的として、関連する無作為化比較試験(RCT)を体系的にレビュー・メタアナリシスした。
目的
本研究の主目的は、KOA患者におけるEAの疼痛緩和効果(主要アウトカム)および合併する関節機能・QOL改善効果(副次アウトカム)を、偽EA(sham EA)、MA、通常治療(薬物療法・理学療法)と比較して評価することである。
方法
-
検索戦略・選択基準
-
検索データベース:MEDLINE/PubMed、EMBASE、CENTRAL、AMED、CNKI、KoreaMed など計11データベースを2015年9月まで網羅的に検索し、EAを介入群とする前向きRCTを対象とした。
-
除外基準:非ランダム化試験、OA以外の疾患群混合、非侵襲的電気刺激(パッチ式)使用例、個別診断に応じた経穴選択のみを行った研究など 。
-
-
解析対象
-
システマティックレビュー:31件のRCT(計3,187名)
-
メタアナリシス:疼痛評価(VAS/WOMAC pain, NRS)を報告した8件、計1,220名 。
-
-
データ抽出・質評価
-
抽出項目:被験者特徴、診断基準、介入内容(経穴、通電周波数、持続時間、治療回数)、対照群内容、評価時期、評価尺度など。
-
バイアスリスク:Cochrane Collaboration’s ROBツールを用い、ランダム化、盲検化、欠損データ、選択的報告など7領域を評価 。
-
-
統計解析
-
効果量:尺度不一致時は標準化平均差(SMD)、一致時は加重平均差(WMD)を採用。
-
モデル:研究間の異質性(I²)が75%以上の場合はRandom Effects Model、未満はFixed Effects Modelを適用。
-
異質性解析:I²統計で評価し、高異質性時はサブグループ解析(sham EA vs. MA vs. 薬物療法)を実施 。
-
-
電気鍼プロトコルの特徴
-
使用経穴:局所膝周囲に加え、遠隔刺激点を併用(ST35、ST34、EX-LE4、SP10、GB34、SP9等)
-
通電周波数:2 Hz(低周波)、100 Hz(高周波)、あるいは両者を交互に変更するパターンなど多様 。
-
治療時間・回数:20~45分/回、8~15回のコースが一般的
-
刺鍼深度・刺激感:25~60 mm、de-qi獲得を標準化
-
結果
-
疼痛(VAS/WOMAC pain)
-
EA群は対照群と比較し、SMD = –1.86(95% CI: –2.33~–1.39, I²=75%)と大きく疼痛を軽減 。
-
-
関節機能・QOL(WOMAC total, SF-36, EQ-5D等)
-
WOMAC totalではEA群がSMD = –1.34(95% CI: –1.85~–0.83, I²=73%)で有意改善
-
SF-36精神領域および身体領域ともにEA群優位(サブ解析) 。
-
-
安全性・副作用
-
大規模研究で重篤な有害事象は報告されず、短期的には局所の軽微な痛みや出血、紅斑程度にとどまる例が多い。
-
-
異質性の要因
-
経穴選択のばらつき、通電周波数・パターンの多様性、漸増的な評価時期の違いが主因。
-
サブグループ解析では、sham EA対比でのEA効果は8週間以上のコースでより顕著であり、MA対比ではEA特有の通電刺激が疼痛制御に有効と示唆された。 。
-
考察
-
生理学的メカニズム
-
EAによるC/Aδ線維刺激が内因性オピオイド(エンケファリン、エンドルフィン)分泌を促し、ゲートコントロール機構を活性化。
-
局所血流促進により浮腫・炎症性サイトカインの除去が加速し、関節周囲軟部組織の柔軟性改善に寄与。
-
交互周波数設定は異なる神経伝達系を選択的に刺激し、多面的な鎮痛効果を発揮すると考えられる。
-
-
臨床的示唆
-
KOA治療において、EAは非薬物療法の有力な選択肢として導入可能。
-
通電周波数・経穴選択・治療期間を標準化することで、さらなるエビデンス構築と臨床ガイドラインへの反映が期待される。
-
-
研究の限界と今後の課題
-
RCTの質(盲検化不徹底、高リスクバイアス例)がまだ一部に残存。
-
長期フォローアップデータや多施設共同試験による普遍性の担保が必要。
-
副作用プロファイルの詳細な報告と、定量的な血流・炎症マーカー評価を含む生理学的アウトカムの導入が望まれる。
-
結論
EAはKOA患者の疼痛軽減と関節機能・QOL改善において統計学的に有意な効果を示し、安全性にも優れる。その臨床応用にあたっては、プロトコル(経穴選択、通電周波数、治療期間)の最適化と標準化を図りつつ、大規模長期RCTによるエビデンス拡充が今後の重要課題である。
使用経穴一覧
-
ST35(犢鼻)
-
ST34(梁丘)
-
EX-LE4(内膝眼)
-
SP10(血海)
-
GB34(陽陵泉)
-
SP9(陰陵泉)