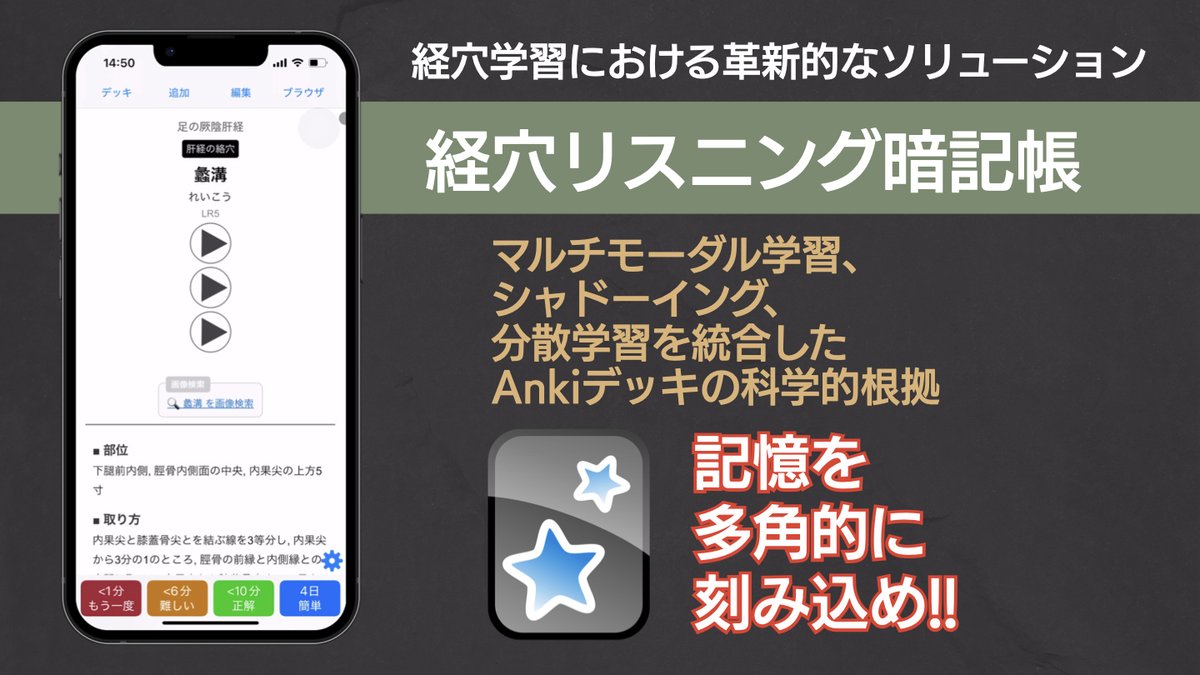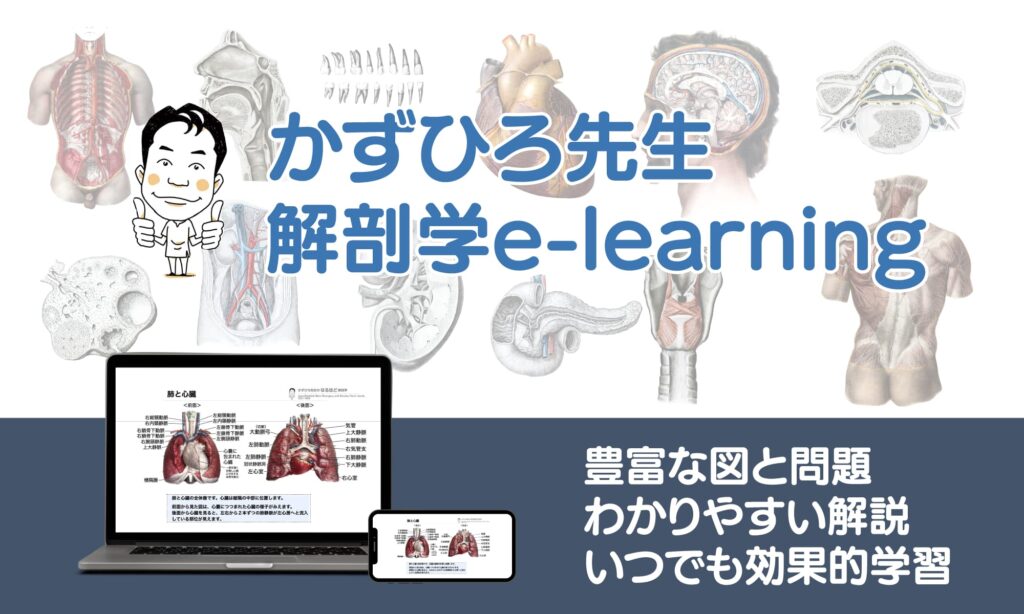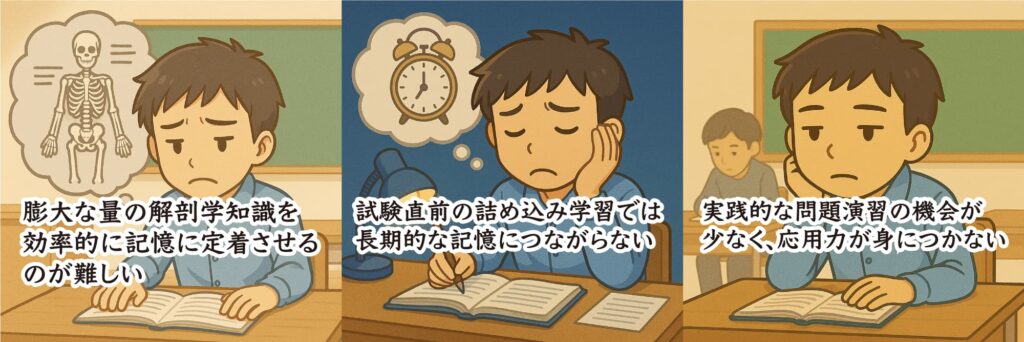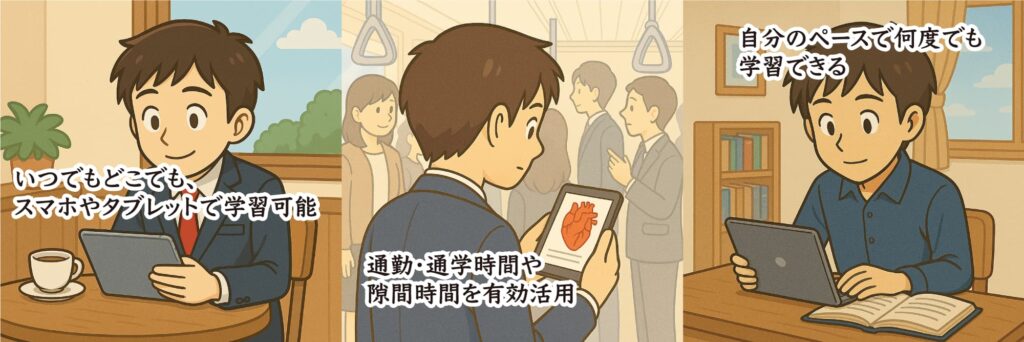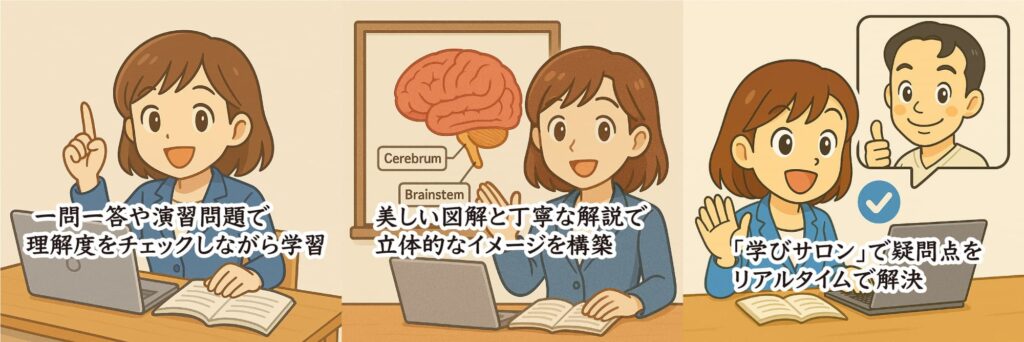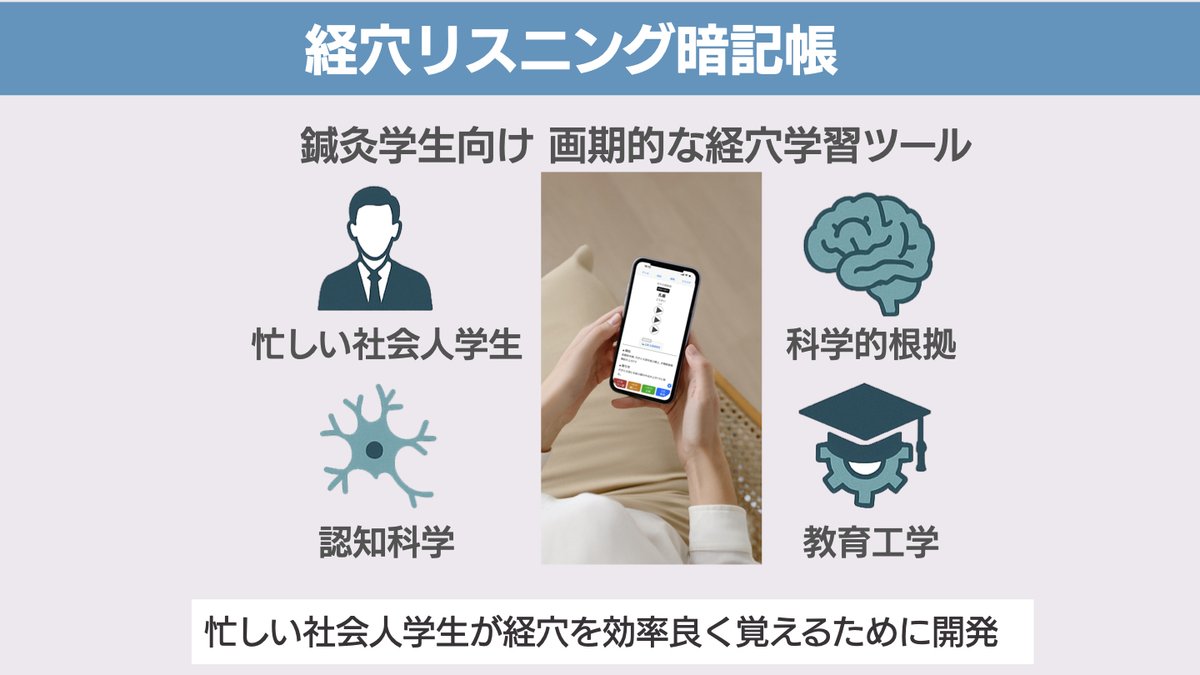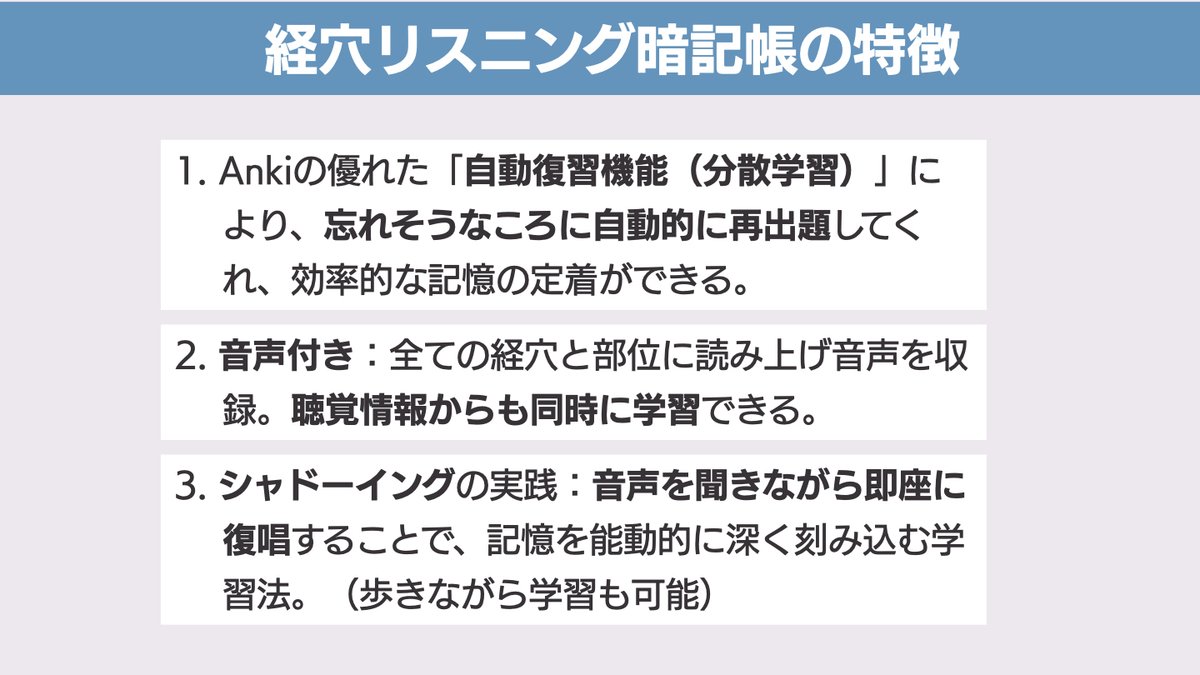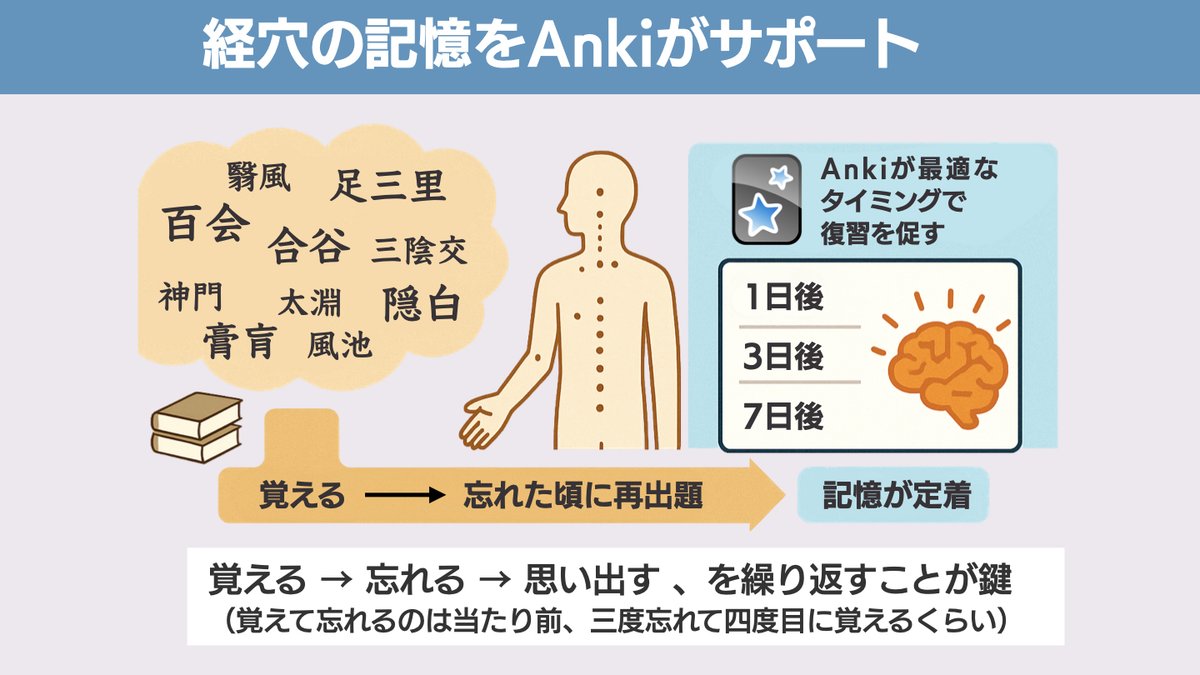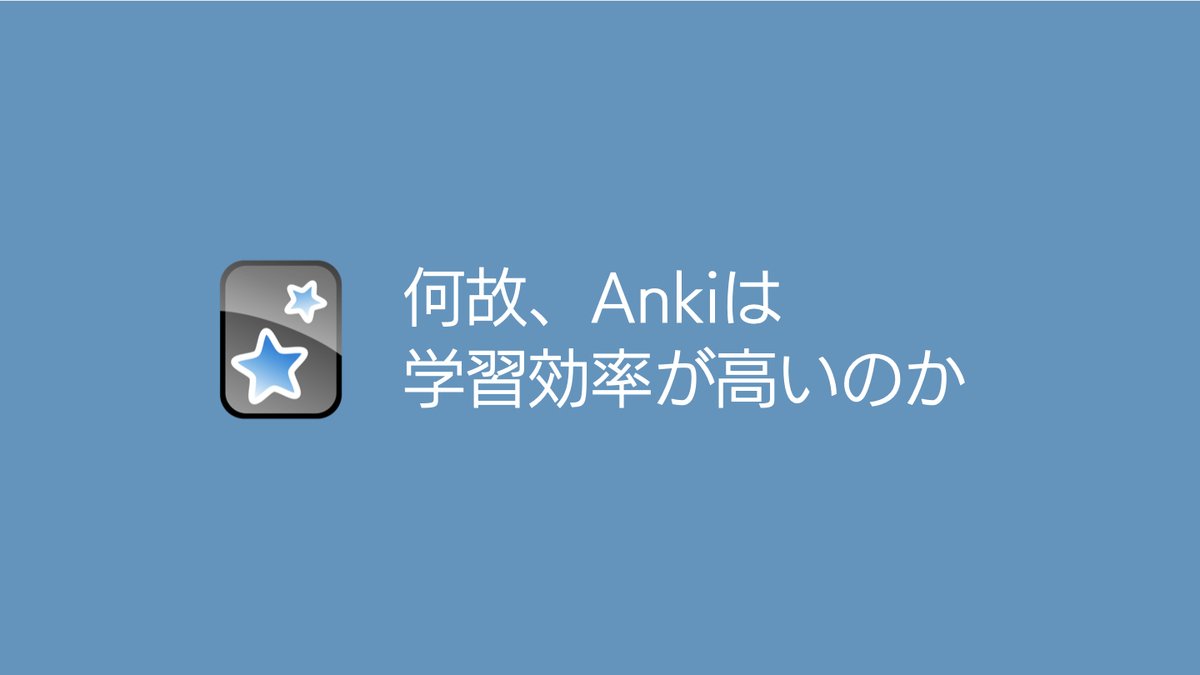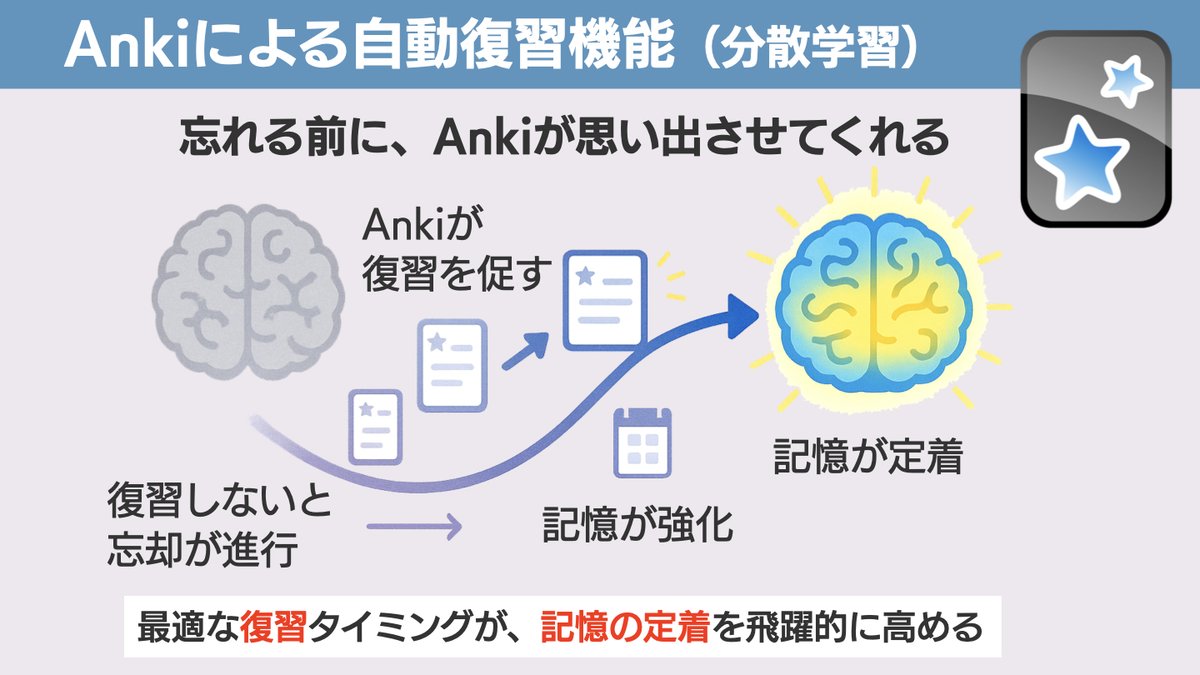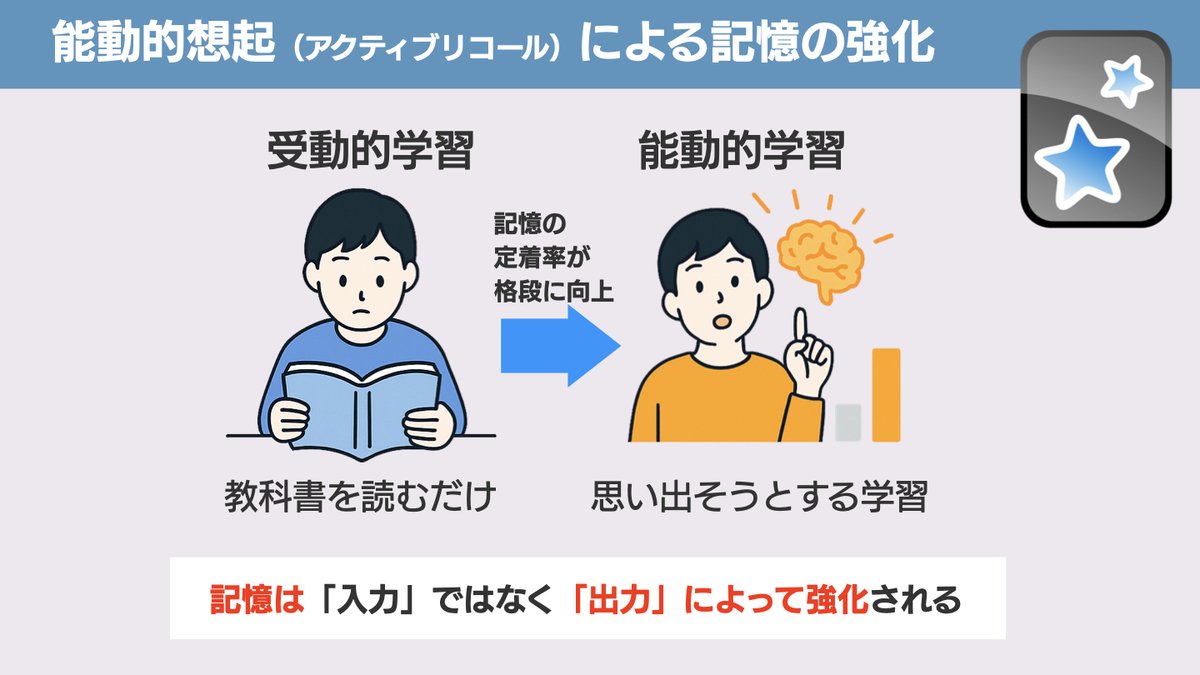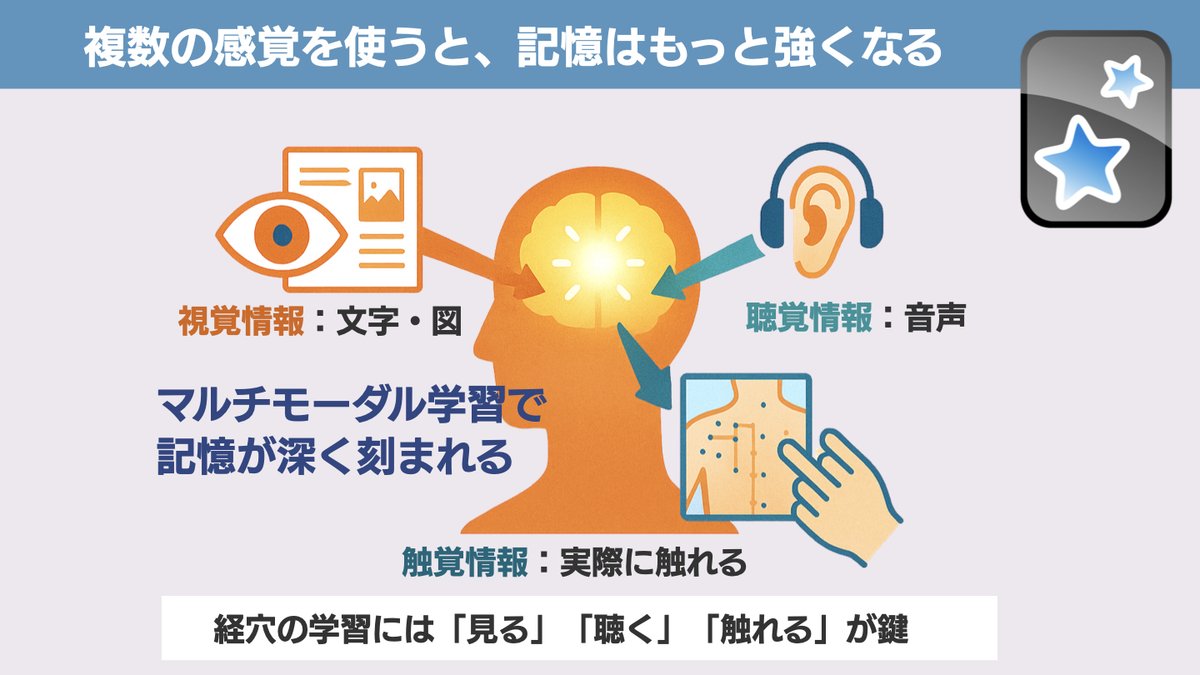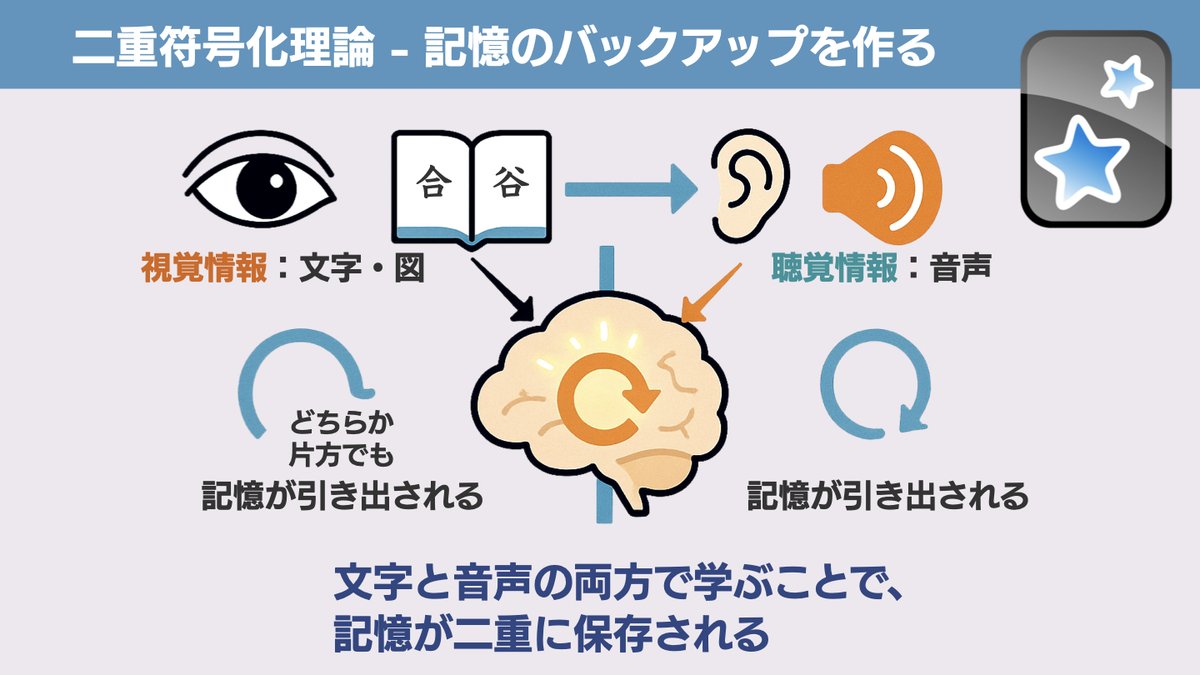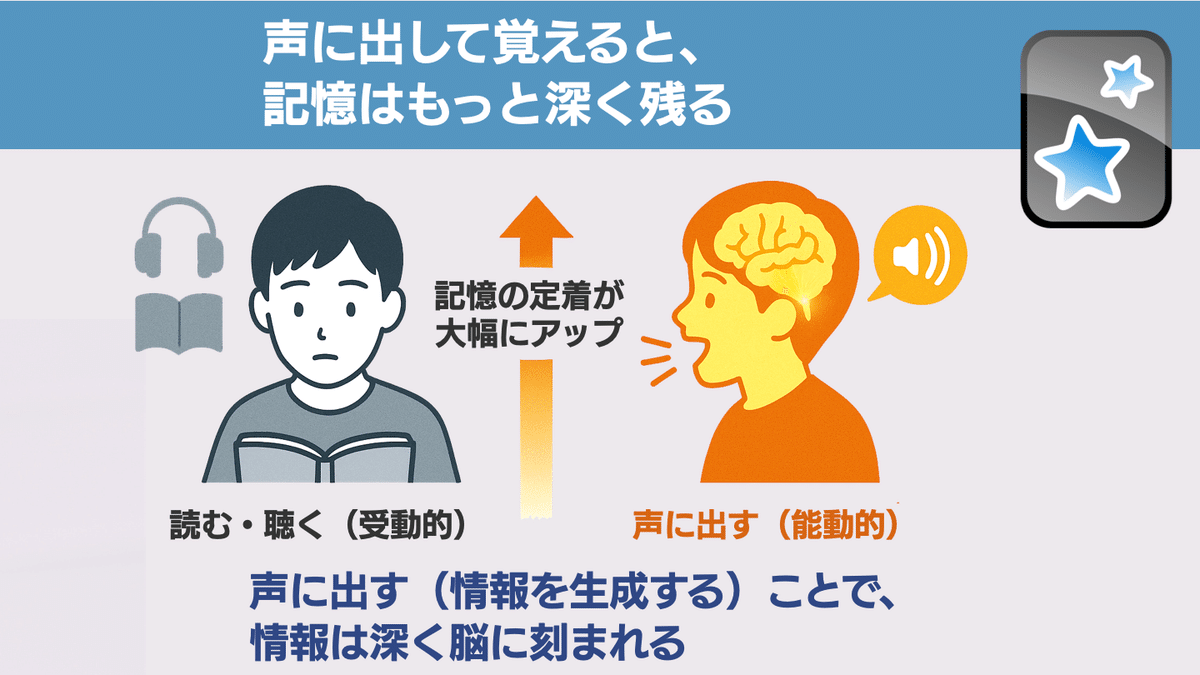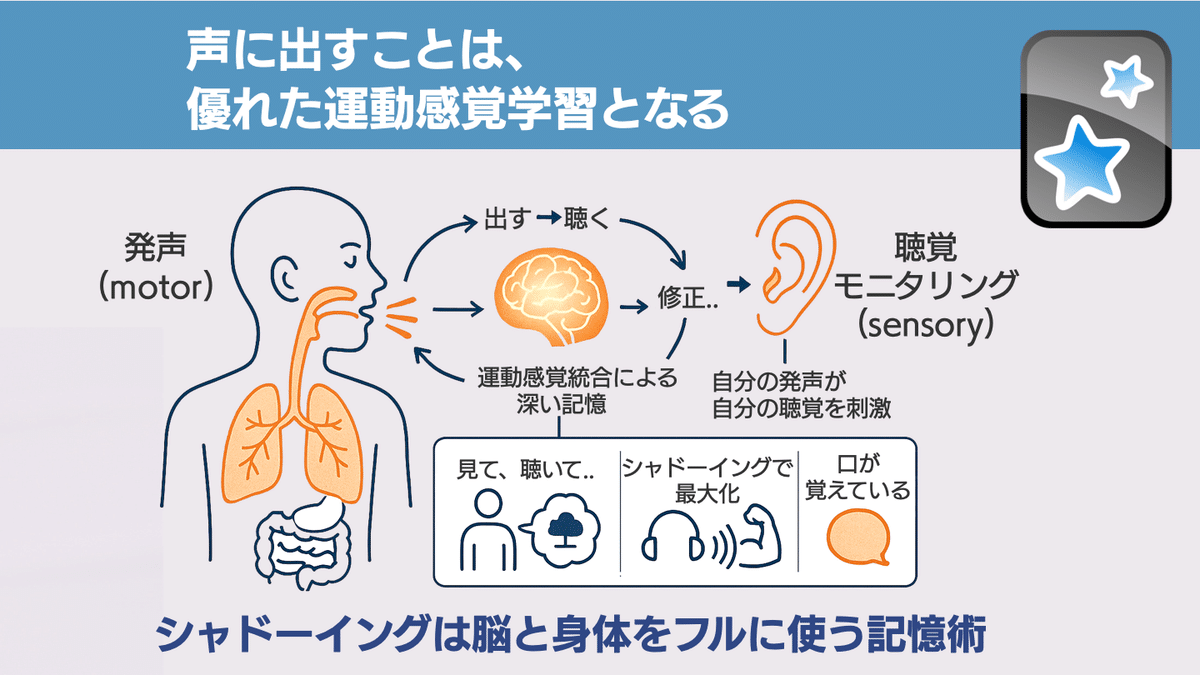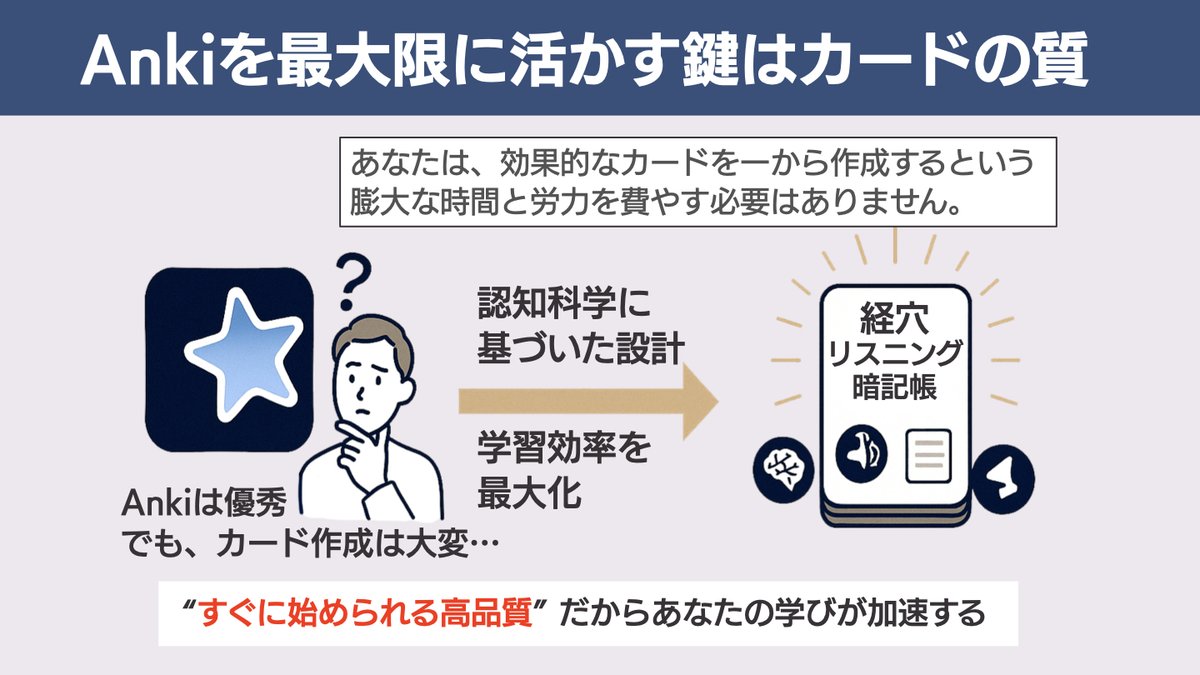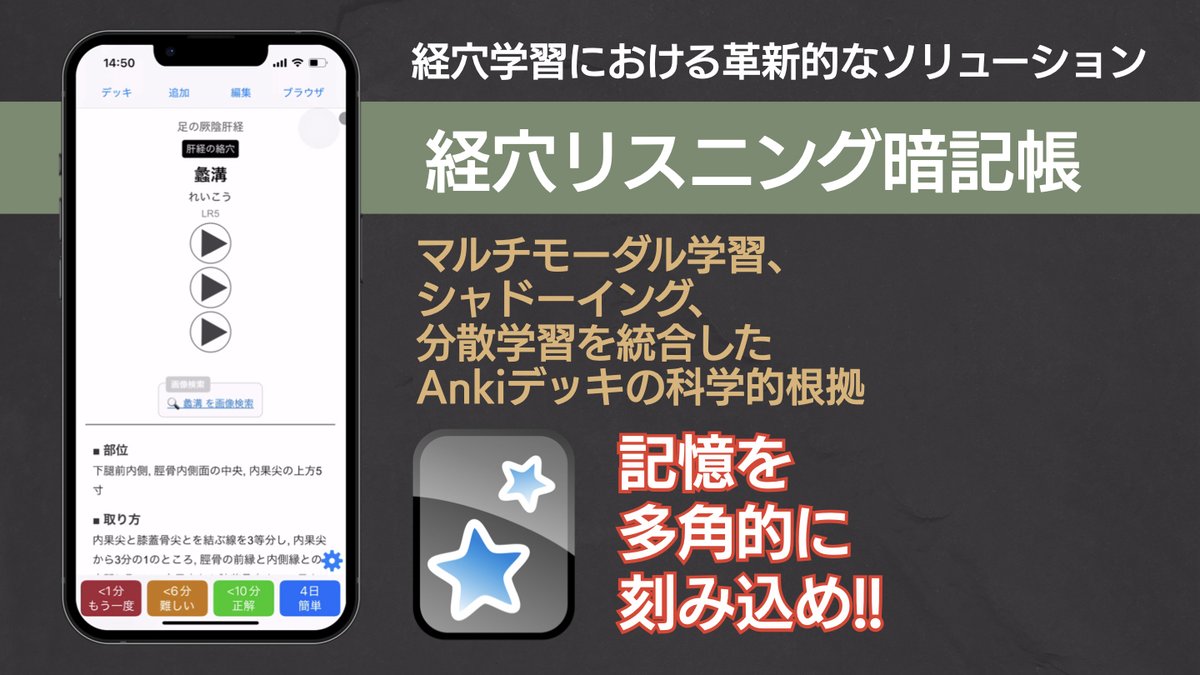引用論文
Acupuncture for the treatment of overactive bladder: A systematic review and meta-analysis
「過活動膀胱の治療に対する鍼治療:システマティックレビューとメタアナリシス」
背景
過活動膀胱(OAB)は、明らかな尿路感染症や神経病変を伴わないにもかかわらず、尿意切迫感、頻尿、夜間頻尿などの症状を呈し、デトルーサー筋の不随意収縮(デトルーサー過活動)が主たる病態メカニズムと考えられています。高齢化社会では有病率が増加傾向にあり、QOLを著しく低下させるため行動療法や抗ムスカリン薬、β3アドレナリン受容体作動薬など段階的治療が行われます。しかし、服薬継続率が低いことや口渇・便秘・視覚障害といった副作用、さらには侵襲的治療の適用制限など、未解決の課題が少なくありません。こうした状況下で、鍼治療(AT)は神経調節を介した非侵襲的かつ経済的な補完代替医療として注目され、多数のランダム化比較試験(RCT)が実施されています。本システマティックレビューとメタアナリシスでは、複数データベースにわたり発表されたRCTを網羅的に収集し、AT単独および薬物併用介入のOAB症状改善効果を統合的に評価しました 。
神経調節機序
鍼刺激は主に皮膚下のAδ線維やC線維を介して脊髄後角に伝達され、ゲートコントロール機序によりデトルーサー筋への興奮性入力を抑制するとされています。また、鍼による微小損傷が局所でサイトカインや神経伝達物質(エンドルフィン、セロトニンなど)を放出し、視床下部–脳幹–脊髄を経由して下行性抑制系を活性化することで膀胱過活動を抑制する可能性があります。さらに、自律神経系への影響として交感・副交感神経バランスを調整し、膀胱の蓄尿期と排尿期の機能調和を促す作用も示唆されています 。
方法
本レビューはPRISMA指針に準拠し、PROSPERO登録(CRD42014010377)プロトコルに基づいて実施しました。PubMed、EMBASE、Cochrane CENTRAL、AMEDに加え、中国・韓国の計八データベースを創設時から2022年2月まで横断的に検索し、“acupuncture”“overactive bladder”“detrusor instability”“urinary urgency”などをキーワードとして用いました。対象は刺鍼または電気鍼のみを介入とするRCTとし、アキュプレッシャーやレーザー鍼、複合介入試験は除外。主要アウトカムをOAB症状スコア(OABSS)と1日排尿回数、副次的アウトカムに失禁回数、改善反応率(改善例/総症例数)、有害事象(AEs)と定義。RevMan 5.4.1によるランダム効果モデルを用いてメタアナリシスを行い、バイアスリスク評価にはCochraneツール、エビデンス質評価にはGRADEを適用しました 。
結果
-
試験数・対象者:30試験、約2,000名が解析に含まれました 。
-
AT単独 vs. 偽鍼(sham AT):OABSSはMD −1.13(95% CI: −2.01~−0.26、p=0.01、I²=67%)で有意に改善。1日排尿回数もSMD −0.35(95% CI: −0.62~−0.08、I²=0%)で改善を示しました 。
-
AT単独 vs. 薬物療法:OABSSおよび排尿回数は薬物療法と同等(OABSS: MD −0.39、p=0.61、I²=94%;排尿回数: MD 0.74、p=0.05、I²=71%)で、有害事象はAT群で有意に少なかった(RR 0.38、95% CI: 0.16–0.92、p=0.03、I²=58%) 。
-
AT+薬物療法 vs. 薬物療法単独:OABSSはMD −2.28(95% CI: −3.25~−1.31、p<0.00001、I²=84%)、排尿回数はMD −2.34(95% CI: −3.29~−1.38、p<0.00001、I²=88%)、失禁回数はMD −0.46(95% CI: −0.60~−0.32、p<0.00001、I²=0%)、改善反応率はRR 1.21(95% CI: 1.11–1.33、p<0.00001、I²=0%)と、薬物単独群を大きく上回る改善を示しました 。
-
AT+通常ケア vs. 通常ケア:排尿回数・失禁回数は統計的有意差を示しませんでしたが、改善反応率はRR 1.30(95% CI: 1.01–1.67)で有意に向上しました 。
安全性
30試験中15試験でAEs報告なし、7試験でAEsなし、8試験で針刺痛や軽微な内出血が認められましたが、重篤事象は一例も報告されませんでした 。
エビデンスの質
GRADE評価では、多くのアウトカムが「低」または「非常に低」と判定され、その主因は盲検化困難・小規模サンプル・プロトコル異質性・高いI²値などです 。
考察
従来レビューに比べ18件の新規RCTを追加した本研究では、AT単独が偽鍼を上回る改善を示した点が特徴です。ATと薬物療法の併用はOAB症状の多面にわたり相乗的改善をもたらし、QOL向上にも寄与すると考えられます。一方、偽鍼モデルの適切性、多国間・多施設共同試験による一般化可能性評価、長期持続効果や費用対効果、安全性プロファイルの詳細評価は今後の重要課題です 。
今後の展望
-
経穴選択・保持時間・通院頻度・治療期間を標準化した鍼プロトコルの確立
-
大規模・多施設共同RCTの実施
-
改良された偽鍼条件および盲検化手法の最適化
-
自律神経機能や神経伝達物質解析を含むメカニズム研究
-
患者報告アウトカム(PROs)やQOL指標の導入
結論
鍼治療はOABの主要症状である尿意切迫感、頻尿、失禁を偽鍼に比して有意に改善し、薬物療法と同等の効果を低い副作用で示しました。さらに薬物療法併用では単独療法を大幅に上回る改善が得られ、OAB治療における有用な補完代替療法として期待されます。エビデンスの質向上とプロトコル標準化が今後の必須課題です 。
使用経穴
本レビューで頻用された代表的な経穴(保持時間約30分、得気誘発あり)
-
SP6(三陰交)
-
BL23(腎兪)
-
BL28(膀胱兪)
-
CV4(関元)
-
BL32(次髎)
-
CV3(中極)